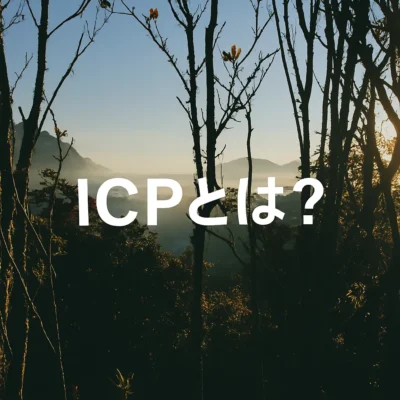地球規模での気候変動対策が喫緊の課題となる中、日本政府は、途上国の温室効果ガス(GHG)排出削減を支援しつつ、日本の削減目標達成にも貢献する画期的な国際協力の仕組みを推進しています。それが二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism:JCM)です。
JCMは、日本の優れた脱炭素技術やノウハウを、アジア、アフリカ、中南米などのパートナー国へ展開することで、これらの国々の持続可能な発展を後押しし、同時に地球全体の排出削減に貢献する「Win-Win」のフレームワークとして世界から注目されています。
このJCMの導入・普及を強力に後押しするために環境省が主導しているのが「脱炭素移行に向けた二国間クレジット制度(JCM)促進事業」です。この事業は、日本企業が途上国で具体的な排出削減プロジェクトを実施する際の資金的・制度的な支援を提供します。
本記事では、この国際協力とビジネスチャンスを両立するJCM促進事業について、その仕組み、支援内容、そして日本企業が獲得できる具体的なメリットに至るまでを、詳細かつわかりやすく解説します。国際市場での競争力強化と地球環境への貢献を目指す企業にとって、この制度の活用は欠かせません。
INDEX
二国間クレジット制度(JCM)とは
JCMは、日本の気候変動対策における国際協力の柱であり、途上国との協働を通じて排出削減を推進する制度です。
日本とパートナー国が共同で排出削減に取り組む制度
二国間クレジット制度(JCM)は、日本政府が二国間協定を結んだパートナー国において、日本の低炭素・脱炭素技術や製品、システムを導入することで実現したGHG排出削減・吸収量を、両国で共同して評価・算定する仕組みです。
- 基本理念: JCMは、地球規模での排出削減を効果的かつ効率的に進めるために、市場メカニズムを活用する枠組みとして設計されています。
- 特徴: 途上国にとっては、自国の経済成長と両立しながら、環境に優しい技術を導入できるメリットがあります。一方、日本企業にとっては、海外での事業展開と同時に、国の脱炭素化に貢献できる機会となります。
削減したCO₂量の一部を日本の削減実績として算定可能
JCMの最大の特徴は、パートナー国で実現したCO₂削減量の一部、または全てを、日本のGHG排出削減目標(NDC)の達成に活用できる点です。
プロジェクトによって削減された排出量は、JCMのルールに基づいて算定され、クレジットとして発行されます。このクレジットの配分比率は、原則としてプロジェクトごとに両国間で協議・決定されます。
これにより、日本は自国のコスト効率の良い技術を海外に展開することで、国内対策だけでは達成が難しい削減目標を、国際的な協力によって補完することが可能となります。
気候変動対策と国際協力の両立を目指す枠組み
JCMは、単なるクレジット取引に留まらず、以下の三つの目標を同時に達成することを目指しています。
- 気候変動対策: グローバルな排出削減に貢献し、途上国の持続可能な開発を促進する。
- 国際協力: 質の高いインフラや技術を提供することで、パートナー国との二国間関係を強化する。
- 経済成長: 日本企業の優れた低炭素技術の国際展開を促し、新たな市場の創出と経済成長の機会を生み出す。
JCMは、パリ協定においても、第6条に規定される国際的な排出量取引・協力メカニズムの一つとして位置づけられており、その重要性は国際的にも高まっています。
JCM促進事業の目的と背景
「脱炭素移行に向けた二国間クレジット制度(JCM)促進事業」は、JCMの制度的な枠組みを、具体的なプロジェクトの実行へと結びつけるための、資金的・技術的な支援プログラムです。
途上国の脱炭素移行支援
JCM促進事業の第一の目的は、途上国が低炭素経済から脱炭素経済へとスムーズに移行(トランジション)できるよう、具体的な支援を行うことです。
多くの途上国は、経済成長を優先する中で、環境負荷の低い技術への転換が遅れています。この事業は、日本政府がその初期コストを支援することで、途上国における再生可能エネルギー導入や高効率な省エネ設備の普及を加速させます。これは、途上国が自らの責任で設定するNDC(国別削減目標)の達成を強力に後押しすることにも繋がります。
日本の優れた低炭素技術の国際展開
日本は、世界トップレベルの省エネルギー技術や、高効率な再エネ関連技術を有しています。しかし、これらの技術は途上国において初期投資が高くなるため、市場普及が難しいという課題がありました。
JCM促進事業は、この「価格差」を補助金によって埋め合わせることで、日本企業の優れた技術が、途上国の市場に競争力をもって参入できるよう支援します。これにより、日本の環境インフラ関連産業や製造業の国際市場でのプレゼンスを向上させるとともに、技術の大量普及によるコストダウン(ラーニング・バイ・ドゥーイング効果)を期待します。
NDC(国別削減目標)達成への貢献
日本の政府全体としてのGHG削減目標(NDC)は非常に野心的であり、国内対策だけでは達成が困難な部分を、国際的な貢献によって補完することが認められています。
JCMを通じて獲得したクレジットは、この日本のNDC達成に活用されます。JCM促進事業は、このクレジット創出のための具体的なプロジェクトを数多く実行に移すことを支援するため、日本の気候変動政策全体において、極めて重要な役割を担っています。
対象国と連携の仕組み
JCM促進事業は、日本政府と政府間協定を締結した特定の国々との連携に基づいて実施されます。
アジア・アフリカを中心に展開するJCMパートナー国
JCMは、特定の国に限定されるものではなく、日本との合意に基づき、随時パートナー国が拡大しています。2024年現在、JCMパートナー国はアジア、アフリカ、中南米、オセアニアなど世界に20カ国以上に広がっています。
| 主なJCMパートナー国(例) | 主な関心分野 |
| アジア | ベトナム、インドネシア、タイ、フィリピン、モンゴルなど |
| アフリカ | エチオピア、ケニアなど |
| 中南米 | コスタリカ、チリなど |
日本企業は、これらのパートナー国の中から、自社の技術ニーズや事業戦略に合致する国を選定し、プロジェクトを構想する必要があります。
政府間協定を基にした共同プロジェクト体制
JCMプロジェクトは、民間企業が主導しますが、その基盤には日本政府と相手国政府間の「二国間協定」が存在します。
- JCM合同委員会(JC): 各パートナー国との間で設置される最高意思決定機関です。この委員会が、JCMの実施に関する基本ルールや、具体的なプロジェクト手法(Methodology)を承認します。
- 共同プロジェクト体制: 日本側実施者(日本企業など)と、相手国側実施者(現地企業など)が共同でプロジェクトを実施します。この共同体制のもとで、技術導入、資金調達、排出削減量のモニタリングが行われます。
相手国政府との承認手続きの流れ
プロジェクトの実施とクレジットの発行には、相手国政府による厳格な承認手続きが必要です。
- プロジェクト計画書の作成: 削減目標、導入技術、モニタリング方法などを記載した計画書を作成します。
- JCM登録: JCM合同委員会(JC)に対して、プロジェクトの登録を申請します。
- 相手国政府の承認: 相手国政府の指定機関(Designated National Authority: DNA)が、プロジェクトが自国の持続可能な開発目標に貢献するかどうかを審査し、承認を与えます。
- クレジット発行申請: 削減実績のモニタリング後、JCM合同委員会にクレジット発行を申請します。
JCM促進事業の支援は、特にこの複雑な申請・承認プロセスを円滑に進めるためのコンサルティングや調査費用にも活用できます。
対象となる事業・設備導入例
JCM促進事業の補助対象となるのは、明確なGHG排出削減効果があり、かつ日本の技術が活用されるプロジェクトです。
再生可能エネルギー導入(太陽光、バイオマスなど)
途上国の電力部門の脱炭素化は、最大の削減ポテンシャルを持つ分野の一つです。
- 太陽光発電(PV): 工場や商業施設での自家消費型太陽光発電システムの導入、大規模太陽光発電所の建設。
- バイオマス発電: 現地の未利用資源(例:パームヤシ殻、農業残渣)を活用した高効率バイオマスボイラー・発電設備の導入。
- 小水力発電: 地方の小規模河川を活用した小水力発電システムの導入。
日本の高効率なパネル技術や、安定供給を可能にする蓄電池技術・制御システムが導入されることが、補助の前提となります。
省エネ技術(高効率ボイラー、冷凍設備)
産業・業務用部門におけるエネルギー効率の改善は、即効性の高い削減策です。
- 高効率ボイラー・ヒートポンプ: 工場やビルにおける、従来の低効率ボイラーを日本の最新鋭の高効率設備に更新。排熱回収技術の導入。
- 高効率照明・空調: 現地工場や商業施設へのLED照明の一斉導入、高効率インバーター制御の空調・冷凍冷蔵設備の導入。
- エネルギーマネジメントシステム(EMS): 日本のEMS技術を活用し、工場やビルのエネルギー消費を最適化するシステム構築。
日本の設備は、耐用年数が長く、保守・運用(O&M)のノウハウも優れているため、途上国での長期的な運用と持続可能な削減効果が期待できます。
廃棄物管理や水処理などの環境インフラ改善
インフラ分野においても、GHG排出削減に貢献するプロジェクトが対象です。
- 廃棄物発電・メタン回収: 埋立地からのメタンガス(強力なGHG)回収・利用(発電など)、または廃棄物処理施設における高効率な焼却・発電設備の導入。
- 高効率水処理: 排水処理施設における、日本の高性能な膜分離技術や曝気制御技術の導入による、電力消費量の削減。
- 低炭素交通: 現地都市におけるEV(電気自動車)バスや燃料電池フォークリフトの導入、公共交通機関の効率化。
これらのプロジェクトは、CO₂削減と同時に、途上国の公衆衛生や生活環境の改善という持続可能な開発目標(SDGs)にも大きく貢献します。
補助内容と支援スキーム
JCM促進事業は、単なる資金提供に留まらず、プロジェクトの初期段階からクレジット発行・事業化に至るまでを包括的に支援するスキームを提供します。
設備導入費の一部を補助(最大50%程度)
この事業の最も大きな支援は、GHG排出削減を実現する設備導入費用の一部補助です。
- 補助対象経費: 導入する日本の低炭素技術・製品・システムの設備本体費、輸送費、据付工事費、試運転費など、設備導入に直接かかる費用。
- 補助率の目安: 設備導入にかかる費用の最大50%程度が補助されます。(補助率は年度や事業の内容によって変動します。)
この補助金は、前述の通り、日本の技術が途上国で市場参入する際の「初期コストの差」を埋めることを目的としています。この補助金があることで、採算性が厳しかったプロジェクトも、事業化の可能性が大きく高まります。
FS(実現可能性調査)から事業化までを支援
JCM促進事業は、本格的な設備投資に至る前の段階から、プロジェクトの成功確率を高めるための支援も行います。
- FS(フィージビリティ・スタディ)支援: プロジェクトの技術的な実現可能性、経済的な採算性、GHG削減効果の算定、現地ニーズの調査など、事業化に向けた事前調査の費用を補助します。
- 事業計画策定支援: JCMの複雑なルールに則ったプロジェクト計画書(PDD: Project Design Document)や、モニタリング計画の策定を、専門家の活用を含めて支援します。
このFS支援段階から関わることで、日本企業は低リスクで海外の新規市場の調査や開拓を行うことができます。
技術実証・普及段階でのサポート
補助金による資金支援のほか、環境省や執行団体による様々なソフト面でのサポートも提供されます。
- JCM手続き支援: 相手国政府との協議、JCM合同委員会への登録・承認手続きなど、複雑な国際的な調整プロセスをサポートします。
- モニタリング・報告支援: クレジット発行に必要な排出削減量の計測・モニタリング体制の構築や、JCMルールに則った定期報告書の作成を支援します。
- 成果普及: 採択されたプロジェクトの成功事例を国内外に積極的に発信し、他の日本企業や途上国への横展開を後押しします。
応募・採択の流れ
JCM促進事業は、国際的なルールに則るため、一般的な国内補助金よりも複雑なステップを踏みます。
公募要領を確認
環境省および事業の執行団体(例:地球環境センターGECなど)が公表する最新の公募要領と募集ガイドラインを詳細に確認します。特に、対象国、補助対象経費の範囲、JCMの基本的なルール、採択される事業の重点テーマなどを正確に把握します。
プロジェクト構想書の提出
事業化を検討している日本企業は、現地パートナー企業と共同で、プロジェクトの概要や技術、想定される削減効果などを記載したプロジェクト構想書(または提案書)を提出します。
- 提出内容: 導入技術の特定、実施体制(日本側・現地側)、想定されるGHG削減量、資金計画(自己負担・補助金希望額)、JCMクレジットの活用方針など。
審査・採択
提出された構想書に基づき、以下の観点から専門家による厳正な審査が行われます。
- CO₂削減効果の妥当性・実現性: 計画された削減量が技術的に達成可能か。
- 技術の優位性: 導入する技術が、現地における既存技術と比べて、どれだけ優位性があるか。
- JCM制度への適合性: JCMの対象となる事業であり、モニタリングが可能か。
- 事業の経済性・継続性: 補助金終了後も事業が継続し、削減効果が持続するか。
審査の結果、採択が決定された場合、企業には採択決定通知が送られます。
協定締結・事業実施
採択決定を受け、企業は補助事業実施に必要な交付申請を行い、交付決定を受けます。
- 協定締結: 日本側実施者と相手国側実施者との間で、プロジェクトの役割分担やクレジットの配分などに関する共同実施協定を締結します。
- 設備導入: 交付決定後、計画に沿って設備の調達、輸送、現地での据付工事を実施します。
- JCM登録: JCM合同委員会に対して、プロジェクトの正式登録手続きを行います。
モニタリング・クレジット発行
設備導入が完了し、稼働を開始すると、プロジェクトのモニタリング期間に入ります。
- モニタリング: 導入設備の効果測定データ(例:電力使用量、稼働時間)を継続的に収集し、GHG排出削減量を算出します。
- 検証: 第三者機関によるモニタリングデータの検証を受けます。
- クレジット発行申請: JCM合同委員会にクレジット発行を申請し、承認されれば、協定に基づき日本とパートナー国の間でクレジットが配分されます。
採択のポイントと評価基準
限られた予算の中で採択を勝ち取るためには、審査基準を深く理解し、計画書の説得力を高める必要があります。
CO₂削減効果の明確性
最も基本的な評価基準は、「どれだけCO₂を削減できるか」です。
- 削減量の根拠: 導入する技術や設備のスペック(例:効率、COP値)と、現地の稼働状況の予測に基づき、論理的かつ透明性をもって削減量を算定すること。
- ベースラインの妥当性: 削減量を評価する際の「ベースライン」(既存または一般的な技術を用いた場合の排出量)が、JCMの規定に従って適切に設定されているか。
技術の実現性・持続可能性
先進的であると同時に、現地での運用に耐えうる技術である必要があります。
- 現地適応性: 導入技術が、現地の気候、インフラ、メンテナンス能力などに適合しているか。
- 運用・保守体制: 補助金終了後も、現地パートナーが技術を自立的に運用・保守できるための、人材育成や技術移転計画が組み込まれているか。
パートナー国との連携体制
JCMは二国間協力であるため、日本企業と現地パートナー、そして相手国政府との関係性が重要です。
- 現地パートナーのコミットメント: 現地パートナーが、資金面、人材面、制度面でプロジェクトに強くコミットしていることを示す。
- JCMクレジットの活用方針: クレジットの配分、活用方法について、両国間で合意形成がなされているか。
費用対効果と波及性
- 費用対効果: 補助金1円あたりで、どれだけのCO₂削減効果が得られるか(円/t-CO₂)。この指標が高いほど、公的資金の投入効果が高いと評価されます。
- 波及性: 採択されたプロジェクトが、その国の他地域や他の産業分野にも横展開できるモデルケースとなる可能性が高いか。
成功事例の紹介
JCM促進事業は、アジアを中心とした多様な国で、日本の強みが活かされた多くの成功事例を生み出しています。
東南アジアにおける再エネ導入プロジェクト
- 国・地域: インドネシアの製造業工場群
- 技術: 日本の高性能な太陽光発電パネルと、高効率なエネルギー貯蔵システム(蓄電池)を導入。
- 成果: 工場群における電力の一部を再生可能エネルギーで賄い、CO₂排出量を大幅に削減。日本の蓄電池技術を活用することで、電力供給が不安定な現地でも安定した自家消費を実現し、脱炭素化と電力コスト削減を両立。
アフリカ地域での低炭素交通インフラ整備
- 国・地域: ケニアの港湾
- 技術: 港湾内物流で使用されるディーゼル式フォークリフトやトラクターを、日本の電動フォークリフトや高効率充電設備に置き換え。
- 成果: 港湾作業におけるディーゼル燃料消費を削減し、CO₂削減と大気汚染改善に貢献。電動化技術の導入と、現地の作業員へのO&M(運用・保守)研修を組み合わせることで、技術の持続的な定着を図った。
日本企業による現地パートナーとの協働モデル
- 国・地域: ベトナムの工業団地
- 技術: 日本の高効率冷凍冷蔵設備とEMS(エネルギー管理システム)を、工業団地内の食品加工工場に導入。
- 成果: 導入企業の電力消費量を平均30%削減。リード企業である日本企業が、複数の現地サプライヤーを巻き込み、エネルギーデータの可視化と運用改善のノウハウを継続的に移転するモデルを構築。JCMを通じて、日本の省エネコンサルティングというソフトスキルも輸出した事例。
日本企業にとってのメリット
JCM促進事業への参画は、日本企業にとって、単なる補助金獲得以上の、多角的なメリットをもたらします。
国際市場での競争力強化
- 初期投資の軽減: 補助金により、初期投資の負担が軽減され、日本の高価格帯の優れた技術が、海外の安価な競合製品に対しても価格競争力を持つことができます。
- 市場開拓の足がかり: JCMプロジェクトは、現地政府の承認を得て公的に進められるため、事業の信頼性が高く、その国や周辺国への新たな市場開拓の足がかりとなります。
環境貢献とESG評価の向上
- ESG評価の向上: GHG排出削減への国際的な貢献は、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)評価において非常に高く評価されます。これは、国内外の投資家からの評価を高め、資金調達面で優位に働く要因となります。
- 環境ブランドの確立: 途上国の脱炭素化を支援する企業として、企業の環境ブランドが確立され、グローバルなサプライチェーンにおける信頼性が向上します。
カーボンクレジットの取得による経営的利点
- 排出量削減実績の活用: JCMを通じて発行されたクレジットは、日本のNDC達成に活用されるだけでなく、企業が自社のカーボンニュートラル目標達成のためにオフセットとして活用することが可能です。(※クレジットの利用にはJCM制度のルールに従う必要があります。)
- 将来的な価値: 今後、グローバルにカーボンクレジット市場が拡大していく中で、クレジットの創出者としての地位を早期に確立することは、新たな収益源や経営戦略上の大きな強みとなります。
今後の展望と課題
JCMは、日本の国際的な気候変動対策の中核として、今後も拡大と制度の強化が進められる見込みです。
JCMの国際的拡大と制度強化
JCMパートナー国は今後も増え続け、日本企業の活動範囲はさらに拡大することが期待されます。また、パリ協定の第6条に関する国際ルールの整備が進む中で、JCMの制度もこれに合わせてより強固で透明性の高いものへと進化していく見込みです。
脱炭素移行支援への民間参加拡大
これまでは再エネや省エネが中心でしたが、今後は水素・アンモニアなどを用いた産業部門の脱炭素化(トランジション)や、デジタル技術を活用した高度なエネルギー管理など、より高度で大規模なプロジェクトがJCMの対象として期待されます。これにより、幅広い分野の日本企業の参画が促されます。
クレジット取引・活用の仕組み整備
発行されたクレジットの市場での流動性を高め、企業がより容易にクレジットを取引・活用できるための市場インフラやルールの整備が進められています。これにより、JCMプロジェクトの経済的インセンティブがさらに高まることが期待されます。
まとめ:日本の技術力と国際的貢献を踏まえたグローバル展開が成功の鍵
「脱炭素移行に向けた二国間クレジット制度(JCM)促進事業」は、日本の優れた低炭素技術を世界の脱炭素移行に活かすための、極めて戦略的な制度です。この事業は、地球温暖化対策という国際的な責務を果たしつつ、日本企業に新たな市場と経済的メリットをもたらす「技術と国際貢献を結ぶ架け橋」の役割を担っています。
この制度を最大限に活用し、成功に導くための鍵は、次の二点です。
- 技術力の適切な適応: 日本の技術を、現地の気候やインフラ、そして経済状況に合わせてカスタマイズ(現地適応)し、持続可能な運用が可能な形で導入すること。
- 長期的な国際連携: 単なる補助金事業としてではなく、現地パートナーや相手国政府との信頼に基づく長期的な協力体制を構築し、クレジット創出から事業化、そして次のプロジェクトへと繋がる持続的なビジネスモデルを確立すること。
今こそ、「日本の技術力と国際的貢献を踏まえたグローバル展開」を推進し、このJCM促進事業をテコに、企業の国際市場での競争力を高め、世界的な脱炭素社会の実現に貢献することが、日本企業の成功の鍵となります。
【参考文献・出典】
- 環境省「脱炭素移行に向けた二国間クレジット制度(JCM)促進事業」https://www.env.go.jp/content/000336015.pdf
- 環境省 二国間クレジット制度(JCM)公式サイトhttps://www.jcm.go.jp/
- 経済産業省「国際協力を通じたカーボンニュートラル推進施策」https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/
- UNFCCC(国連気候変動枠組条約)関連資料https://unfccc.int/