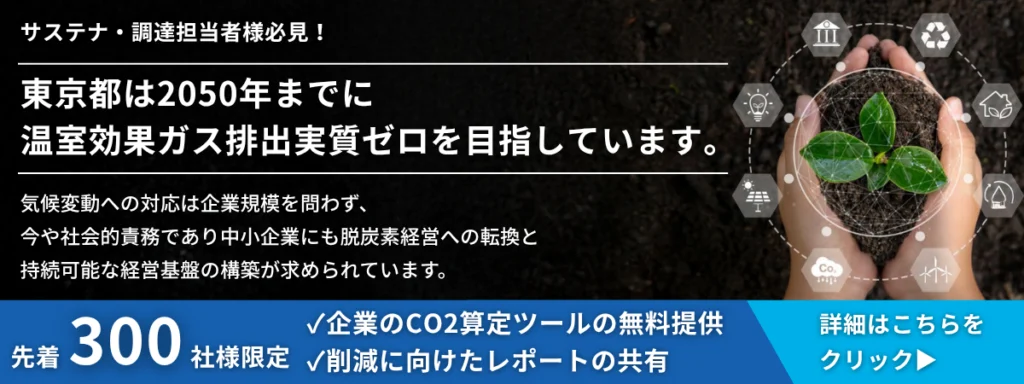企業にとって、脱炭素化の取り組みはますます重要な課題となっています。世界各国では、温室効果ガス排出削減に向けた新たな政策や技術革新が進む中、企業はその動向に迅速に対応することが必要です。
特にCO2排出量の削減に関しては、国内外で規制が強化されるとともに、企業の競争力にも大きな影響を与えるようになっています。
本記事では、世界的な脱炭素化の最新動向を紹介するとともに、CO2排出量の推移を振り返りながら、企業がこれらの変化にどのように適応し、戦略を練るべきかを解説します。
世界の脱炭素に向けた風潮
世界的に脱炭素化が加速しており、各国は温室効果ガス削減に向けた取り組みを強化しています。再生可能エネルギーや電気自動車の普及拡大など、さまざまな施策が進行中です。まずは、これらの動向と、気候変動の原因とされる要因について解説します。
(1)背景
脱炭素化が進む背景には、気候変動の影響を軽減するための国際的な認識の高まりが大きな要因です。
特に、パリ協定が重要な指針となっており、この協定では世界共通の長期目標として、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」としています。この目標に向けて、温室効果ガスの排出量をできるだけ早くピークアウトさせ、21世紀後半には排出量と吸収量のバランスを取ることが求められています。
また、COP26では、パリ協定第6条に基づく「市場メカニズム」の実施指針が長年の交渉の末に合意され、パリ協定のルールブックが完成しました。これにより、温室効果ガス削減のための市場メカニズムが機能し、国際的な協力が一層強化されました。また、インドが2070年を目標にカーボンニュートラルを宣言したことなど、脱炭素化に向けた国際的な機運がさらに高まりを見せています。
さらにCOP26では、154カ国・1地域がカーボンニュートラルを宣言し、国際的な協力が進む中、気候変動のリスクに対応するための政策が強化されています。
これらの国々のCO2排出量とGDPは、世界全体の79%、90%を占めており、脱炭素化が世界的な課題であることを示しています。また、金融面ではESG投資が急増し、気候関連情報の開示義務化が進展するなど、企業の社会的責任が一層求められています。
これにより、企業は脱炭素化に向けた対応を加速せざるを得なくなり、サプライチェーン全体での脱炭素化やグリーントランスフォーメーション(GX)が進行中です。加えて、デジタル技術を活用した排出量の可視化サービスなども、脱炭素化を支える重要な要素となっています。
出典:経済産業省 資源エネルギー庁「今さら聞けない「パリ協定」 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~」(2017/08/17)
(2)気候変動が原因とされる影響
気候変動による影響は世界中で深刻化しており、その影響は人々の生活に直接的に及んでいます。特に地球の平均気温の上昇が、極端な気象現象や異常気象の頻発を招いているのが現状です。
例えば、ブラジルや南アフリカでは大雨による洪水が多発し、多数の死者や甚大な被害が報告されています。また、フランス南西部やポルトガルでは山火事が繰り返し発生し、環境への深刻な影響を与えています。さらに、アメリカではハリケーンがもたらした甚大な被害により、多額の経済損失が記録されました。
これらの事例は、気候変動が引き起こす自然災害の増加を象徴し、気候危機への対応がますます急務であることを示しています。
出典:環境省「脱炭素社会の実現に向けた国際的な動向(1/2)」(2024/05/24)
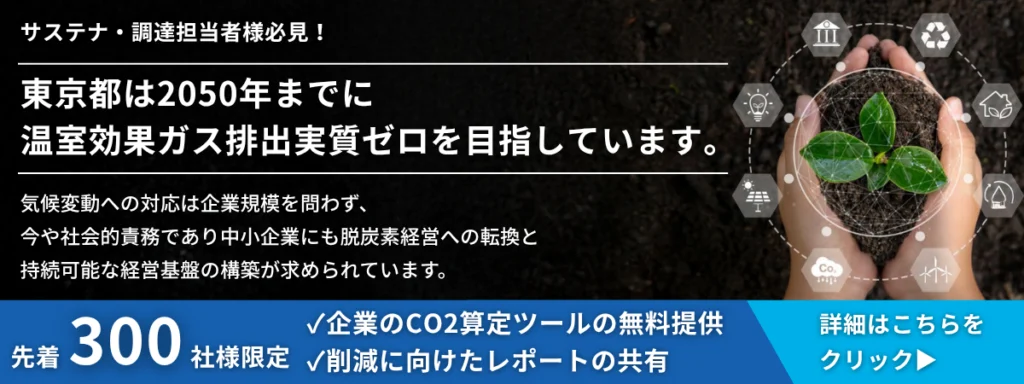
国内外のCO2排出量の推移と今後
ここでは、国内外のCO2排出量の推移と、それに伴う削減目標の変化について解説します。世界各国は温室効果ガス削減に向けた政策を強化しており、今後の取り組みが排出量に与える影響が注目されています。
(1)世界のCO2総排出量の推移
1990年代の世界のCO2排出量は205億トンであり、主な排出国は米国、EU27カ国、中国、ロシア、日本などが占めていました。特に米国は23.4%、中国は10.3%の割合を占めていました。
2021年には、世界のCO2排出量は336億トンに達し、排出量の多い国々では中国が31.8%、米国が13.6%となり、EU27カ国は7.7%、インドは6.8%となっています。予測される2030年には排出量は351億トンに増加し、中国が32.1%、インドが9.3%となり、その他の国々の排出割合も増加する見込みです。
出典:環境省「脱炭素社会の実現に向けた国際的な動向(1/2)」(2024/05/24)
(2)各国別|CO2排出量の比較
| 国名/年代 | 1990年代(205億t) | 2021年(336億t) | 2030年予測(351億t) |
| 米国 | 23.4% | 13.6% | 10.3% |
| 中国 | 10.3% | 31.8% | 32.1% |
| EU27か国 | 17.0% | 7.7% | 5.4% |
| インド | 2.6% | 6.8% | 9.3% |
| ロシア | 10.5% | 5.0%. | 4.7% |
| 日本 | 5.1% | 3.0% | 2.2% |
| ブラジル | 0.9% | 1.3% | 1.3% |
| その他 | 30.2% | 30.9% | 34.9% |
先進国ではCO2排出量の減少が予測される一方、インドなどの発展途上国は人口増加やインフラ整備などの開発により、CO2排出量が増加する傾向にあります。
特に、インドの排出量は2021年の6.8%から2030年には9.3%に増加すると予測されています。これに対して、米国やEU27か国はそれぞれ13.6%、7.7%から、2030年には10.3%、5.4%に減少する見込みです。中国は、世界の排出量の約32.1%を占め、引き続き最大の排出国としての地位を維持する予想です。
また、各国の削減目標について、2023年9月までに提出されたNDC(国別決定貢献)の分析によると、これらの目標を達成した場合でも、2100年時点での気温上昇は2.1~2.8℃になるとされています。1.5℃の目標達成には依然として大きなギャップがあり、特に2030年に向けては、2019年比43%減の削減が必要ですが、実現にはさらなる努力が求められます。
出典:環境省「国内外の最近の動向について(報告)」P5 (2024/02/14)
2030年に向けた世界の脱炭素に関する最新動向
ここでは、世界の脱炭素に関する最新動向について解説します。各国の政策や技術革新、企業の取り組みが進展する中、脱炭素化を目指す取り組みがどのように進んでいるのか、最新のデータとともに紹介します。
(1)日本
日本は、2030年度にCO2排出量を46%削減し、2050年のネットゼロ実現に向けて、地域と自然と共生しながら再生可能エネルギー(再エネ)の最大導入を目指しています。特に、地域資源を活用した再エネの導入は、地域経済の活性化や災害に強い地域づくりに貢献する重要な柱です。
太陽光発電においては、次世代型や初期費用ゼロ型の技術を導入し、公共施設やビル、工場、倉庫などの屋根や壁面への設置を集中的に進めています。
これにより、再エネ導入を加速するとともに、地域の経済循環やエネルギー自給率の向上を目指しています。また、再エネ設備の廃棄・リサイクルに関しては、技術革新と共に制度的な議論を進め、持続可能なエネルギー供給体制を確立するための計画的な対応を推進しています。
これらの取り組みにより、地域との共生を図りながら、再エネの最大限導入を目指す社会の実現を目指しています。
地域資源である再エネを活用し、地域経済の活性化や災害に強い地域づくりを進めており、特に太陽光発電では次世代型や初期費用ゼロ型の技術を導入し、公共施設やビル、工場の屋根・壁面への設置を重点的に拡大中です。
また、再エネ設備の廃棄・リサイクルについては、技術の高度化と制度的な議論を進め、持続可能なエネルギー供給体制を確立するための計画的な対応が進められています。
出典:環境省「国内外の最近の動向について(報告)」P14 (2024/02/14)
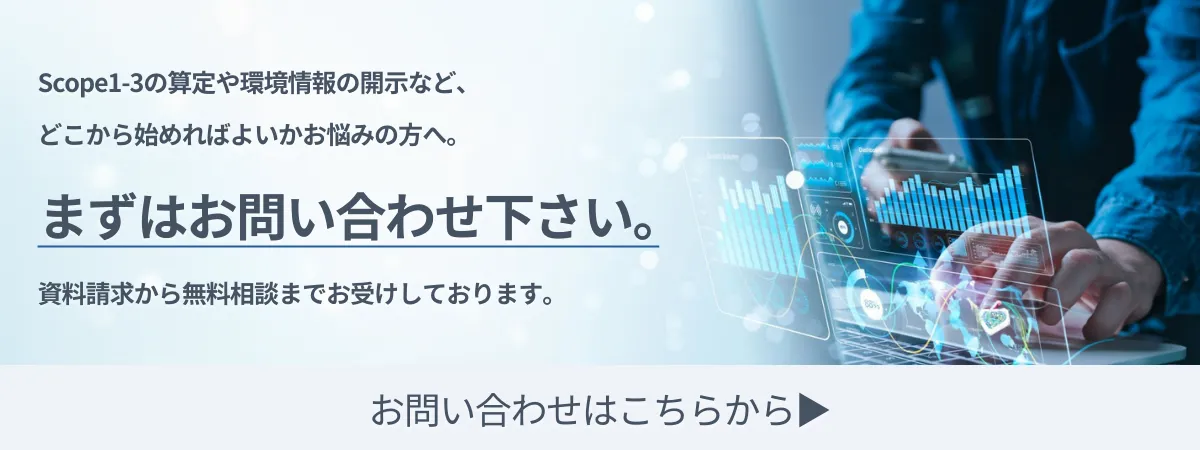
(2)主要国
以下は、主要国の脱炭素に向けた最新動向です。
■アメリカ
アメリカは、2050年までにカーボンニュートラルを実現するため、2035年までに電力部門の脱炭素化を達成することを目指し、さまざまなクリーンエネルギー施策を推進しています。
特に、運輸部門に重点を置き、電動車(EV)の普及を加速させています。2021年に発表された超党派インフラ投資雇用法では、EVインフラの整備に75億ドルを投入し、2030年までに50万基の充電施設の設置を目指しています。また、電気バスやゼロエミッション車の導入支援にも予算が割り当てられています。
さらに、産業部門の脱炭素化に向けて、クリーン水素技術の活用を含む製造業の変革を進めています。これに関連する政策として、電化が難しい分野の水素化や、持続可能な航空燃料(SAF)の導入が強調されています。2021年には、航空部門で2050年までにゼロエミッションを達成するための行動計画も公表されました。
加えて、住宅や家電の省エネ基準を見直し、連邦政府が所有する建物の省エネ基準を初めて策定したほか、低炭素製品の普及を進めるため、政府調達のクリーン化が進められています。
これらの取り組みは、カーボンニュートラル実現に向けた重要な進展を示しています。
アメリカは、2035年までの電力部門脱炭素化や2050年カーボンニュートラル実現を目指し、再生可能エネルギーの導入やEVインフラの整備、産業部門の電化・水素化を推進しています。特に運輸部門への投資が重点的に行われ、クリーン技術の普及が進められています。
■EU
EUは、2050年のカーボンニュートラル達成に向けた重要な政策パッケージ「Fit for 55」を策定し、温室効果ガス削減目標を引き上げました。
このパッケージでは、排出量取引制度の強化や再生可能エネルギーの導入目標引き上げ、エネルギー効率化の強化、ガソリン車の新車販売禁止、充電・水素インフラ整備などが盛り込まれています。
特に、2030年までに温室効果ガスを2005年比で61%削減することを目指し、運輸・建物暖房部門も対象に加えた排出量取引制度の拡大が重要な要素となります。また、再エネの割合を最終エネルギー消費の40%にまで引き上げる目標が設定され、エネルギー効率化の進展が求められています。
さらに、2021年12月には「Fit for 55パッケージ第2段」として、ガスの脱炭素化や省エネ改修の義務化を含む建物エネルギー性能指令の改正案が発表されました。これにより、低性能な建物の改修が義務づけられ、CO2除去技術の普及促進も進められています。
これらの施策は、EUが推進するグリーンディールの柱として、経済成長と気候変動対策の両立を目指しています。
EUは2050年のカーボンニュートラル達成に向け、「Fit for 55」パッケージを策定し、2030年の温室効果ガス削減目標を引き上げました。重点施策には、排出量取引強化、再エネ導入目標の引き上げ、エネルギー効率化の強化、ガソリン車の販売禁止、充電・水素インフラ整備が含まれています。また、建物の省エネ改修やCO2除去技術の推進も重要な政策として進められています。
■中国
中国は、2060年までのカーボンニュートラル達成を目指し、さまざまな施策を進めています。2021年には「2030年前カーボンピークアウト」計画を発表し、石炭消費の削減と再生可能エネルギーの拡充に力を入れています。
特に風力や太陽光発電の拡大を進め、水力や原子力発電の増設も行っています。さらに、省エネの強化が重点的に進められ、鉄鋼や建材産業でのCO2排出削減が具体的に計画されています。
加えて、EVの急速な普及も進んでおり、2035年までに新車販売の半分をEVにする目標を掲げています。また、工業分野では産業構造の最適化やグリーン化を推進し、エネルギー効率を向上させるための技術開発が進められており、特に住宅や公共建築物に対する省エネリノベーションや、新築建築物のグリーン建築基準への適合が求められています。
こうした取り組みを通じて、中国は脱炭素化を加速しています。
中国は、2060年までのカーボンニュートラル達成を目指し、2021年には「2030年前カーボンピークアウト」計画を発表。石炭消費の削減や再生可能エネルギーの拡充、EV普及を進めています。特にEV市場は急成長し、2035年には新車販売の半数をEVにする目標を掲げています。また、省エネの強化やグリーン建築基準の適用を進め、脱炭素化を加速しています。
■インド
インドは、2070年までのカーボンニュートラル実現を目指し、2030年までに非化石燃料由来の電力を500GWに拡大する目標を掲げています。そのとなる政策が「国家水素ミッション」であり、2021年8月にモディ首相が発表しました。
このミッションでは、2030年までにグリーン水素の年間生産量を500万トンに増加させることが目標とされています。具体策として、2022年2月に「グリーン水素・アンモニア政策」が発表され、再生可能エネルギーの優先購入や、州をまたぐ電力融通料金の25年間免除といった支援策が導入されました。
これにより、グリーン水素のコスト削減と産業利用の拡大が進められています。
また、産業部門では、省エネ法に基づく排出権取引の仕組みが2012年から導入されており、企業が省エネ目標を達成できるよう支援が行われています。さらに、都市化の進行に伴い、水道網の整備や住環境の改善も進められており、これらの施策は温暖化対策と経済成長の両立を図る重要な取り組みとなっています。
インドは、2070年までのカーボンニュートラルを目指し、2030年までに500GWの非化石燃料電力を導入する目標を設定しました。これに加え、グリーン水素の年間生産量を500万トンに増加させる「国家水素ミッション」を進めています。産業部門では、省エネ法に基づく排出権取引制度や、省エネ目標達成を支援する取り組みが行われています。
まとめ:脱炭素社会に向け、企業が未来を築く力となる
世界的に脱炭素に向けた動きが活発化していますが、脱炭素社会の実現には企業の積極的な取り組みが欠かせません。再生可能エネルギーの導入や省エネ技術の活用は、今後の成長を支える要素となり、持続可能なビジネスモデルを構築することで、環境への貢献だけでなく競争力を高めることに繋がります。クリーンな未来に向けて、脱炭素社会に繋がる一歩を踏み出してみましょう。
アスエネ株式会社は、企業の脱炭素化をトータルで支援します。
アスエネのサービスでは、脱炭素ロードマップの策定やLCA(ライフサイクルアセスメント)分析、さらにトランジション・ファイナンスを活用するための戦略設計をサポートしています。科学的根拠に基づいたデータと専門知識により、企業が透明性を確保し、投資家や社会からの信頼を得るお手伝いをいたします。
脱炭素化を加速し、持続可能な未来を共に築きましょう。