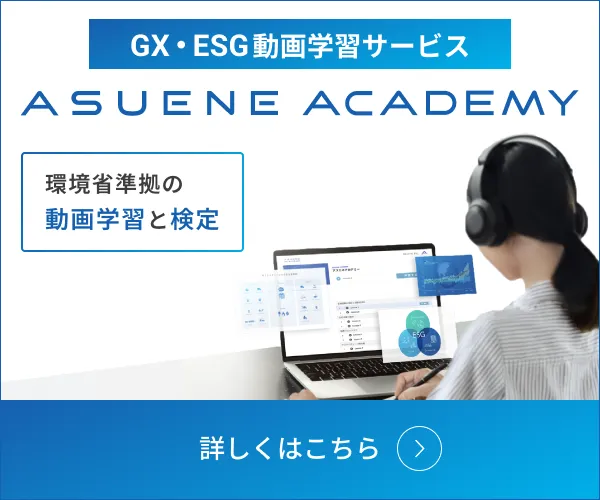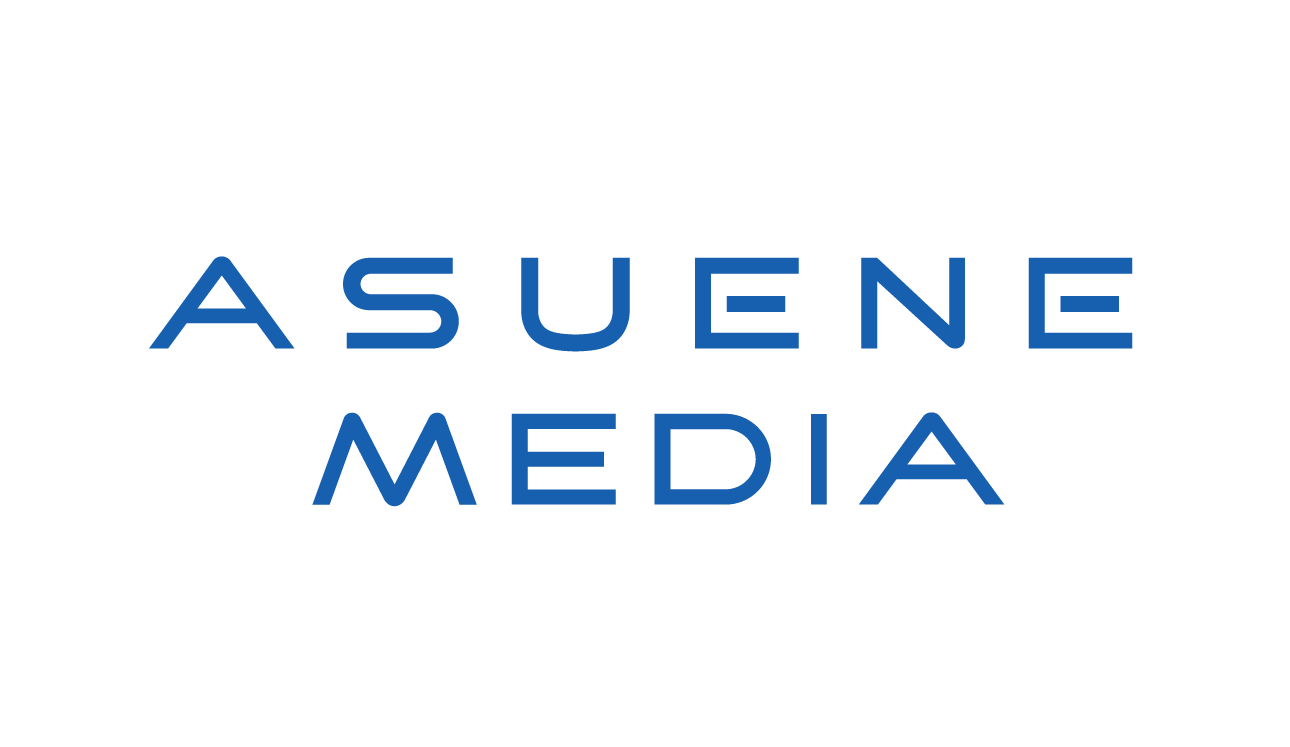CCSとCCUSは、地球温暖化を抑制するためのCO2(CO2)回収技術です。これらの技術は目的や手法に違いはあるものの、産業界をはじめとする多くの分野でのCO2回収に効果的とされており、持続可能な未来への道を切り開くものとして期待されています。
特に世界的な気候変動対策の一環として、国内外でその効果と実用性についての議論が活発化しているのが現状です。本記事では、CCSとCCUSの基本的な違いやメリット、さらに技術的・法令に関する課題について詳しく解説します。
INDEX
CCS・CCUSとは?概要と違いについて
CCSとCCUSの基本的な概要とその違いについて解説します。
(1)CCS・CCUSの概要
CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)とCCUS(Carbon dioxide Capture Utilization or Storage)は、工場や火力発電などから排出されるCO2を大気中から分離し、回収する技術です。これらは、従来の化石燃料の使用抑制や再生可能エネルギーの利用拡大などとは異なり、CO2の回収と管理に特化している点が大きな特徴です。これにより、産業分野でのCO2回収が現実的に進めることが可能となり、気候変動対策として世界的に注目されています。
出典:環境省「CCUSを活用した カーボンニュートラル社会の 実現に向けた取り組み」
(2)CCS・CCUSの違い
CCSとCCUSは、火力発電所などから排出されるCO2を大気中へ放出させないための技術です。主な違いは、分離・回収後の処理方法にあります。以下では、CCSとCCUSそれぞれの具体的な技術についてご説明します。
■CCS
CCSは、CO2を分離・回収し、安全な場所に貯留する技術です。専用の分離回収液を用いて、火力発電所や工場などから排出されるCO2を他のガスから分離し、陸上や海上のパイプライン、船舶輸送などを通じて地中や海底に貯留します。
■CCUS
CCUSは、回収したCO2を貯留するだけでなく、有効利用する技術です。具体的には、燃料やプラスチック、ドライアイスの製造、石油増進回収などに活用されます。
このように、CCSはCO2の貯留に特化し、CCUSは回収後にCO2を有効利用する点が大きな違いです。
出典:環境省「CCUSを活用した カーボンニュートラル社会の 実現に向けた取り組み」p2 p3(2020年2月)
CCS・CCUSが重視される理由
CCSおよびCCUSが重視される理由は、地球温暖化対策における長期的な目標達成のためです。2015年に合意されたパリ協定では、気温上昇を2℃未満に抑えるという目標が掲げられました。
また、2050年までにカーボンニュートラルを達成し、2030年までには2013年度比で温室効果ガスを46%削減する目標もあります。これらの目標達成に向け、CCSは重要な役割を担っており、特に2060年までの温室効果ガス合計量の14%をカバーすることが期待されています。
CCS/CCUSのメリット3つについて
CCSとCCUSには地球温暖化対策において大きなメリットがあります。以下は、CCS・CCUSに取り組む3つのメリットです。
(1)CO2(CO2)の大幅な抑制が可能
CCS・CCUSは、大気中へのCO2の放出を大幅に抑制することが可能な技術です。これらの技術は、火力発電・ごみ焼却場・製鉄など幅広い産業分野に導入できるため、より多くのCO2を回収できると期待されています。
事実、環境省によると、出力80万kWの石炭火力発電所にCCSを導入した場合、年間約340万トンのCO2の放出を防ぐことができると試算しています。このように、CCS・CCUSは産業界での実用性が高く、国や企業が掲げるカーボンニュートラルの達成に向けて重要な役割を果たすと見込まれています。
(2)炭素の循環利用に役立つ
CCUS技術を活用することにより、炭素の循環利用を可能にします。たとえば、ゴミ焼却とCCUSを組み合わせることにより、大気中へのCO2の放出を減らすことが可能です。
その他、再生可能エネルギー由来の水素とCO2を反応させることによって、メタンなどの化学原料の生産にも繋がります。このように、排出されたCO2を単なる廃棄物として扱うのではなく、持続可能な形で循環させることができるため、地球規模の炭素循環の促進に大きく貢献します。
(3)再生可能エネルギーの貯蔵や有効利用に活用できる
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、地球温暖化対策に欠かせない技術ですが、出力が変動しやすく、余剰電力を貯蔵する仕組みが必要です。一つの方法は水素を製造して貯蔵することですが、インフラ整備が十分に整備されていません。
一方、CCUS技術を活用して水素とCO2からメタンを製造することにより、既存の都市ガス用インフラを活用し、余剰電力を有効に貯蔵・利用できます。これにより、再生可能エネルギーを効率的に普及させることが可能です。
出典:環境省「CCUSを活用した カーボンニュートラル社会の 実現に向けた取り組み」p2(2020年2月)
CCS・CCUSが抱える3つの課題
地球温暖化対策の効果に優れるCCS・CCUSですが、取り組むうえで解消すべき課題があることも事実です。主な課題は、以下の3つが挙げられます。
(1)技術的課題の解決
CCS/CCUS技術はCO2の回収・貯留・利用に効果的ですが、いくつかの技術的な課題を抱えています。まず、CO2の分離・回収にかかるエネルギー消費が大きく、導入には数百億円規模のコストがかかるため、単独で導入できる企業は限られているのが現状です。
また、回収したCO2を安全かつ長期間にわたって貯留するための地質条件の調査や管理が求められます。さらに、CO2を有効利用する技術開発も進んでいますが、商業的な規模での運用にはさらなる研究が必要です。
(2)貯留能力の拡張性や貯留適地の確保
CCS/CCUS技術は、CO2の貯留能力の拡張性や貯留適地の確保といった課題を抱えています。貯留するための地質条件は厳しく、適切な貯留地を見つけるには詳細な調査が必要です。さらに、十分な容量を持つ貯留地が限られていることから、大量のCO2を安全に貯留し続けるための選択肢は限られています。
これに加え、貯留地までの輸送インフラの整備や、地域住民の理解を得ることも大きな課題です。現在、国の調査によって判明している11地点(合計160億トン分)の貯留地について、民間事業者による経済性などの分析・評価が実施されており、試掘などの開発が期待されています。
(3)関連法案の整備の必要性
CCS・CCUS技術の普及には関連法案の整備が欠かせません。現状では、CO2の回収・貯留・利用に関する具体的な規制やガイドラインが不十分であり、技術導入の課題となっています。
現在、国が先頭に立ち、技術導入による環境への影響はもちろん、CCS事業の推進や導入コスト低減に向けた取り組みや支援策に関する議論が進められています。法整備が進むことで、企業が安心して技術を導入できる環境が整い、CCS・CCUSの普及が加速することが期待されます。
出典:経済産業省「経済産業省におけるCCUS の取組み」p19 p28
CCS・CCUS導入に関する世界と日本の取り組み
ここでは、世界と日本におけるCCS・CCUS導入の取り組みと進展について詳しく解説します。
(1)世界の取り組み
世界では、2000年代後半からCCSの事業化に向けた取り組みが進められています。以下は、アメリカ・イギリス・EU(欧州)・ASEAN(アジア)の取り組みです。
■アメリカ
アメリカは、2009年頃にCCS事業法が整備され、貯留槽を利用する権利や事業者の責任範囲の取り決めが定められました。
また、2021年にはインフラ法により、CCS事業に対して120億ドルもの予算措置、2022年に成立したインフレ削減法(IRA)による税額控除の規模を拡充し、実質的に国がCCSコストを負担する形式が取られるなど、CCS普及に向けた取り組みが進んでいます。
さらに、CCUSについては45Q税額控除の拡大・延長を通じて推進が図られており、インフラ投資・雇用促進法において、今後5年間でCCUSバリューチェーン全体に約120億米ドルを提供するなど、積極的に取り組んでいます。
技術面においても、アメリカ中西部で3つの大規模なCO2輸送パイプラインを建設する動きが進んでいます。これは、中西部、主にアイオワ州のトウモロコシを使用したエタノール生産工場や肥料工場から放出されるCO2を圧縮輸送し、貯留することが目的です。
出典:JETRO(日本貿易振興機構)「CCUS普及のカギを握るパイプライン、中西部開発の行方は(米国)」
■イギリス
2008年に、CO2の貯留を規制する「エネルギー法2008」を皮切りに、2023年にCO2貯留・輸送に関する事業規制の導入を行っています。また、排出者向けに200億ポンド(約3.6兆円)もの支援を決定するなど、積極的なCCS普及に取り組んでいます。
CCUSについては、2030年までに最大10億ポンドを投資することを皮切りに、4つの産業クラスターでCCUSハブ設立支援を予定しています。また、CCUSへの民間投資を呼び込むため、政府支援を前提としたCCUSビジネスモデルの構築を始めています。
また、技術面においては、イギリス政府が掲げる2050年ネットゼロ達成に向けて、2025年までにCCUSを2カ所、2030年までに4ヵ所を設置し、年間最大1000万トンのCO2回収を目指しています。それに伴い、イングランド北東部のハンバーやティーズサイド地域をはじめとした重工業地域では、企業の脱炭素化およびCCUSを活用したブルー水素やグリーン水素を製造するプロジェクトが進んでいます。
出典:JETRO(日本貿易振興機構)「英国の主要な産業クラスターにおける CCUS プロジェクトの動向 ~イングランド北東部ハンバー地域~」p4
■EU(欧州)
EUでは、2009年にCCS指令を成立し、EU各国でのCCS法整備を促進させています。また、2024年には石油業界などに対し、2030年5000万トンのCO2貯留容量の開発に向けた貢献を義務付ける「ネットゼロ産業法」を成立させるなど、CCSへの取り組みが活発です。
また、CCUSに関しては、2021年12月に炭素除去量の算定と認証コストの提案を記載した「Sustainable Carbon Cycles(持続可能な炭素循環)を採択したことに加え、資金提供プログラムなどでの支援を進めています。
現在、欧州全体を繋ぐCO2輸送ネットワークの構築が進められています。 すでに地方、地域、国レベルで複数のプロジェクトが始動しており、2030年までに6,700~7,300キロメートル、2050年までに15,000~19,000キロメートルまで拡大する可能性あると発表されています。
出典:EUサイエンスハブ「CO2輸送インフラ:2050年までに気候中立を達成するための鍵」
■ASEAN(アジア)
インドネシアは、2023年3月にCCS事業に関する省令および、2024年2月に越境輸送に関する大統領令を公表しています。また、マレーシアでは、2024年内のCCS関連法の成立を目指しており、タイでは法整備を進めています。
また、2021年6月には、アジアレベルでのCCUSの発展を目指す「アジアCCUSネットワーク」が立ち上げられました。
これは、ASEAN10カ国に加え、アメリカ、日本、オーストラリア、さらに100を超える国際機関や企業、金融機関などが関与する産学官プラットフォームです。CCUS活用に向けた知見の共有や事業環境整備を目指し、各国と連携してCCUSの取り組みが本格的に始動しています。
一例として、インドネシアでは経済成長に伴うエネルギー需要の増加により、CO2排出量が増加しています。そのため、日本政府にCCS技術の共同研究および開発を要請しました。
それにより、現在、インドネシアのグンディガス田において、ガス生産処理施設から放散されている年間30万トンものCO2をパイプライン輸送による地下圧入で回収する技術の開発を進めています。これは、低コストでCO2の地下貯留が可能であり、JCM(二国間クレジット制度)スキームを活用するための実現可能性調査も行われています。
出典:経済産業省「「アジアCCUSネットワーク」が立ち上がりました」
このように、CCS・CCUSの取り組みは世界的に進んでいます。
出典:資源エネルギー庁「日本でも事業化へ動き出した「CCS」技術(前編)〜世界中で加速するCCS事業への取り組み」
出典:経済産業省「CO2分離回収技術開発に関連した 国内外の情勢について」p16
(2)日本の取り組み
世界と同様に、日本でもCCS事業に向けた取り組みが活発化しています。2021年に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」における「2050年カーボンニュートラル実現」に向けたひとつに、CCSが挙げられています。
それに伴い、CCS事業の支援が進み、2023年3月にはCCS長期ロードマップが策定されました。これは、2030年までの事業開始を目標に、年間貯留量600~1200万トンの確保を目指す内容です。CCS事業のビジネスモデルの確立に向けて、CO2の「分離・回収」「輸送」「貯留」の各段階において民間事業者を選定し、技術やコスト面などの幅広い支援を行っています。
また、環境省ではCCUSに係る取り組みとして、エネルギー対策特別会計を活用した環境省の温室効果ガス回収施策を実施しています。これは、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比46%削減、さらに50%に挑戦するものです。
さらに、「炭素中立」「循環経済」「自然再興」の経済や社会への統合的な転換の実現に貢献することを目標にしています。具体的な内容は、以下の通りです。
【第一の柱】脱炭素でレジリエントかつ快適な地域・くらしの創造
- 地域脱炭素ロードマップに基づく、脱炭素先行地域づくり
- 脱炭素の基盤となる重点対策の全国実施の推進、地域の実施体制構築の積極的支援
【第二の柱】バリューチェーン・サプライチェーン全体の脱炭素移行の促進
- 民間投資を活用した企業・バリューチェーンの脱炭素経営の実践
- 地域・くらしを支える物流・交通、資源循環などサプライチェーン全体の脱炭素移行の促進
【第三の柱】地域・くらしの脱炭素化の基盤となる先導技術実証と情報基盤等整備
- 再エネ由来水素やCO2の利活用、革新的な素材・触媒などの脱炭素技術の開発・実証の推進
- 地域・くらしや社会インフラの脱炭素移行に必要な先導技術の社会実装を加速化
- 脱炭素化に不可欠な情報基盤の整備
【第四の柱】世界の脱炭素移行への包括支援による国際展開・国際貢献
- パリ協定第6条に位置づけられる二国間クレジット制度や温室効果ガス観測技術衛星による排出量検証を通じて、途上国等の脱炭素移行支援
- アジア・ゼロエミッション共同体構想の実現に向けた支援
- 世界の排出削減に主導的役割の実現
また、苫小牧で実施されたCCS大規模実証実験では、国内初となるCO2分離・回収から貯留までの一貫システムを実証しました。事業内容は、出光興産の北海道製油所で発生した約52%濃度のCO2をPSAオフガスから回収し、1.4 kmのパイプラインで輸送して地下に圧入。 異なる深さの2層の貯留層に圧入し、安全なプロセスを確立しました。
結果として、目標の30万トンのCO2圧入を達成しただけでなく、分離・回収から圧入・貯留までの操業および安全・環境管理など、各種モニタリングにおいてCCSが安心・安全なシステムであることが確認されました。
このように、日本は国内の取り組みだけでなく、脱炭素社会に向けた世界の主導的役割に向けて取り組んでいます。
出典:環境省「CCUS and Carbon Recycling in Japan Present and future」p5
まとめ:カーボンニュートラル達成には企業のCCS・CCUSへの協力が不可欠!
今回は、CCS・CCUSの概要と国内外の取り組みを中心に解説しました。CCS・CCUSは、世界的な問題に挙げられている気候変動問題の解決に繋がる革新的な技術です。しかし、本格的な導入には、多大なコストや技術面の課題が残されています。
現在、政府の支援のもと、特定の事業者がCCS事業に取り組んでいますが、2030年の本格導入を達成するためには、企業のCCS・CCUSへの積極的な協力が欠かせません。政府の政策支援や法整備が進む中、企業は技術導入や設備投資を通じて、CO2回収の主体的な役割を果たすことが求められています。
特に、CO2の分離・回収から輸送、貯留までの各段階での民間企業の参入が、技術の進展とコスト削減に繋がります。持続可能な未来を築くためにも、産業界全体で連携し、積極的に取り組んでいきましょう。