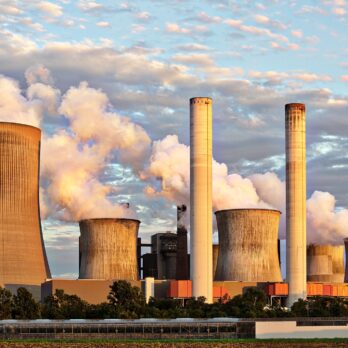企業経営の中心課題として「Scope3排出量削減」が急速に存在感を増している。カーボンニュートラルへの移行が世界的に加速するなか、企業の排出量は「自社(Scope1・2)」だけでなく「取引先を含むサプライチェーン全体(Scope3)」が問われる時代になった。
こうした流れのなか、環境省が推進する 「企業間連携による省CO2設備投資促進事業」 が注目されている。本事業は、リード企業と取引先企業が連携してScope3削減に取り組む企業を対象に、省エネ・再エネ設備導入などを支援する補助金制度だ。
本記事では、本事業の構造・対象要件・申請のポイント・実際の効果・Scope3削減を進めるための実務的なポイントまで、採択を狙う企業に向けて徹底解説する。
INDEX
Scope3排出量とは?
1.1 Scope1〜3の違い
企業の温室効果ガス排出は以下の3分類で整理される。
- Scope1(直接排出)
事業者が燃料を燃焼させた際の排出。例:自家用車、ボイラー、ガス設備など。 - Scope2(間接排出/エネルギー起因)
電力・熱の購入に伴う排出。例:オフィス電力、工場電力。 - Scope3(その他の間接排出)
企業活動の上流・下流を含むサプライチェーン全体で発生する排出。
原材料調達、物流、製品使用、廃棄までを含むため、最も範囲が広い。
1.2 Scope3削減が企業の課題となる理由
Scope3の排出量は多くの企業で「総排出量の70~90%」を占めると言われる。
つまり、Scope1・2だけ減らしても、全体最適としては不十分になりやすい。
企業がScope3削減に踏み出す理由は3つある。
- 取引先からの要請が急増している
大手企業がサプライチェーン排出量の開示を進めており、中小企業にもデータ提出が求められるケースが増加。 - ESG評価・金融評価の指標化
銀行融資や投資判断において、Scope3が審査項目化されつつある。 - 国際基準(GHGプロトコル)への整合が求められる
海外取引ではScope3の開示を前提とする例も多い。
事業の目的と概要
2.1 事業の目的
環境省が実施する「企業間連携による省CO2設備投資促進事業」の目的は以下のとおり。
- サプライチェーン全体の脱炭素化を加速する
- リード企業が中小企業を巻き込み、Scope3削減を促す
- CO2見える化・省エネ投資・再エネ導入などを包括的に支援
単一企業ではなく、複数の企業が“連携体”として取り組むことが特徴である。
2.2 事業の概要
本事業の基幹は「連携による設備導入支援」で、以下を補助対象とする。
- 省エネ設備(高効率機器、インバータ、空調更新、LEDなど)
- 再エネ設備(太陽光発電、蓄電池など)
- データ計測・排出量管理システム
- Scope3算定・可視化システム
- 連携体で協働するためのシステム整備
「連携して削減する」という視点が、従来の単独企業向けの設備補助金と異なる最大のポイントだ。
対象となる企業
3.1 リード企業と取引先企業の連携が条件
本事業は単独企業の申請はできない。
申請主体は リード企業(主導企業)を中心とした“連携体” であり、以下のような形式になる。
- 大手企業(リード企業)+中小のサプライヤー数社
- 中堅企業(焦点企業)+物流会社や協力工場
リード企業の役割
Scope3削減はリード企業の責任が大きい。
リード企業は次のような“司令塔”の役割を担う。
- 連携体の組成・取りまとめ
- サプライヤーの排出量把握の支援
- 削減計画の策定
- 補助金の申請主体(事務局機能)
- 設備投資の妥当性評価
- 導入後のデータ回収とモニタリング
大手企業にとっては、Scope3(カテゴリ1・4・12など)削減がESG格付けの重要指標となるため、この事業を活用する価値は極めて大きい。
取引先企業(サプライヤー)の役割
中小企業は以下の役割を担う。
- 実際の設備更新によるCO2削減
- エネルギー使用量・稼働時間などのデータ提供
- リード企業との協働作業(改善会議参加など)
- 設備導入後の効果測定
- 現場改善による効率化
中小企業側のメリットは“自社負担が大きく減り、脱炭素の第一歩を踏み出せる”ことだ。
3.2 中小企業も参加しやすい制度設計
本事業は中小企業が参加できるよう工夫されている。
- データ提出が簡略化
- リード企業のサポートがある
- 設備投資のコストを大きく抑えられる
- 専門家派遣の支援がある
サプライチェーン構造をもつ業界であれば、製造・物流・小売・サービスなど幅広く対象となる。
補助対象と内容
4.1 補助対象の範囲
補助対象は大きく3カテゴリに分かれる。
① 省エネルギー設備
- 高効率空調
- 産業用高効率機器
- インバータ化
- ボイラー更新
- LED照明
② 再生可能エネルギー導入
- 太陽光発電設備
- 蓄電池
- 自家消費型の再エネシステム
③ 連携体の協働に必要なシステム
- 排出量の可視化システム
- エネルギー管理システム(EMS)
- 共同管理プラットフォーム
- データ収集・分析システム
Scope3削減には「可視化」が不可欠であり、そのためのシステム導入が補助される点が大きい。
4.2 補助率・上限額(目安)
年度により変動するが、一般的な目安は以下。
- 補助率:1/2程度(中小は2/3の場合も)
- 補助上限:数千万円~1億円超規模
- 連携体の規模に応じて増額可能
特に中小企業にとっては、通常の省エネ補助金より「連携のメリットにより採択率が高まりやすい」という特徴がある。
申請条件と要件
5.1 共同申請(連携体の組成)が必須
申請には 複数企業が共同で計画を提出すること が求められる。
- リード企業:計画策定・全体管理
- 取引先企業:設備導入・排出削減
- 共通システム:連携体の排出量共有・管理
5.2 削減効果の実効性が審査のポイント
採択審査では以下が重視される。
- 連携体としての削減量
企業個別ではなく「チーム全体」でのCO2削減効果が重要。 - 設備投資の妥当性
投資対効果、削減貢献度、費用妥当性が評価される。 - 実現性・スケジュールの精度
データ収集方法や管理方法が明確であるかが問われる。 - Scope3削減への寄与度
特にリード企業のサプライチェーン削減戦略の整合が見られる。
申請から採択までの流れ
本事業の流れは次のように整理される。
6.1 公募要領を確認
最初に行うべきことは、「最新版の公募要領」と「Q&A集」の確認である。
特に注意すべき項目は以下の通り。
- 対象となる設備の分類(省エネ・再エネ・デジタル管理など)
- 共同申請(連携体)の定義
- 要件に該当しないケース(単独申請、事前着手、データ不備など)
- 補助率の上限と予算規模
- スケジュール(公募開始〜採択発表〜完了期限)
申請期間が短い年度もあり、「情報収集が遅れる=申請できない」 という状況が実際に起きている。
特に大企業がリード企業となる場合、内部稟議に時間がかかるため、早めの情報共有が必須である。
6.2 連携体を組成
この事業の最大の特徴は 「企業間の連携が前提であること」。
リード企業は次のような観点でパートナー企業を選定する必要がある。
- Scope3(カテゴリ1・3・4など)に関係する取引先であるか
- CO2削減につながる設備投資の余地があるか
- 設備導入後も継続的にデータ提供が可能か
- 経営層が脱炭素に理解を示しているか
- 申請書類・証憑提出に協力できる体制があるか
実際には、以下のような企業が選ばれやすい。
- 製造業の下請け企業(老朽設備の更新余地が大きい)
- 物流会社(燃料削減効果が大きい)
- 加工業・印刷業・食料品業など省エネ余地の大きい業種
「連携体内で役割分担を明確にする」 ことが採択率向上の重要ポイントである。
6.3 計画書提出・審査
申請書では、次の項目を論理的に説明する必要がある。
(1)連携体として取り組む理由
- リード企業のScope3削減に直結しているか
- なぜこの企業同士の連携が必要か
- 単独ではなく“共同申請”である必然性を示す
(2)設備投資の必要性と妥当性
- 現状のエネルギー消費の課題
- 導入する設備の性能・スペック
- 他の設備では代替できない理由
- 経済産業省の基準と比較した省エネ性能
(3)CO2削減効果
審査で最も重視される項目。
- 削減量(t-CO2)
- 投資額とのバランス(効率性)
- リード企業のScope3削減への寄与度
特に“削減量の根拠データ”が弱いと不採択につながりやすい。
電気使用量・稼働時間・燃料消費など、一次データでの説明が望ましい。
(4)データ管理方法
- 導入後の測定方法
- モニタリング体制
- データ連携(クラウド、IoT等)
補助金後の継続性も問われるため、「仕組みとして続く体制」を示すことが重要。
6.4 採択後に事業開始
採択通知の後、以下の手順で実行される。
- 設備の最終仕様確認
- 発注・契約
- 工事・設置
- 導入後の測定
- 報告書作成
- 連携体としての成果共有
特に重要なのは 事前着手の禁止。
1日でも早く発注してしまうと全額補助対象外になる。
多くの企業がここで失敗するため、採択通知前の発注は絶対に避ける必要がある採択通知後に設備発注が可能となる。事前着手は不可。
活用事例と効果
7.1 製造業における事例
背景
大手メーカーA社は、ESG評価を高めるため“サプライチェーン全体の脱炭素”を推進していた。
しかし、取引先である中小製造業B社・C社は老朽化設備が多く、CO2排出量が高止まりしていた。
●取り組み
A社をリード企業とし、B社・C社と連携体を組成。
導入した設備:
- 高効率モーター
- インバータ制御装置
- 省エネ型コンプレッサー
- 老朽照明のLED化
●効果
- 工場全体の電力使用量が 15〜22%削減
- A社のScope3カテゴリ1排出量を大幅に削減
- B社・C社の設備維持費が年200万円削減
- A社はESG評価レポートに改善実績を記載でき、株主からの評価向上につながった
- 省エネ補助金の加点対象となり、次年度の申請が通りやすくなった
「サプライチェーン全体での削減」により、全社の競争力が高まった典型例である。
7.2 物流業における事例
●背景
荷主企業D社は、Scope3カテゴリ4(輸送・配送)における排出量が多く、脱炭素が課題だった。
一方、配送企業E社は燃料費高騰によるコスト圧迫に苦しんでいた。
●取り組み
D社とE社が連携し、補助金を活用して下記を導入。
- 低燃費トラック
- EVバン
- 配送ルート最適化システム
- 積載率管理システム
- サプライチェーン全体の配送データ管理プラットフォーム
●効果
- 燃料費 10〜14%削減
- CO2排出量 8〜12%削減
- 積載率改善により配送回数が減少
- 荷主D社は、「脱炭素調達ガイドライン」で取組評価ポイントを獲得
- ESGレポートでサプライチェーン削減量を開示でき、金融機関からの評価も上昇した
特に、燃料価格が高騰した年は“脱炭素=コスト削減策”になったとして高く評価されている。
7.3 企業が実感した効果
単なるCO2削減・コスト削減以外にも、以下のような“経営インパクト”が得られている。
●ESG・金融機関からの評価向上
- 地銀・信金が「脱炭素の取り組み」を融資条件に反映
- ESG格付けの観点で高評価
- A行では「Scope3削減実績」を金利優遇に利用
●サプライチェーン強化
- 取引先からの信頼性向上
- 脱炭素対応を理由に価格交渉がしやすくなる
- 大企業のサプライヤー選定で“優良企業”として扱われる
●ビジネス面での波及効果
- 脱炭素PRを通じて採用力が向上
- 顧客向け提案資料の質が上がる
- 新規受注の際に「環境対応の格付け」が改善される
特に多かった声は次の通り:
「取引先からの信頼が明らかに変わった」
「設備更新のついでに経営効率まで良くなった」
「脱炭素が“義務”ではなく“利益”につながった」
Scope3削減を進めるための実務ポイント
8.1 データの可視化と共有が最優先
Scope3排出量を正確に算定し、削減目標を設定・実行するためには、バリューチェーンを構成する連携体(サプライヤー、製造委託先、販売代理店など)間で、データの種類と収集方法を統一することが重要です。具体的には、以下の主要データの統一が必要です。
- エネルギー・燃料データ: 各拠点で消費される電力、ガス、重油などの種類と使用量。再生可能エネルギー導入比率なども含めます。
- 使用量データ: 原材料、部品、間接材(消耗品など)の購入量や投入量。製品ごとの投入原単位を設定することも有効です。
- 生産量データ: 各工場の製品別生産量、またはサービスの提供量。
- 製品出荷データ: 製品の輸送距離、輸送手段、輸送量(重量または個数)。
- 廃棄物データ: 製造過程やオフィスから排出される産業廃棄物および一般廃棄物の種類と量。
これらのデータを、共通のフォーマット、計測単位、報告頻度で収集する仕組みを構築し、透明性をもって共有することが、削減策の立案と進捗管理の基盤となります。8.1.2 デジタルツールを活用した可視化
収集したデータを手作業で集計・分析することは非効率であり、ミスを招きやすいリスクがあります。Scope3対応の専用プラットフォームやデジタルツールを導入し、データの入力から集計、排出量への換算、そして排出源(カテゴリー)別の貢献度をリアルタイムで可視化することが、効果的な対策を打つための最優先事項となります。可視化されたデータは、取引先へのフィードバックや削減目標の共同設定の根拠となります。
8.2 取引先との協働体制を構築
Scope3排出量の約7割はサプライチェーンの上流(調達)または下流(販売・使用)で発生すると言われています。このため、「取引先を巻き込む」こと、すなわちバリューチェーン全体での協働体制の構築こそが、Scope3削減の最重要ポイントとなります。8.2.1 リード企業としての責任と支援
バリューチェーンにおいて影響力を持つ「リード企業(自社)」は、単に取引先にデータ提出を求めるだけでなく、削減に向けた取り組みを支援する責任があります。具体的な協働体制の構築ステップと支援内容は以下の通りです。
- 説明会とエンゲージメント: Scope3削減の重要性、自社の目標、取引先への具体的なデータ要求内容、そして協働のメリット(例えば、将来的な取引継続の条件になりうること、企業イメージ向上など)を伝える説明会を定期的に開催し、取引先の理解とコミットメントを引き出します。
- データ収集方法の統一と教育: GHGプロトコル(GHG Protocol)などの国際的な算定基準に基づき、取引先がデータ収集と排出量算定をスムーズに行えるよう、統一されたマニュアルやテンプレートを提供し、実務担当者向けのトレーニングを行います。
- システム導入支援: 特にデータ収集・管理体制が未熟な中小規模の取引先に対し、Scope3算定・報告を支援するシステムの共同導入や、安価なSaaSツールの推奨、技術的なサポートを提供します。
- 補助金申請サポート: 省エネルギー設備導入や再エネ導入など、取引先が行う削減投資に対して利用可能な国の補助金や優遇制度に関する情報提供や申請実務のサポートを実施し、経済的な負担軽減を図ります。
- 優良事例の共有と評価: 先行して削減に成功している取引先の事例を共有し、モチベーション向上に繋げます。また、削減目標達成度やデータ提供の協力度合いを評価し、サプライヤー選定基準に組み込むことで、取り組みを強化します。
この協働体制を構築することで、単なる排出量削減に留まらず、バリューチェーン全体のレジリエンス(強靭性)強化や新たなビジネス機会の創出にも繋がります。
今後の展望
9.1 Scope3対応は企業評価の新基準へ
今後、金融・投資・取引の基準としてScope3は必須項目化が進む。
9.2 脱炭素経営を進める企業の必須ステップ
- データ可視化
- 取引先との連携
- 設備投資による削減
- 中長期計画の策定
これらは国際競争力に直結する。
まとめ:Scope3削減は「連携」を軸にした脱炭素経営が重要
Scope3は単独企業では削減できない領域であり、サプライチェーン全体での“協働”が成功のカギとなる。
環境省の「企業間連携による省CO2設備投資促進事業」を活用することで、削減効果・コスト削減・ESG向上を同時に達成できる。
本記事で紹介したポイントを踏まえ、企業は早期にScope3対応を開始し、脱炭素化と経営価値向上の両立を実現すべき時代に突入している。