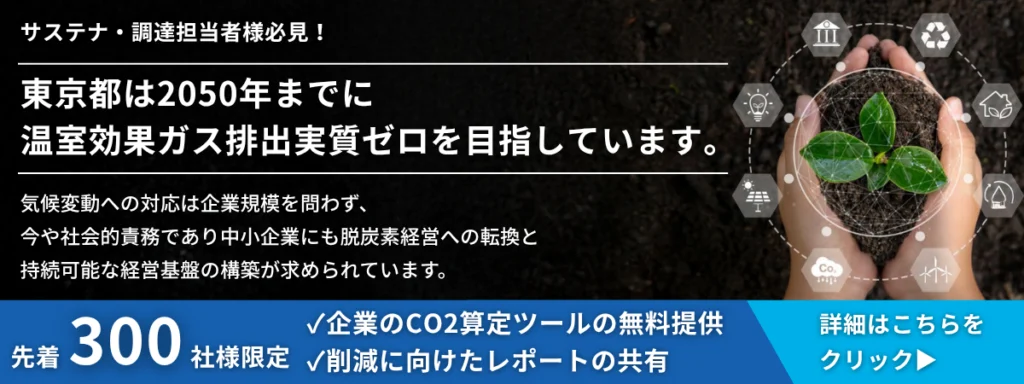日本の中小企業における“脱炭素経営”が急速に加速している。
気候変動対策が世界レベルで重要視され、各国が2050年カーボンニュートラルを掲げるなか、日本でも企業の温室効果ガス排出削減は「社会の要請」から「企業活動の前提条件」へと変化しつつある。
かつては大手企業だけの課題と考えられていた脱炭素だが、いまは取引条件や調達基準が厳しくなり、中小企業にも対応が求められている。特に製造業・建設業・物流業などは、大手企業のサプライチェーンに含まれるケースが多く、「CO2排出量の開示を求める書類」が届き始めた会社も少なくない。
また金融機関も、融資判断や金利優遇の基準として「脱炭素の取り組み」を扱い始めている。
この流れは中小企業にも確実に波及しており、「自社のCO2排出量を把握していないと不利になる場面」が増えている。
しかし実際には、多くの中小企業が次のような課題を抱えている。
- CO2算定のやり方がわからない
- データ入力や管理が難しそう
- LCAやスコープといった専門用語が理解しにくい
- 測定ツールの導入コストが高い
- 社内に環境担当者がいない
こうしたハードルを取り除く目的で、東京都が中小企業向けに開始したのが「無料のCO2算定サービス」である。
これは東京都環境公社が運営する “中小企業脱炭素経営 総合支援サイト(Planning Support)” の支援メニューの一つで、脱炭素に取り組みたい中小企業が“初期コストゼロ”で排出量の可視化に着手できる。
本記事では、この「先着300社限定」の無料CO2算定サービスの内容、申込条件、導入メリット、実際の使い方、事例、注意点まで徹底的に解説する。
脱炭素経営に興味がある都内中小企業、または大手企業から排出量の提出を求められ始めた企業にとって、本記事が最初の一歩となるだろう。
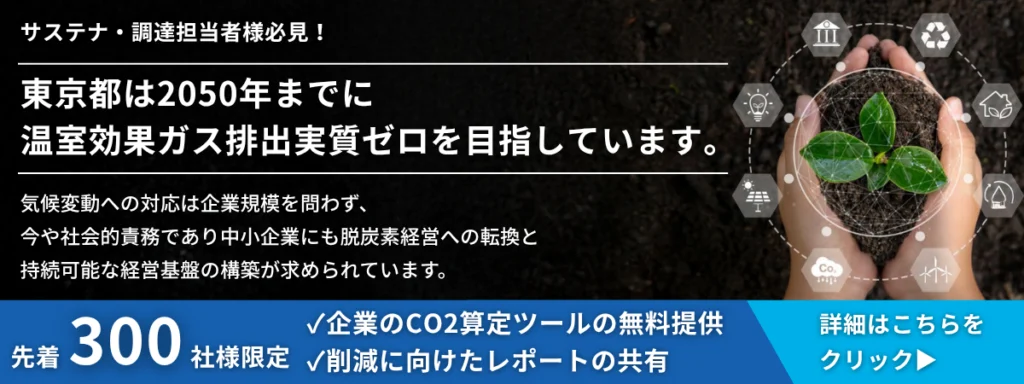
【先着300社様限定】CO2算定サービスの無償提供とは?
1.1 キャンペーンの概要と目的(都内中小企業の脱炭素経営推進)
東京都は、都内事業者の脱炭素化を後押しするため、CO2排出量の可視化を行う支援事業を実施している。特に中小企業は人員・専門知識・IT環境の面で脱炭素化へのハードルが高いため、「誰でも簡単に算定・管理ができる仕組み」を提供する必要があった。
そこで登場したのが 無料のCO2算定サービス(先着300社限定) である。
このサービスは、企業が持っているエネルギー使用量、購入品、廃棄物、物流などの基本データを入力するだけで、自動的にCO2排出量を算出できる仕組みを提供するものだ。
算定結果はレポートとして出力でき、取引先や金融機関への提出にも活用できる。
この制度の目的は大きく3つある。
- 中小企業が脱炭素経営の第一歩を踏み出しやすくすること
- サプライチェーン全体の排出量削減を加速すること
- 都内企業の競争力を向上させ、環境に強いビジネス基盤を作ること
特に「排出量把握」は脱炭素経営の“スタートライン”であり、ここがわからないままでは削減計画も立てることができない。東京都は、この最初の壁をなくすため、無償提供という思い切った支援策を打ち出したのだ。
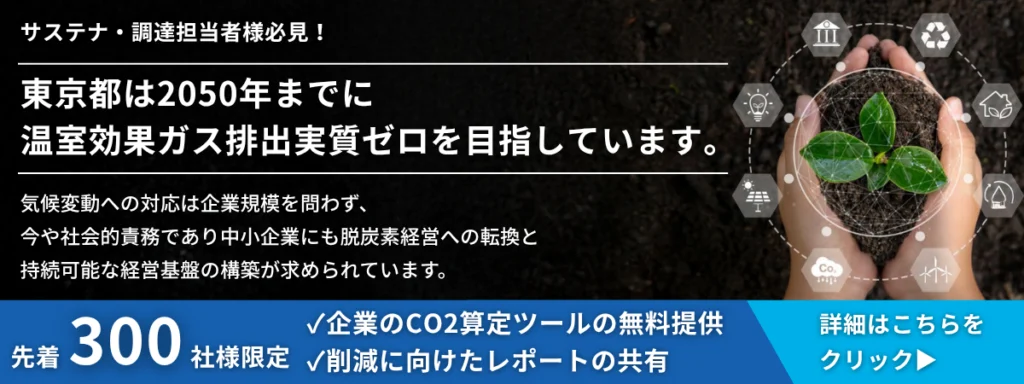
1.2 提供主体・支援内容・申込期間・無償提供の条件
公式サイトによれば、サービス提供主体は 公益財団法人 東京都環境公社 である。
中小企業向け環境支援に長年取り組んできた団体であり、脱炭素化に関する専門知識を持つスタッフがサポートを行う。
無償提供の主な内容は以下のとおり。
- CO2算定ツールの利用(スコープ1〜3の算定に対応)
- データ入力・管理機能の使用
- CO2算定レポートの発行
- 実際の電気・ガス・燃料使用量からCO2排出量を算出
- 専門スタッフによるアドバイス
- 削減に向けた改善ポイントの提示
- 省エネ・低炭素化の補助金紹介
- 脱炭素経営に関する相談対応
さらに企業のレベルに応じ、以下も支援される。
- 排出量の基準年設定
- 削減目標の考え方
- 排出量削減計画の作成支援
- 環境配慮契約やグリーン調達への対応方法
無償提供の条件としては、以下を満たす必要がある。
- 東京都内に事業所があること
- 中小企業であること(中小企業基本法に準拠)
- 脱炭素経営に関心を持ち、算定結果を活用する意志があること
- 申込が先着枠300社以内であること
申込期間は年度によって異なるが、毎年「枠が埋まるスピード」が速いため、できるだけ早い申込が推奨されている。
1.3 「先着300社限定」という枠の意味と競争率の高さ
この支援制度で最も重要なポイントが「先着300社限定」という枠である。
東京都は約14万社以上の中小企業を抱えており、300社というのは全体の0.2%程度に過ぎない。
実際、前年の同様の支援施策では以下のような傾向があった。
- 受付開始から数週間で枠がほぼ埋まる
- 製造業・サービス業を中心に申込が殺到
- 大手企業から排出量開示を求められた企業の申し込みが多数
- 脱炭素に関心を持つ企業の増加
つまり、脱炭素の波が本格的に中小企業に押し寄せていることを示している。
枠が埋まってしまった場合、次年度まで利用できない可能性が高く、早めの申込を行う企業が多い。特に自社がサプライチェーンに組み込まれている場合、排出量開示の提出期限が迫っているケースもあり、「優先順位の高い経営課題」になっている企業が増えている。
1.4 対象企業の要件
本無償の支援サービスは、環境経営や脱炭素経営への第一歩を踏み出そうとしている意欲的な企業を対象としており、以下の条件をすべて満たすことが要件となります。必須となる条件
- 事業所の所在地
- 東京都内に主たる事業所、または支店・営業所を保有していることが必須となります。これは、本支援サービスが東京都内企業の脱炭素化を促進することを目的としているためです。
- 企業規模
- 中小企業基本法に定める「中小企業」に該当することが必要です。具体的には、業種に応じて資本金または従業員数のいずれかが規定の基準以下である企業を指します。大企業の子会社であっても、この定義に合致すれば対象となり得ます。
- 業種の不問
- 製造業、建設業、サービス業、卸売業、小売業など、業種による制限は一切ありません。あらゆる業種の中小企業からの申し込みを歓迎します。
- 取り組み意欲
- 環境経営、特に脱炭素経営・地球温暖化対策に新たに取り組みたいという明確な意向がある企業を対象とします。既に高度な取り組みを行っている企業よりも、これから始める企業への支援に重点を置いています。
- データ提出の協力
- CO2排出量(Scope1, Scope2)の算定に必要なデータ、具体的には直近1年分の電気使用量、ガス使用量、燃料(ガソリン、軽油、重油など)の使用量などの各種エネルギーデータを正確に提出できることが条件となります。データが不足している場合、適切な算定ができないため、ご協力をお願いいたします。
- 申込枠の確保
- 本サービスは提供できる支援数に限りがあるため、申込枠内であることが最終的な要件となります。先着順または選考により決定される場合がありますので、お早めの申し込みをお勧めします。
本支援サービスの特長
上記の通り、対象企業の要件は非常に柔軟に設定されており、特に厳しい制限は設けられていません。これは、「脱炭素に関心がある企業なら誰でも申込できる制度」として、間口を広く設けているためです。
特に、脱炭素対応の専任担当者や体制が社内にまだ存在しない企業、あるいはCO2排出量の算定すらこれから始める企業にとって、この無料サービスは大きなメリットがあります。専門的な知見を持つコンサルタントが無料でCO2排出量の現状把握から削減に向けた具体的なアクションプラン策定までをサポートするため、安心して脱炭素経営への第一歩を踏み出すことが可能です。
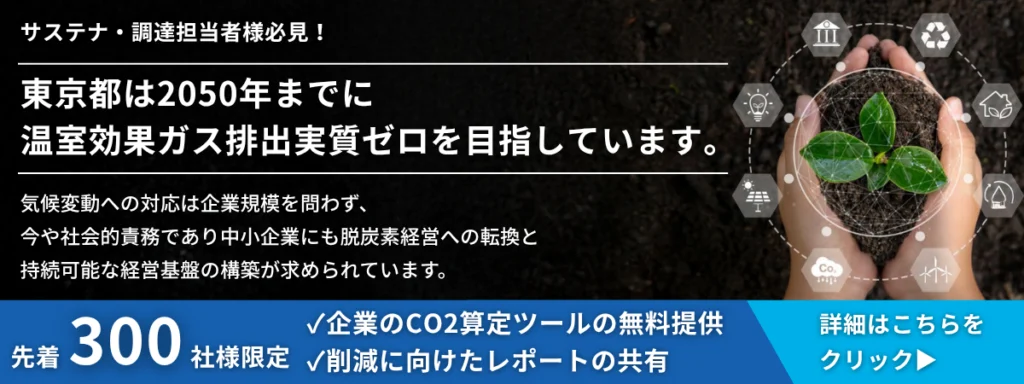
CO2算定サービスで何ができる?
2.1 CO2排出量の見える化(スコープ1〜3対応)
CO2算定サービスの最大の機能は「排出量の見える化」である。
国際基準であるGHGプロトコルに準拠し、スコープ1〜3を算定できる。
- スコープ1:自社が直接排出するCO2(燃料使用など)
- スコープ2:他社から供給された電力・熱の使用による排出
- スコープ3:原材料の購入・輸送・廃棄など“間接排出”全体
多くの企業が躓くのはスコープ3だが、東京都のツールは業種別に必要データが整理されており、専門知識がなくても入力しやすい。
これにより、企業は自社がどの部分でどれだけ排出しているのか、一目で把握できる。
2.2 自社の排出源を把握し、改善策を立てる仕組み
算定結果をもとに、排出源が明確になり、具体的な改善点を特定できます。排出量が多い項目を特定することで、効果的な対策を優先的に実施することが可能になります。
例えば、以下のような詳細な分析に基づいた改善策の検討が可能です。
- 物流・輸送部門の排出が多い場合:
- 配送ルートの最適化を図り、走行距離を短縮します。
- 燃費効率の良い車両や、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)といった低排出ガス車の導入を検討します。
- 共同配送やモーダルシフト(トラックから鉄道・船舶への切り替え)を推進し、積載効率の向上を目指します。
- 製造設備の稼働による排出が高い場合:
- 生産プロセス全体を見直し、エネルギー効率の高い最新の製造設備への入れ替えを検討します。
- 設備のアイドリングストップや、運転時間の見直し、生産計画の最適化による稼働率の改善を図ります。
- 未利用の熱源を回収・再利用する排熱回収システムの導入を検討します。
- 事務所・拠点における電力使用量が多い場合(スコープ2の排出):
- 高効率なLED照明や、人感センサー、調光システムなどを導入します。
- 高性能な断熱材や遮熱フィルムの利用、空調設定温度の適正化、高効率な空調設備(GHPやEHP)への更新を行います。
- 再生可能エネルギー由来の電力プランへの切り替えや、太陽光発電設備の導入を検討します。
- 廃棄物由来のCO2が課題となる場合:
- 廃棄物の分別を徹底し、リサイクル率の向上を目指します。
- 製造工程における歩留まり改善や、製品設計の見直しを通じて、そもそもの廃棄物発生量の削減に取り組みます。
- 食品廃棄物などについては、堆肥化やバイオガス化などの有効活用を検討します。
これらの改善策の検討にあたっては、専門のスタッフが貴社をきめ細かくサポートいたします。単に「どう削減すれば良いのか」という漠然とした問いではなく、具体的なデータに基づき、投資対効果や実現可能性を考慮した最適な削減ロードマップが明確になります。これにより、目標達成に向けた具体的なアクションプランを確実に実行できます。
2.3 報告書や削減計画のフォーマット支援
無料サービスでは、算定ツールだけでなく、以下の書類の作成支援も受けられる。
- CO2算定レポート(提出用PDF)
- 排出量集計データ
- 削減計画書フォーマット
- 環境配慮契約の提出資料
- 取引先から求められるCO2関連書類のドラフト
特に製造業は、大手企業から「スコープ3の開示」を求められるケースが増えており、算定レポートがあると大きな強みになる。
2.4 ESG評価・取引先対応・東京都環境配慮契約への活用可能性
算定結果、すなわち自社の事業活動に伴うGHG排出量(温室効果ガス排出量)の可視化は、単なるデータ収集にとどまらず、多岐にわたる重要な場面で戦略的な価値を発揮します。【多様なステークホルダーへの対応と競争力の強化】
排出量算定の結果は、企業の「環境への取り組み」を客観的かつ定量的に示す根拠となり、以下の分野で企業の競争力と評価を大きく向上させます。
- 金融機関の融資評価(サステナビリティ・リンク・ローンなど)
金融機関は、投融資の判断において企業の非財務情報、特に環境リスクと機会への対応を重視しています。排出量削減の目標設定とその実績を明確に示すことで、有利な融資条件の獲得(サステナビリティ・リンク・ローンなど)や、環境配慮型金融商品の対象となる可能性が高まります。 - ESG評価(投資家向けの情報開示)
機関投資家をはじめとする多くの投資家は、企業の長期的な安定性と成長性を測る指標としてESG(環境、社会、ガバナンス)評価を重視しています。CDPやSBTなどの国際的なイニシアチブへの対応、および算定結果に基づく情報開示は、企業の透明性を高め、ESGスコアの向上に直結し、結果として資金調達力の強化に貢献します。 - 大手企業のグリーン調達要件・サプライチェーン対応
サプライチェーン全体での排出量削減が世界的なトレンドとなる中、特に大手企業(取引先)は、自社のScope3排出量削減のため、取引先に対し環境データの提出や、特定の環境基準の遵守を求める「グリーン調達」を強化しています。排出量の可視化は、こうした取引要件を満たし、主要な取引先との関係を維持・強化するための必須条件となります。 - 都や自治体の入札における「環境配慮契約」
東京都をはじめとする地方自治体では、「環境配慮契約条例」に基づき、公共調達(入札)において、価格だけでなく、企業の環境への取り組みを客観的に評価する制度を導入しています。排出量の算定と削減計画の提示は、入札時の評価項目となり、競争優位性を高め、新たなビジネス機会の獲得に直接つながります。
【インナーブランディングと企業価値の向上】
算定結果は、社外だけでなく社内に対しても強力なメッセージとなります。
- 企業PR・採用強化(パーパス経営の実践)
環境問題への真摯な取り組みは、企業のブランドイメージを向上させます。特に環境意識の高い消費者や、社会貢献を重視する若年層の採用において、具体的な環境データに基づくPRは、企業の魅力を高め、優秀な人材の確保に貢献します。 - 社内啓発や社員教育(全社的なコスト削減と意識改革)
自社の排出量を具体的に把握することで、部門ごとの排出源が明らかになり、社員一人ひとりの具体的な削減行動(省エネ、節電など)を促す動機付けとなります。これは、環境意識の向上だけでなく、エネルギーコストの削減という経済的なメリットももたらします。
このように、排出量の可視化は、企業の法令遵守やリスク管理にとどまらず、市場における競争力向上、資金調達の円滑化、優秀な人材の確保、そして最終的な企業価値の向上に不可欠な戦略ツールとなっています。
なぜCO2算定が“脱炭素経営の第一歩”なのか
3.1 数値で自社の現状を把握しないと「削減計画」が立てられない
脱炭素経営は、「現状の排出量を把握すること」からしか始まらない、極めて論理的なプロセスです。この排出量の「見える化」こそが、脱炭素戦略の土台となります。
排出量を数値化しなければ、具体的に以下の判断が不可能です。
- 削減目標の明確化: 自社の総排出量が分からなければ、「どれくらい減らすべきか」という目標設定ができません。目標が曖昧であれば、全社的なコミットメントも弱まります。
- 削減余地の特定と優先順位付け: 排出源を「電力」「燃料」「サプライチェーン(Scope3)」などに分類し、それぞれの排出量が数値化されることで、「どこに最も削減余地があるのか」を正確に特定できます。例えば、製造工程の電力が排出量の大部分を占めるなら、省エネ設備投資が最優先になります。
- 施策の効果測定(PDCAサイクル): 施策を実施した後、その効果を測定するためには、算定されたベースラインとの比較が不可欠です。「エアコンを最新のものに変えたが、本当にCO2が減ったのか?」を客観的なデータで検証できなければ、次の改善サイクルに進めません。
この「最初の壁」である排出量算定を、無料のツールや簡易サービスが取り払ってくれることは、特にリソースの限られる中小企業にとって大きなメリットとなります。
3.2 金融機関・取引先からの開示要求への対応
企業の脱炭素への取り組みは、もはや「社会貢献」といったCSRの範疇に留まらず、「ビジネスの継続条件」へと変貌しています。特に中小企業においては、CO2算定が「取引条件」に近い扱いになりつつあります。
最近、具体的に以下のような要求が急増しており、対応できない企業は、ビジネス機会の損失や資金調達の難航に直面するリスクがあります。
- 取引先からのサプライチェーン排出量報告要請(Scope3対応): 大手企業は自社のGHG排出量だけでなく、サプライヤーである中小企業の排出量も集計する必要があります。そのため、取引先から「CO2排出量を報告してほしい」「GHGプロトコルに準拠したデータを開示してほしい」といった依頼が届くケースが爆発的に増えています。
- 金融機関の融資審査におけるES(環境・社会)評価: 金融機関は、投融資先のリスク評価に気候変動リスクを組み込むようになり、融資審査や格付けの際に、脱炭素への取り組みやCO2排出量の開示状況を重視します。取り組みが不十分な場合、金利の上乗せや融資の縮小につながる可能性があります。
- 商社・バイヤーからのグリーン調達基準への適合要求: 環境意識の高い消費者に製品を販売する商社や小売業者は、仕入れ基準にCO2排出量削減の要素を盛り込み始めています。CO2算定データは、この基準を満たすための「パスポート」の役割を果たします。
3.3 CO2削減はコスト削減にもつながる
脱炭素経営は、しばしばコスト負担と誤解されがちですが、実際には「コスト削減」に直結する戦略的な投資である側面が非常に強いです。排出量の算定と削減のプロセスは、企業内部の無駄を徹底的に洗い出す機会となるためです。
CO2削減の具体的なアクションは、以下のような形で直接的なコストメリットを生み出します。
- 光熱費の大幅削減: 省エネ性能の高いLED照明、高効率の空調設備、太陽光発電システムなどの導入は、使用する電力(=排出量の主要因)を減らすと同時に、月々の電気代・ガス代を劇的に削減します。削減効果は年間数十万円、規模によっては数百万円に達する場合もあります。
- 物流コストの効率化: 物流におけるCO2排出量の算定は、配送ルートの非効率性、積載率の低さなどを浮き彫りにします。これらを改善する(共同配送の実施、モーダルシフトの推進など)ことで、燃料費や人件費などの配送コストが減少します。
- 廃棄物処理コストの低減: 廃棄物の削減は、排出ガスだけでなく、その処理にかかるコスト(収集運搬費、処理委託費)の低減に直結します。
- オフィス経費の最適化: ペーパーレス化の推進は、印刷費、トナー代、紙代だけでなく、文書の保管スペースや管理の手間も削減します。
3.4 自治体・大手企業の「脱炭素パートナー企業」への参加条件に関連
持続可能なサプライチェーン構築への動きが加速する中で、CO2算定データは、新たなビジネス機会を獲得するための重要な参入条件となりつつあります。
多くの自治体や大手企業は、環境配慮を重視した以下のような制度やプログラムを積極的に展開しています。
- グリーン調達・環境配慮契約: 地方自治体や大企業が、製品やサービスを調達する際、環境負荷の低い企業や製品を優先的に選定する制度です。この選定基準には、CO2排出量のデータ開示や、特定の排出量削減目標の達成が含まれることが多くなっています。
- エコアクション21・ISO14001などの環境マネジメントシステム: これらの認証取得プロセスにおいて、排出量データの収集と管理は必須の要素です。認証取得は、企業の信頼性を高め、取引先へのアピール材料となります。
- SCP(サステナブル調達プログラム)や各種イニシアティブ: CDP(気候変動情報開示プロジェクト)への参加要請など、グローバルなサプライチェーンにおける環境イニシアティブへの対応が求められます。
これらの制度への申請や参加には、信頼性の高い排出量データが必要不可欠です。CO2算定を怠っていると、新規の取引や公募案件、補助金制度などの参加機会を逃すことになり、競争優位性を失うことに直結します。つまり、CO2算定は、現状維持のリスクヘッジであると同時に、未来への投資機会を獲得する手段なのです。
申込から活用までの流れ(ステップ形式)
ここでは、実際に申込をしてから利用を開始するまでの流れを、わかりやすく紹介する。
ステップ1:専用サイトから申込フォームを入力
企業基本情報、事業内容、データ保有状況などを入力する。
申込は5分ほどで完了する。
ステップ2:審査・登録完了後にサービス利用開始
先着枠に入っていれば、数日でメールが届き、算定ツールの利用が可能になる。
ステップ3:データ入力・CO2算定レポートの受領
電気・ガス・燃料・水道・廃棄物などのデータを入力すると、自動的に排出量が算定される。
ステップ4:専門スタッフによる改善提案・削減支援
算定結果を基に、東京都環境公社の専門スタッフが改善策を提案してくれる。
ステップ5:社内共有・外部PR・認定制度への展開
算定レポートは、社内・取引先・金融機関など幅広く活用できる。
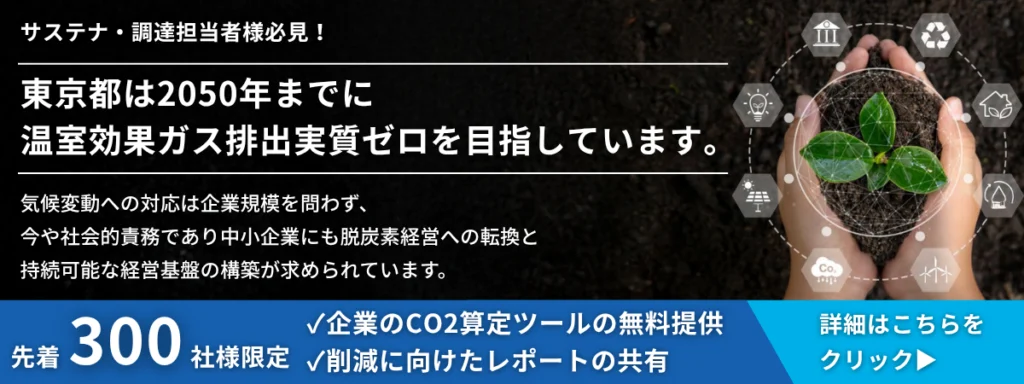
実際の導入事例・効果イメージ
5.1 都内製造業やサービス業での導入事例
無料CO2算定サービスを利用した都内企業では、業種を問わず多様な成果が報告されている。ここでは、実際に見えてきた改善ポイントと、企業が得た効果をより具体的に紹介する。
製造業:生産設備の稼働最適化で光熱費20%削減
都内の精密部品製造企業A社では、CO2算定によって「工場全体の電力使用の約40%が、夜間の待機電力によるもの」だと判明した。
これまで“生産性に影響しないから”と見過ごしていたが、算定した数値を見ると年間のCO2排出量に大きく影響していたことが一目瞭然となった。
そこで、機械の自動停止設定や空調管理の見直しを実施したところ、電力使用量が大幅に減少。結果として 年間の光熱費は20%削減。
経営者は「数字で可視化されることで、現場の理解と協力を得やすかった」と語り、改善活動がスムーズに進んだことを評価している。
サービス業:オフィス電力の最適化で年間10万円節約
都内でITサービス事業を行うB社の場合、CO2算定後に“電力ピーク時の消費量の高さ”が課題として浮き彫りになった。
PCやモニターの利用時間帯が集中し、またフロア全体の照明を一括管理していたため、稼働にムダが多かったのだ。
改善策として以下を実施:
- 照明をLEDへ交換
- 出社人数に合わせてゾーンごとに照明を制御
- スリープ機能の徹底
- 空調の温度設定見直し
これらの対策で 年間10万円以上の電気代削減 を実現。
CO2排出量も前年比で約15%削減され、社内の環境意識向上にもつながった。
物流業:配送ルートと積載効率改善で燃料費が減少
物流企業C社では、CO2算定の過程で「配送ルートの非効率」と「積載率の低さ」が主要な排出要因であることが判明した。
そこで、算定スタッフのアドバイスのもと、以下の取り組みを実施した。
- AIによる最適ルート計算ツールを導入
- 荷主と協力して積載率を改善
- アイドリング時間削減の教育を実施
- 中距離配送を共同輸送に切り替え
結果として、 燃料費は年間8%削減。CO2排出量も相応に減少した。
特に「非効率な運行をデータで説明できるようになったことで、荷主側にも協力を求めやすくなった」という声が大きい。
5.2 「取引先からの信頼アップ」「補助金採択の加点」「光熱費削減」などの実例効果
CO2算定によって得られるメリットは、光熱費削減や効率化だけではない。実際に導入した企業では、以下のような“ビジネス効果”が顕著に現れている。
取引先からの信頼向上
大手企業を中心に「スコープ1〜3の排出量提出」を求める調達基準が増加している。
算定レポートがあることで、以下のメリットが生まれる。
- 大手企業との取引継続・拡大につながった
- 調達審査で有利に働いた
- “環境対応企業”として競合との差別化が可能に
特に製造業や建設業では、「排出量を提出できなければ取引条件を見直す」という厳しいケースも出てきており、算定の必要性が一気に高まっている。
補助金採択で加点がつく
実際に、省エネ設備導入補助金・事業再構築補助金などの申請において、「温室効果ガス削減」の根拠としてCO2排出量を示せたことで 採択確率が上がった という声が複数ある。
CO2算定レポートは、
- 省エネ効果の説明
- 排出量削減の裏付け
- 投資妥当性の証明
の3点に活用できるため、金融機関にも説明しやすくなる。
経費削減につながる
CO2排出量の多い工程は “無駄なコストがかかっている工程” と一致することが多いため、
- 空調費
- 電気代
- 燃料費
- 水道代
- 廃棄物処理費用
などの削減が自然と進む。
あるオフィスでは、空調効率改善だけで年間15万円以上、廃棄物分別徹底で年間30万円近くの削減につながった事例もある。
採用力・PR効果が向上
企業の環境取り組みは、求職者の企業選びにも影響し始めている。
- 採用ページにCO2算定の取り組みを掲載
- SDGsの取り組みとしてアピール
- 地域企業としての信頼向上
結果として応募者が増えた企業もあり、「企業ブランド向上」という副次効果も見過ごせない。
5.3 小規模企業でも導入できた理由と成功のポイント
無料CO2算定サービスは、従業員数数名〜10名未満の小規模企業にも多く導入されている。導入できた理由と成功のポイントを整理すると、以下の要素が共通している。
1. データ提出が圧倒的に簡単
CO2算定と聞くと「大量のデータ入力」が必要と思われがちだが、実際には以下の基本情報だけで算定が可能である。
- 電気料金の明細
- ガス/燃料の使用量
- 水道使用量
- 廃棄物の量
- 自社車両の走行距離
- 仕入れの大まかな内訳
多くの小規模企業では、月に必要な作業は「電気明細の数値を入力するだけ」で完了している。
2. 操作画面が初心者向けに作られている
ツールの画面は専門用語を極力使わず、以下のような直感的なUIになっている。
- 入力箇所が少ない
- 自動計算に対応
- グラフで排出量を視覚化
- 年度比較がワンクリック
ITに不慣れな企業でも、1〜2時間で慣れてしまうケースがほとんどだ。
3. 専門家サポートが手厚い
東京都環境公社の専門コンサルタントが、
- データの集め方
- 入力方法
- 算定結果の見方
- 削減に向けた優先順位
- 補助金の使い方
などを個別にサポートしてくれる。
特に「削減提案」が具体的で、例えば
- 空調の運転スケジュール最適化
- 電灯のゾーニング
- 冷蔵・冷凍設備の設定調整
- 物流の効率化
- 廃棄物削減の方法
など、すぐ実行できる改善案を提示してもらえるため、経営者が“何をすれば良いのか”が明確になる。
4. 費用ゼロだから行動のハードルが低い
小規模企業にとって「まず一度使ってみる」というスタンスが取りやすい。
一般的なCO2算定ツールは年間数十万円かかるケースもあるため、それが“完全無料“というのは非常に大きいメリットだ。
5. 小規模企業でも“数値としての信用”が得られる
排出量の算定結果は取引先にも提示可能であり、「小さい会社でも環境意識が高い」というポジティブな印象を持たれる。
結果として、
- 新規取引時の信頼性向上
- 地域企業としてのブランド向上
- 金融機関とのコミュニケーション円滑化
といった長期的な企業価値向上につながっている。
よくある質問(FAQ)
Q1:無償提供の範囲は?途中で費用が発生することは?
A:算定ツール利用、レポート作成支援、専門アドバイスまで無料。基本的に追加費用は発生しません。
Q2:1社あたりどの程度の時間・人員が必要?
A:1〜2時間程度で初年度の算定が可能。1名の担当者で十分対応できます。
Q3:CO2算定ツールの操作は難しい?
A:電気・ガスの検針票などの数値を入力するだけなので非常に簡単です。
Q4:どんな業種でも申し込める?
A:はい。製造・飲食・サービス・IT・建設などすべての業種に対応。
Q5:他の補助金・支援制度との併用は可能?
A:はい。設備更新の補助金や東京都の環境支援制度と併用できます。
まとめ:都内中小企業は今こそ「脱炭素経営」を始める絶好のタイミング
脱炭素経営は、もはや“大企業だけの取り組み”ではない。
中小企業でも排出量の可視化を求められる場面は確実に増えており、環境対応が「取引条件」「金融評価」の基準になる時代へと移行している。
しかし東京都の無料CO2算定サービスを活用すれば、こうした脱炭素への第一歩を 初期コストゼロ で踏み出すことができる。
さらに以下の大きなメリットが得られる。
- 取引先からの評価向上
- 金融機関のESG評価に対応
- 補助金活用の加点効果
- 光熱費の削減
- 社内の意識改革
- 採用・PRに活かせる
特に「先着300社限定」という枠は競争率が高く、毎年すぐに埋まる人気制度である。
取り組みを後回しにすると、排出量の提出を求められた際に対応できず、ビジネスチャンスを逃す可能性もある。
脱炭素化の波が本格化する今こそ、中小企業が環境対応で一歩リードする絶好のタイミングである。
まずは無料のCO2算定サービスを活用し、自社の現状を可視化し、脱炭素経営の土台を築こう。