ニチコン株式会社NECST事業本部が挑む、カーボンニュートラル社会への道筋
INDEX
2011年の震災を機に立ち上がった、蓄電池市場のパイオニア
日本のエネルギー業界において、家庭用蓄電システム分野で圧倒的な存在感を示すニチコン株式会社。同社は2012年に業界に先駆けて家庭用蓄電システムを市場導入し、累計販売台数20万台以上という国内No.1の実績を誇ります。さらに、世界初のV2H(Vehicle to Home)システム「EVパワー・ステーション」の開発や、業界初の「トライブリッド蓄電システム」の商品化など、数々の革新的な製品を世に送り出してきました。今回は、同社NECST事業本部 副本部長の戸成秀道氏にお話を伺い、蓄電システム事業の歩みと今後の展望について詳しく聞きました。
東日本大震災が生んだイノベーション:蓄電池市場の創出
——まず、ニチコンの蓄電システム事業について、創業の経緯を教えてください。
戸成氏:我々の蓄電システム事業は、2011年の東日本大震災がきっかけとなって本格的にスタートしました。当時私は、震災直後のゴールデンウィークにトラックをチャーターして関東のショッピングモールや住宅展示場を回り、駐車場にお客様を集めて太陽電池と蓄電池を組み合わせたデモンストレーションを行ったんです。
その時の反応が非常に良く、「これは売れるんじゃないか」と実感しました。まだその時点では、リチウムイオン蓄電池を家庭に設置するなんて世の中に一台もなかった時代です。ただ、太陽光発電はそれなりに普及していましたので、太陽光発電と蓄電池を組み合わせれば、停電時、お日様がない夜でも家電製品が使えるというコンセプトでした。
翌年の2012年には、ニチコンと京セラの共同で蓄電システムを立ち上げました。当時、パナソニックや東芝など他社も同様の製品を出していましたが、飛び抜けて販売を伸ばし、シェアは5割以上、ピーク時には6〜7割になったと思います。
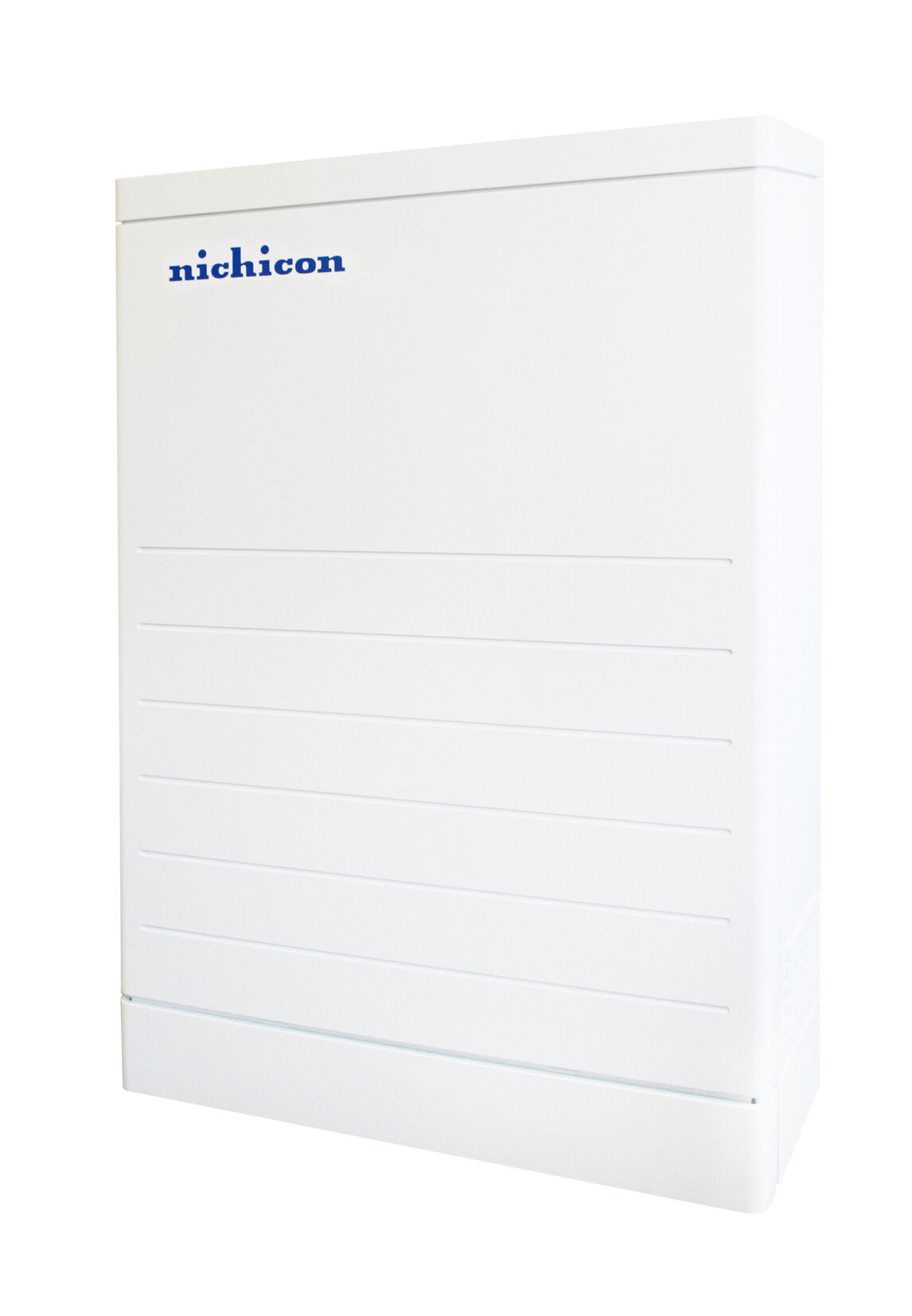
日本初の系統連系認証蓄電システム「ESS-U1シリーズ」
——まさに市場を創出されたということですね。
戸成氏:そうですね。それまで市場に無かった住宅用蓄電システムという市場を立ち上げ、太陽光発電と蓄電池を一緒に使うハイブリッド製品も先駆けて出しました。その先にはEVまで一緒に使っていこうというトライブリッドシステムまで発展させ、これがニチコンのアイデンティティになっています。
革新を支える「外様集団」:多様性がもたらす技術開発力
——技術的な進歩を支える組織の特徴について教えてください。
戸成氏:我々の組織は非常にユニークで、「外様集団」なんです。私もそうですが、各人がそれぞれ今までやってきた事業の経験があり、成功も失敗も積んでいる。そういった背景をしっかり持ちながら、スピード感を持って決断し、事業を推進しています。
スピードが必要なので、育てていられないと言ったらちょっと言い方が違うかもしれませんが、すぐに結果が必要だということです。結果的に中途採用が多くなっています。各業界での経験者が集まることで、業界に凝り固まった発想よりもアイデアの幅が広がっていると思います。
例えば、全く関係ない家電メーカーや音響メーカーの人もたくさんいます。私のように太陽光業界に関わったことのある人間もいますが、キャリアの中心だった経験者は実は少ないんです。
——多様な人材が集まることのメリットは何でしょうか?
戸成氏:それぞれ異なる経験をしてきた人材が集まることで、一つの業界の常識にとらわれない発想が生まれます。当たり前のことを考えていては他社に勝てっこないので、二歩も三歩も先を考える必要があります。その際、多様な視点を持つ人材がいることで、革新的なアイデアが生まれやすくなります。

NECST事業本部 戸成副本部長
「考働」の企業文化:スピードと品質の両立
——御社の企業カルチャーについて教えてください。
戸成氏:ニチコンの最大の特徴は「考働」という造語にあります。これは「考えて働く」という意味で、単なる行動ではなく、思考を伴った行動を重視しています。また、「Can Do !」というコーポレートステートメントも重要で、「すぐにできます」という実践力を大切にしています。
一方で、品質に対しては非常に厳格です。リチウムイオン蓄電池は最近、ハンディ扇風機などが発火したりするニュースも多く、こうした問題が社会的に認知されると、どんなに良い製品でも売れなくなってしまいます。そのため、安全性と品質には特に力を入れています。
——発想の自由さと品質の厳格さをどう両立されているのでしょうか?
戸成氏:変化点を見逃さないことが重要です。新しいことをやろうとすると、今までの技術を否定して新技術をドンと投入したくなりがちですが、それでは評価に何倍もの時間とコストがかかります。
信頼できるプラットフォームを一つ作り、その上で次の発展をさせていく。その際に必ず新しい技術やユーザビリティが求められる変化点が出てきます。その変化点が何に対して影響するのかをしっかりと見極めて、徹底的に潰していく。この変化点管理を徹底することで、進歩的な製品を作りながらも高い品質を維持しています。
実際に、ハード・ソフトともに住宅用蓄電システムについてはかなり固いプラットフォームができました。新商品開発の際も、このプラットフォームを活かして効率的に進められます。一番大変だったのはプラットフォーム化する製品を生み出す時でしたが、その反省を踏まえて、現在はより効率的な開発ができています。
―― 働かれている方々の特徴はいかがですか。
戸成氏:本当に皆さん真面目ですね。「わかりました、やってみます」と。真面目で純粋なので、絶対大崩れしないと思っています。
ただ、真面目に見えながらも、芯を持っている人が多いです。画一的な動きというよりは、一人一人が自由に発想しながらも、ベクトルは合わせてやってくれる。いろんな意見が出て、それも取り入れつつ、最終的にやろうとなったものはみんなでやり遂げてくれます。

東京開発センターの業務風景
業界シェア80%超:トライブリッドシステムの革新性
——トライブリッドシステムについて詳しく教えてください。
戸成氏:トライブリッドは「太陽光発電」「蓄電池」「EV電池」の3つのエネルギーをコントロールできる業界初のシステムです。2018年に初代、2022年に二代目、そして2025年秋には三代目を発売予定です。
このシステムの特徴は、3つのエネルギーをすべて直流(DC)で高効率にコントロールできることです。昼間は太陽光発電を蓄電池とEV電池に充電し、夕方から朝まで貯めておいた電力を家やクルマに使える「家産家消」の暮らしが実現できます。
——市場での反響はいかがですか?
戸成氏:トライブリッドは非常に好評をいただいています。EV市場の拡大に伴い、EVに充電した電気を家庭で使える、V2Hの需要も増加しております。

新商品トライブリッドシステム「ESS-T5シリーズ」
2030年への戦略:新規事業と既存事業の発展
——今後の事業展開について教えてください。
戸成氏:大きく二つの軸で考えています。一つは既存ビジネスの発展(Evolution)、もう一つは新規ビジネス(New)です。
既存ビジネスでは、台数は増えますが単価が下がってくるため、売上・利益の大幅な増加は見込めません。そこで重要になるのが新規ビジネスです。
2025年から2030年にかけて、大きく3つの軸で成長を目指します。まず、既存の蓄電システム事業のさらなる拡大。政府の蓄電池普及目標や太陽光発電義務化の流れを追い風に、市場の成長を取り込んでいきます。
次に、VPP(バーチャルパワープラント)などのエネルギー事業への展開。蓄電池を単なる製品としてではなく、エネルギーリソースとして活用するデータビジネスを拡大します。
最後に、EVシフトへの対応。V2Hシステムの拡大、急速充電器の全方位展開、商用車EV化への対応など、モビリティの電動化に合わせたソリューションを提供していきます。
具体的には、ペロブスカイト太陽電池を使った新しいシステム、次世代自動車向けの技術開発などです。ただし、飛び石は打ちません。既存事業との関連性を保ちながら、段階的に発展させていきます。
——2032年が一つのターニングポイントになるとお聞きしましたが。戸成氏:2032年は産業用太陽光発電が初めて卒FITを迎える年です。この時点で、原価ゼロの太陽光発電を蓄電池でどう使い倒していくかが大きなビジネスモデルになると考えています。住宅用だけでなく、産業用・公共用での蓄電システムも本格展開し、社会インフラとしての蓄電技術を確立したいと考えています。
カーボンニュートラルへの貢献:蓄電システムの社会的意義
——環境・サステナビリティへの取り組みについてお聞かせください。
戸成氏:「2050年カーボンニュートラル」に向けて、再エネ比率50~60%という政府目標があり、蓄電池の活用と電動車の普及拡大が重要な柱となっています。
国は2030年までに新築戸建ての6割に太陽光発電導入を目標とし、東京都と川崎市は2025年4月から住宅での太陽光発電義務化を開始しました。また、経産省は蓄電池普及台数を2030年に35万台の目標を掲げています。現在、蓄電池を設置している家庭は約100万世帯ですが、日本の戸建て住宅は2500万世帯以上あります。蓄電池は太陽光発電と違って屋根の形状に関係なく設置できるため、将来的には昔の三種の神器のように、当たり前に家にあるものにしたいと考えています。
求める人材:経験を活かせる多様な人材
——どのような方と一緒に働きたいとお考えでしょうか?
戸成氏:年齢や業界経験よりも、やる気と体力があることが重要です。私自身60歳でこの会社に入りましたが、シニア扱いはほとんど感じません。一年契約でもやる気があれば普通に更新されますし、それなりに結果を残せば65歳までは現役で働け、それ以上も70歳くらいまでは可能です。
特に来てほしいのは、太陽光発電や蓄電池をやっていた方です。会社が事業をやめてしまったという理由で転職を考えている方もいらっしゃると思いますので、そういった経験者は大歓迎です。
——御社で働く魅力は何でしょうか?
戸成氏:価値ある、将来的に人々の役に立つビジネスに携われることです。私は前職では「電池バカ」と言われるほど電池が好きで、太陽光発電には25年、蓄電池にも10年以上携わってきました。
この技術を使って、家で作った電気で車を走らせるような「当たり前」の時代を作りたい。私が引退するまでには、そういった時代にしたいと思っています。太陽光発電も最初は夢物語でしたが、今では当たり前になりました。蓄電池も同じような時代の変化を作っていきたいです。

ニチコン東京開発センター全景
読者へのメッセージ:蓄電池の「当たり前」を一緒に
——最後に、この記事を読まれる方へメッセージをお願いします。
戸成氏:蓄電池業界は、まだまだニチコンがどう、他社がどう、というレベルではありません。業界として蓄電池をもっと普及させていく段階です。
現在蓄電池を設置している世帯は100万世帯程度で、まだまだ市場拡大の余地があります。太陽光発電も最初は3kWシステムで1,000万円だったものが、今は100万円になりました。蓄電池も同じような変化が起こると思います。
業界として全体を発展させながら、ニチコンのポジションもしっかりと築いていきたい。一緒になって蓄電池を三種の神器のように当たり前に家にあるものにし、家で作った電気で車を走らせる時代を作りませんか。今までいろんな仕事でいろんな経験をされてきた方、別に太陽光発電や蓄電池の経験者でなくても、これまでの経験を活かせると思われる方は、ぜひ一緒にこの「当たり前」を作っていきましょう。
会社概要
会社名: ニチコン株式会社
設立: 1950年8月1日
代表者:代表取締役会長 武田一平
事業内容: アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、小形リチウムイオン二次電池、 正特性サーミスタ“ポジアール®”、家庭用蓄電システム、V2Hシステム、EV・PHV用急速充電器、公共・産業用蓄電システム、 スイッチング電源、機能モジュール、医療用加速器電源、学術研究用加速器電源、瞬低・停電補償装置など
従業員数: 5,242名(2025年3月31日現在 連結)
主な実績:
- 家庭用蓄電システム累計販売台数国内No.1(25年1月時点)
- V2H市場シェア約90%
- 急速充電器設置口数シェア国内No.1(23年度)
- 業界初トライブリッド蓄電システム開発
Webサイト: https://www.nichicon.co.jp/
【GX・ESG特化型転職サービス ASUENE CAREER利用企業インタビュー】
この記事は2025年に実施したインタビューをもとに作成しました。












































































































