4月22日、世界各地で「アースデー(Earth Day)」が迎えられています。気候変動(Climate Change)の影響がますます深刻化する中、国境を越えて環境への関心と行動が問われる日です。
世界の大多数、約89%の人々が、気候変動対策における政治的リーダーシップの強化を望んでいる――。気候変動報道の国際イニシアチブ「Covering Climate Now(CCNow)」が主導する「89%プロジェクト」は、そうした生活者の声を報道の中で可視化する取り組みです。アスエネメディアもこの趣旨に賛同し、プロジェクトの一環として、国内で進行中の多様な取り組み事例を紹介します。
気候変動の影響は、もはや抽象的な将来の問題ではなく、今を生きる私たちの行動や制度に直結する課題です。教育、スポーツ、小売、行政、そしてエンターテインメントなど、各分野での取り組みを見つめ直すことで、89%の声がどこに存在し、どのように形になりつつあるのかを伝えていきます。
INDEX
不確実な時代に、確かな行動を:89%プロジェクトの広がりと共に
気候変動と脱炭素を巡る国際的な動きは、各国政府の政策判断によって大きく影響を受けています。とりわけ、2025年に再登場した第2次トランプ政権は、就任直後にアメリカを再びパリ協定から離脱させ、脱炭素関連の科学研究や再生可能エネルギーに対する連邦補助金の削減を進めるなど、気候変動対策に関する国家支援の縮小を進めています。これにより、国際協調による気候アクションの足並みには再び不確実性が生じています。
こうした中で、市民社会、地方自治体、企業、教育現場など、国の政策を越えて地道な取り組みを重ねる動きが世界各地で注目されています。「89%プロジェクト」は、こうした草の根の気候アクションに光をあてるグローバルな報道キャンペーンとして、欧米、アジア、アフリカを含む世界中の参加メディアに広がりつつあり、2025年4月現在、600近くの報道機関が参加しています。
この記事では、その一端として、日本国内で進行している5つの気候変動対策の実践例を紹介します。多様な分野における実践は、それぞれが「89%の声」に対する具体的な応答と言えるものです。
音楽イベント:「ap bank fes ’25 at TOKYO DOME」100%カーボンニュートラルな音楽フェス

2025年2月、東京ドームで開催された大型音楽イベント「ap bank fes ’25 at TOKYO DOME」では、100%カーボンニュートラルを目指す試みが行われました。APバンクは、イベント全体のCO2排出量の事前・事後算定と、東京ドームの再生可能エネルギーの利用やカーボンクレジットによるオフセットを通じて、イベントのカーボンニュートラル化に挑戦しました。アスエネはイベント全体のCO2排出量算定とカーボン・オフセットを担いました。
この取り組みでは、参加者の移動手段や消費行動に焦点を当て、環境配慮の「気づき」から「行動」への転換を促しました。音楽ファンをはじめとする幅広い層に、イベント会場やステージ上で地球温暖化問題を啓発し、エンタメと気候変動の接点を自然に伝える場となりました。脱炭素の必要性を体感的に捉えることが、次の行動を生む第一歩となるかもしれません。
【参照】「ap bank fes ’25 at TOKYO DOME」
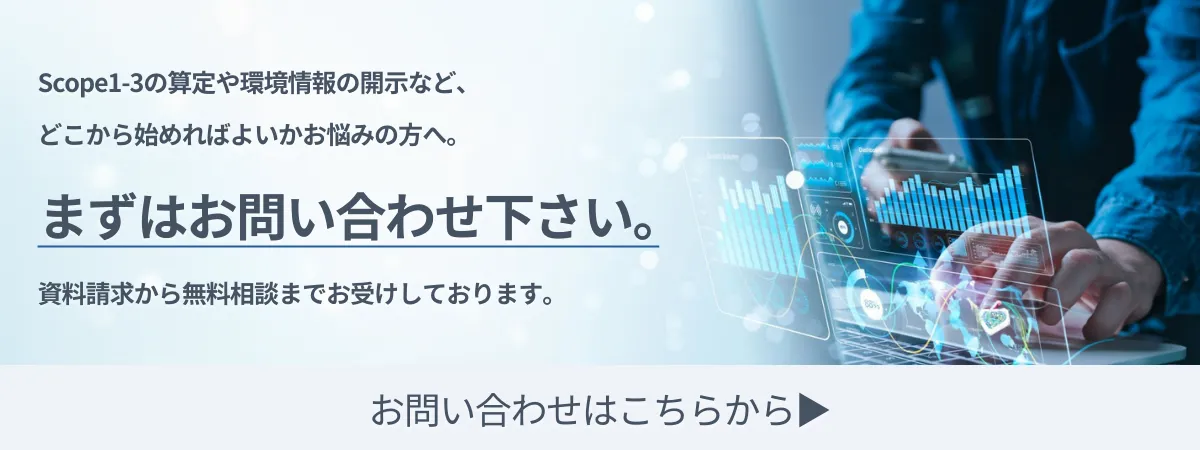
スポーツ観戦:「静岡ブルーレヴズ」国内ラグビー初のカーボン・オフセット付きチケット
ジャパンラグビー リーグワン所属のプロラグビーチーム「静岡ブルーレヴズ」は、国内で初めて「カーボン・オフセット付きチケット」を導入しました。事業運営や試合開催に伴うCO2排出(特に観客の移動)を算定し、地域の製紙会社が創出したJ-クレジットを用いて、地域循環型のカーボン・オフセットを実施しました。
スポーツの試合開催や観戦においても、気候変動の影響を大きく受けています。自治体や地域産業とも連携しながら、スポーツが持つ影響力を活かし、脱炭素化への行動変容を促す設計が広がりつつあります。
【参照】静岡ブルーレヴズ「カーボン・オフセット付きチケット販売」
日常の買い物:「減CO2プロジェクト」買い物から始める脱炭素

日本総研が主催するチャレンジ・カーボンニュートラル・コンソーシアム(CCNC)の「みんなで減CO2(ゲンコツ)プロジェクト」では、スギ薬局や食品スーパー万代の店舗に並ぶ商品のカーボンフットプリント(CFP)を可視化し、生活者が買い物を通じてカーボンニュートラルを「触れる・学ぶ・取り組む」仕掛けを提供しました。また、大阪府内の小学校1,029校に学習キット「減CO2ミッション」を配布するなど、学習の啓発活動も実施しました。
生活者が身近な消費活動を通じて気候変動対策に参加するきっかけづくりを支援しました。環境行動への参加を「選択」ではなく「体験」として提供することが、継続的な変化につながる可能性があります。
次世代教育:「ドルトン東京学園」生徒が学校のCO2排出量を算出する実践型プログラム
中高一貫校であるドルトン東京学園では、2025年5月より、中高生の生徒たちが、実際に企業で活用されているCO2排出量見える化サービス「ASUENE」を使って自校のCO2排出量を可視化し、削減提案までを行う実践型授業が始まります。Scope1-3を含む排出量の算出、課題分析、改善アイデアの立案とプレゼンテーションまで、6回にわたって実施されるカリキュラムです。
生徒が環境と経済の両面から社会課題に触れる機会を提供しています。学校という小さな単位であっても、生徒が主役となって学び、データに基づくアクションを自らの手で起こすことは、未来へのアクションにつながります。
【参照】ドルトン東京学園で「気候変動と社会課題を考える実践型プログラム」
自治体:「神奈川県」県内事業者の脱炭素を見える化で支援

神奈川県とCO2排出量見える化サービスを提供する4企業は、2025年4月に県内中小企業のCO2排出量の見える化・削減支援を目的とした連携協定を締結しました。県内中小企業が「事業活動温暖化対策計画書制度」に対応するうえでの、排出量算定・提出業務の簡素化に寄与することが狙いです。
自治体独自の制度とCO2排出量見える化クラウドの接続により、行政施策の実効性を高めると同時に、企業がより自律的に脱炭素へ取り組めるような基盤整備が進んでいます。
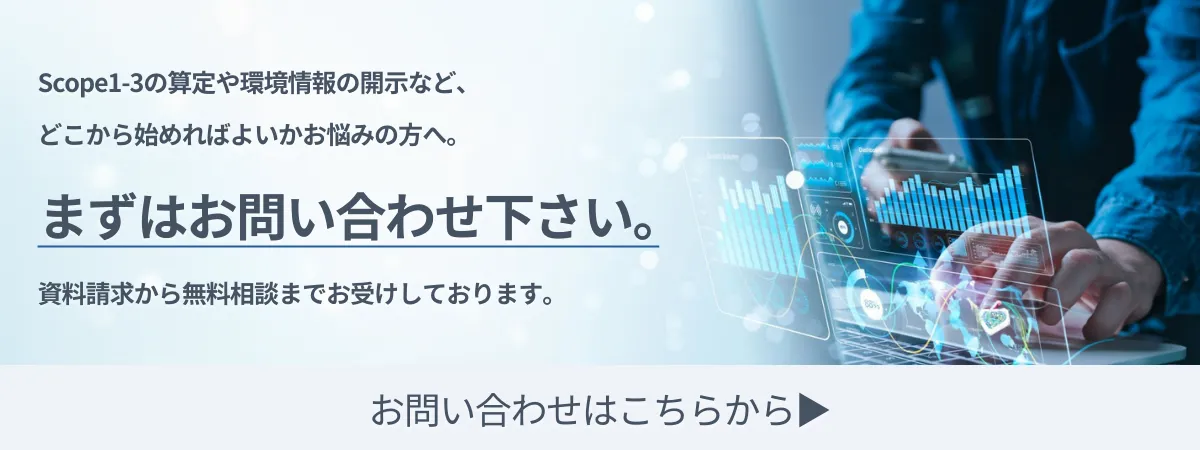
89%の声が示す可能性
最新の国際世論調査では、世界人口の約89%が、自国政府に対して気候変動対策の強化を求めていると報告されています。この数字は、単なる統計ではなく、行動の源泉でもあります。
本記事で紹介したような取り組みは、各々の分野でそれぞれの手段を通じて、同じ課題に向き合おうとする試みです。エンタメの場でも、学校の教室でも、スーパーの棚でも、すでに気候変動へのアクションは始まっています。
政策決定者がこの89%の声をどう受け止め、どのような意思決定につなげるのか。私たち一人ひとりの関心と行動が、その流れを加速させる鍵となるかもしれません。
「気候危機は、遠い世界の話ではなく、私たち一人ひとりの生き方と直結しています」
この想いを胸に、アスエネメディアはこれからも“行動する気候メディア”として、「89%プロジェクト」に真摯に向き合い、共に歩んでいきます。
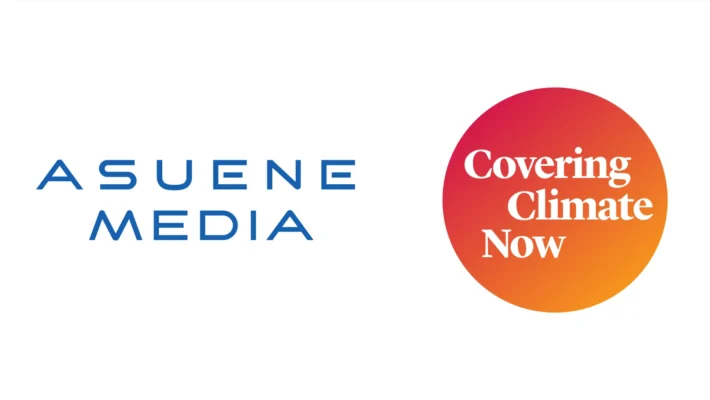
本記事は、国際的な報道連携「Covering Climate Now」による「89%プロジェクト」の一環として執筆・公開されました。














































































































