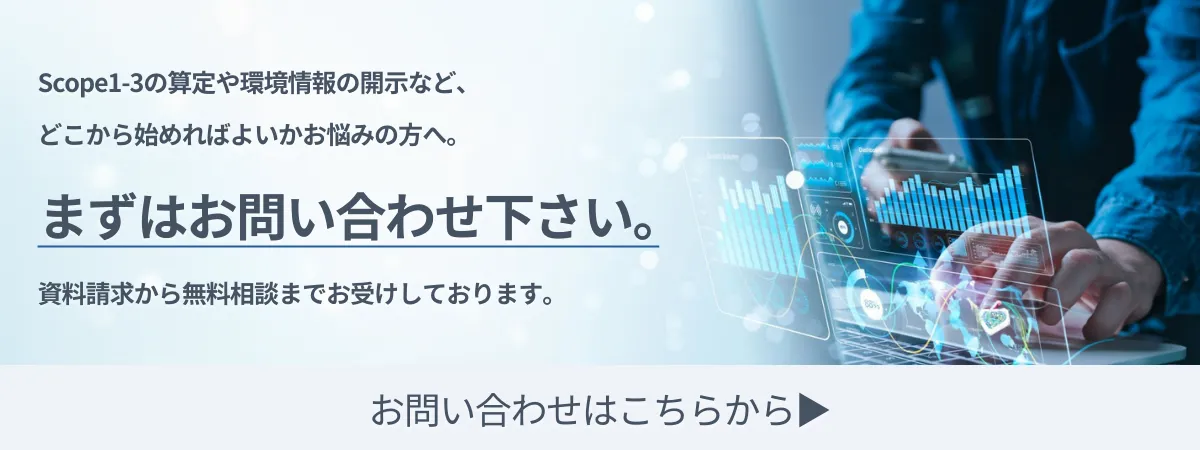紛争鉱物という言葉が、企業のサプライチェーンにおける倫理的な課題として、ますますその重要性を増しています。特に、武装勢力の資金源となり、紛争地域での人権侵害を引き起こす可能性のある鉱物の取引は、国際社会から強い非難を浴びています 。企業は、単に法令を遵守するだけでなく、サプライチェーン全体における透明性を高め、社会的責任を果たすことが求められています 。しかし、その道のりは決して平坦ではありません。複雑なサプライチェーンを管理し、多様な規制に対応しながら、実効性のある調査を実施することは、サプライチェーン担当者にとって大きな負担となっています 。本稿では、紛争鉱物問題の核心に迫り、サプライチェーン担当者が直面する具体的な課題と、その解決に向けた対策を詳細に解説します。
INDEX
紛争鉱物とは?定義、種類、そしてサプライチェーンへの影響
紛争鉱物の定義と「3TG」について
紛争鉱物とは、紛争地域で採掘され、その収益が武装勢力の資金源となっている鉱物資源を指します。特に問題視されているのは、スズ(錫)、タンタル、タングステン、金(Gold)の4種類の鉱物で、これらの頭文字をとって「3TG」と呼ばれています。これらの鉱物は、それぞれカシテライト(スズの原料)、コロンバイト-タンタライト(タンタルの原料)、ウォルフラマイト(タングステンの原料)という鉱石から抽出されます。米国のドッド・フランク法では、主にコンゴ民主共和国(DRC)およびその周辺国で産出される3TGが規制対象となっていますが、EUの紛争鉱物規則やOECDのデュー・ディリジェンス・ガイダンスは、より広範な地域や鉱物を対象とする可能性があります 。
紛争鉱物が問題視される背景:紛争の資金源と人権侵害
紛争鉱物取引が問題視される最大の理由は、その収益が紛争地域の武装勢力にとって重要な資金源となり、地域紛争を激化させ、長期化させる要因となるからです 。国連の専門家グループによると、2024年4月下旬にM23がルバヤを掌握したことで、同地域で採掘されるタンタルの原料であるコルタンの生産と取引から、武装勢力が毎月約80万米ドルの収益を得ていると推定されています 。また、紛争鉱物の採掘現場では、強制労働や児童労働といった深刻な人権侵害が横行しており、拉致された住民が過酷な環境下で働かされたり、10歳にも満たない子供たちが採掘作業に従事させられたりするケースも少なくありません 。さらに、鉱物資源の採掘は、森林破壊や水質汚染といった深刻な環境破壊を引き起こすこともあります 。紛争地域では、採掘による収益が地域住民に還元されず、一部の権力者や武装勢力に独占されるため、インフラ整備や教育への投資が滞り、貧困問題の根源となっています 。紛争地域における女性への性暴力も、紛争鉱物と深く関連しており、武装勢力が地域を支配するための手段として用いられています 。
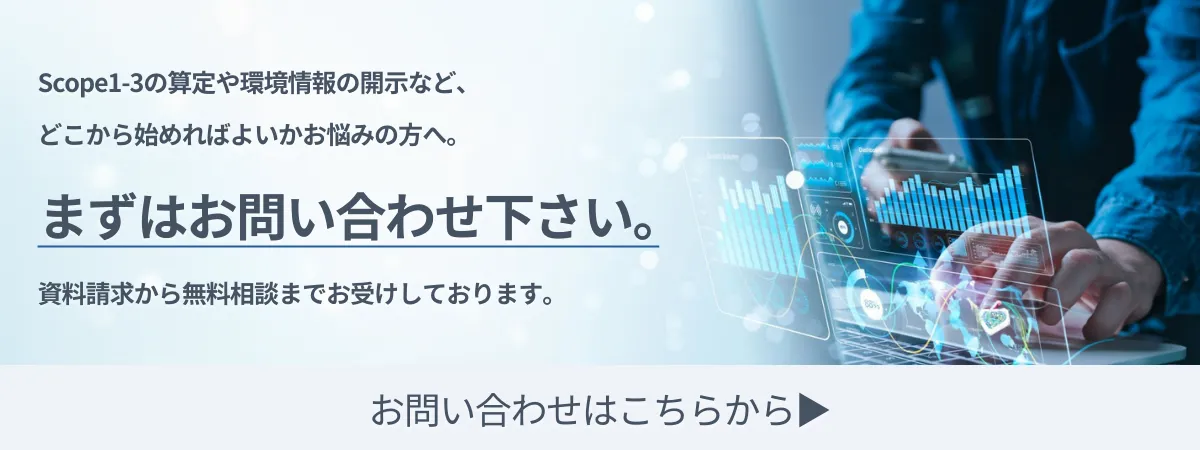
なぜ紛争鉱物調査が必要なのか?法的・倫理的観点からの考察
米国ドッド・フランク法(1502条)の概要と影響
米国では、2010年に成立したドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法(以下、ドッド・フランク法)の1502条において、米国に上場する企業に対し、コンゴ民主共和国(DRC)およびその周辺国を原産とする紛争鉱物の使用状況を開示することが義務付けられました 。この法律は、紛争鉱物の取引が紛争地域の武装勢力の資金源となっているという懸念に基づいて制定され、サプライチェーンの透明性を高めることで、紛争への資金提供を断つことを目的としています 。対象となる企業は、製品の機能または製造に不可欠な3TGがDRC地域を原産とするかどうかを調査し、その結果を年次報告書として米証券取引委員会(SEC)に提出する必要があります 。この調査は、合理的な原産国調査(RCOI)と呼ばれるもので、誠意をもって実施され、鉱物の原産国を特定するために合理的に設計されたものでなければなりません 。もし鉱物がDRC地域を原産とする可能性があると判断された場合、企業はさらに、その鉱物が武装勢力の資金源となっていないことを確認するためのデュー・ディリジェンスを実施し、その結果を紛争鉱物報告書としてSECに提出し、自社のウェブサイトで公開する必要があります 。ドッド・フランク法は、紛争鉱物の使用自体を禁止するものではありませんが、情報開示を義務付けることで、企業の責任ある調達を促すことを意図しています 。しかし、この法律は、報告義務の負担が大きいことや、紛争地域における実質的な改善効果に対する疑問など、多くの課題や批判も存在します 。
EU紛争鉱物規則の概要と対象範囲
スイスでは、2023年1月に、紛争地域を原産とする鉱物および金属と児童労働に関するデューデリジェンスおよび透明性に関する条例(以下、スイス条例)が施行されました 。この条例は、スイスに拠点を置く企業に対し、紛争地域または高リスク地域を原産とするスズ、タンタル、タングステン、金(3TG)を含む鉱物または金属を一定量以上輸入または加工する場合、あるいは児童労働によって製造または提供された疑いのある製品またはサービスを提供する場合に、デューデリジェンスおよび報告義務を課すものです 。スイス条例は、紛争鉱物だけでなく児童労働も対象としている点が特徴です 。企業は、サプライチェーンにおける児童労働のリスクを特定し、評価するための措置を講じ、児童労働が確認された場合には、そのリスクを排除または軽減するための適切な対策を講じる必要があります 。また、紛争鉱物に関しても、OECDのデュー・ディリジェンス・ガイダンスまたはEUの紛争鉱物規則に準拠したデューデリジェンスを実施する必要があります 。対象となる企業は、デューデリジェンスの実施状況に関する年次報告書を作成し、公表する義務があります 。報告義務の不履行または不適切な報告に対しては、罰金が科される可能性があります 。ただし、中小企業(SME)や児童労働のリスクが低いと評価された企業は、一部の義務が免除される場合があります 。
日本における業界の取り組み(JEITAなど)
日本には、紛争鉱物に関する連邦法は存在しませんが、電子情報技術産業協会(JEITA)をはじめとする業界団体が、自主的に責任ある鉱物調達に取り組んでいます 。JEITAは、IT・エレクトロニクス産業のサプライチェーン全体における企業の社会的責任(CSR)の推進を目的として、責任ある鉱物調達ワーキンググループを設置し、活動を行っています 。具体的には、OECDのガイダンスやRMI(Responsible Minerals Initiative)のイニシアチブと連携し、紛争鉱物に関する調査票(CMRT:Conflict Minerals Reporting Template)を活用したサプライチェーン調査を実施しています 。JEITAは、会員企業が責任ある鉱物調達に関する法規制や業界の動向を把握し、効率的かつ正確な調査を実施できるよう、ガイドラインの策定、説明会の開催、調査ツールの開発・改善などの支援活動を行っています 。また、RMIと協力し、CMRTをはじめとする基準の策定にも貢献しています 。多くの日本企業も、自社のウェブサイトで紛争鉱物に関する方針を表明し、サプライヤーに対し、紛争地域を原産とする鉱物の不使用や、責任ある調達を求めています 。
企業の社会的責任とサプライチェーンの透明性
法的義務に加えて、企業が紛争鉱物調査を実施する倫理的な理由は、企業の社会的責任(CSR)を果たすという観点からも重要です 。紛争鉱物の取引は、紛争地域の紛争を助長し、人権侵害を引き起こす可能性があり、企業はこれらの問題に加担しないよう努める必要があります 。サプライチェーンの透明性を高め、製品に使用されている鉱物の原産地を特定することは、企業の倫理的な責任を果たす上で不可欠です 。消費者や投資家も、企業が倫理的な配慮を行っているかどうかを重視する傾向が強まっており、責任ある鉱物調達は、企業の評判やブランド価値にも影響を与える可能性があります 。
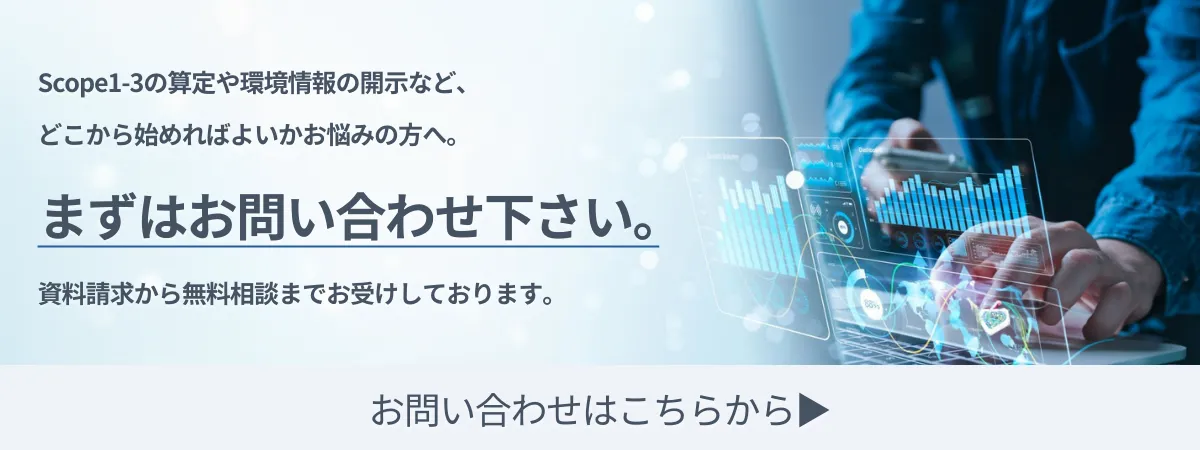
紛争鉱物調査の進め方:サプライチェーン担当者のためのステップバイステップガイド
紛争鉱物調査の必要性と目的
紛争鉱物調査は、法的義務を果たすためだけでなく、倫理的な観点からも非常に重要です 。その主な目的は、自社の製品に使用されている3TGの原産地を特定し、それらが紛争地域において武装勢力の資金源となっていないことを確認することです 。これにより、企業は紛争への間接的な加担を回避し、責任ある調達活動を推進することができます 。
具体的な調査方法と情報収集のポイント
紛争鉱物調査の最初のステップとして、合理的な原産国調査(RCOI)を実施します 。これは、製品に含まれる3TGが、規制対象地域(主にDRCおよびその周辺国)を原産とする可能性があるかどうかを判断するための調査です 。この調査では、サプライチェーンのあらゆる階層のサプライヤーと連携し、鉱物の原産地に関する情報を収集することが重要です 。情報収集の際には、RMI(Responsible Minerals Initiative)が開発した標準化されたツールであるCMRT(Conflict Minerals Reporting Template)を活用することが一般的です 。
紛争鉱物調査のプロセスと注意点
紛争鉱物調査の一般的なプロセスは、計画、データ収集、データ分析、報告という段階で構成されます 。調査の際には、サプライヤーから提供された情報の妥当性を検証し、データの正確性を確保することが重要です 。また、調査のプロセスと結果に関する記録を適切に保管し、監査に備える必要があります 。
業界標準ツール:CMRT(Conflict Minerals Reporting Template)の活用
CMRTは、紛争鉱物の原産国およびサプライチェーンで使用されている製錬業者に関する情報をサプライチェーン全体で伝達するために開発された、業界標準の報告用テンプレートです 。CMRTは、宣言シート、製錬業者リスト、製品リストなど、複数のシートで構成されており、サプライヤーはこれらのシートに必要事項を記入することで、紛争鉱物に関する情報を提供します 。特に、製錬業者リストは、サプライチェーンにおける製錬業者を特定し、その製錬業者が責任ある鉱物調達のための認証プログラム(RMAPなど)に参加しているかどうかを確認する上で重要な役割を果たします 。RMIは、CMRTの使用に関する様々なリソースやガイダンスを提供しており、企業はこれらを活用することで、より効果的な調査を実施することができます 。
世界各国・地域の紛争鉱物対応:規制の現状と企業の取り組み
アメリカの規制:ドッド・フランク法の詳細とエンフォースメント
ドッド・フランク法1502条は、米国に上場する企業に対し、製品の機能または製造に「必要」な紛争鉱物(3TG)がDRC地域を原産とするかどうかを開示することを義務付けています 。ここでいう「必要」とは、製品の機能性または生産に不可欠であることを意味し、使用量の多寡は関係ありません 。この法律は、製造委託契約をしている場合の委託元会社(小売業を含む)も対象となります 。SECは、この法律の執行を担当しており、企業が虚偽または誤解を招くような報告を行った場合には、証券取引法に基づく責任を問われる可能性があります 。ドッド・フランク法の施行後、多くの企業がサプライチェーンにおけるデュー・ディリジェンスを強化し、DRC地域を原産としない鉱物の調達を推進する傾向が見られます 。
EUの規制:紛争鉱物規則の内容とCAHRA(紛争地域・高リスク地域)
EUの紛争鉱物規則は、EU域内に3TGを輸入する企業に、より広範な地理的範囲(CAHRAs)を対象としたデュー・ディリジェンスを義務付けています 。輸入業者は、OECDの5段階のデュー・ディリジェンス・フレームワークに従い、経営管理システムの確立、リスク評価、リスク対応戦略の策定、第三者監査の実施、年次報告を行う必要があります 。CAHRAsの特定は、EU規則において重要な要素であり、欧州委員会は、紛争の影響を受けている地域や人権侵害のリスクが高い地域を示す、非網羅的なリストを定期的に更新しています 。EU規則の執行は、各加盟国の管轄当局が行い、不遵守の企業に対しては、是正措置や罰金などの措置が取られる可能性があります 。
スイスの規制:紛争鉱物と児童労働に関するデューデリジェンス義務
スイスの条例は、紛争鉱物(3TG)だけでなく、児童労働についてもデューデリジェンスを義務付けている点が特徴です 。スイスに拠点を置く企業は、一定量以上の3TGを輸入または加工する場合、あるいは児童労働によって製造または提供された疑いのある製品またはサービスを提供する場合に、サプライチェーンにおけるリスクを特定、評価、軽減するための措置を講じ、年次報告書を作成・公表する必要があります 。この条例では、ILOの最悪の形態の児童労働に関する条約に該当する18歳未満の者の労働などが「児童労働」と定義されています 。スイス条例の不遵守に対しては、罰金が科される可能性があります 。
日本の取り組み:業界団体(JEITA)の自主的な活動
日本には、紛争鉱物に関する直接的な法律はありませんが、JEITAなどの業界団体が中心となり、責任ある鉱物調達を推進しています 。JEITAは、会員企業に対し、CMRTを活用したサプライチェーン調査の実施や、責任ある鉱物調達のためのガイドラインの遵守を推奨しています 。また、RMIをはじめとする国際的なイニシアチブとの連携を通じて、グローバルなサプライチェーンにおける責任ある鉱物調達の実現を目指しています 。多くの日本企業も、自社のサプライチェーンにおける紛争鉱物の使用状況を把握し、責任ある調達を推進するための独自の取り組みを実施しています 。
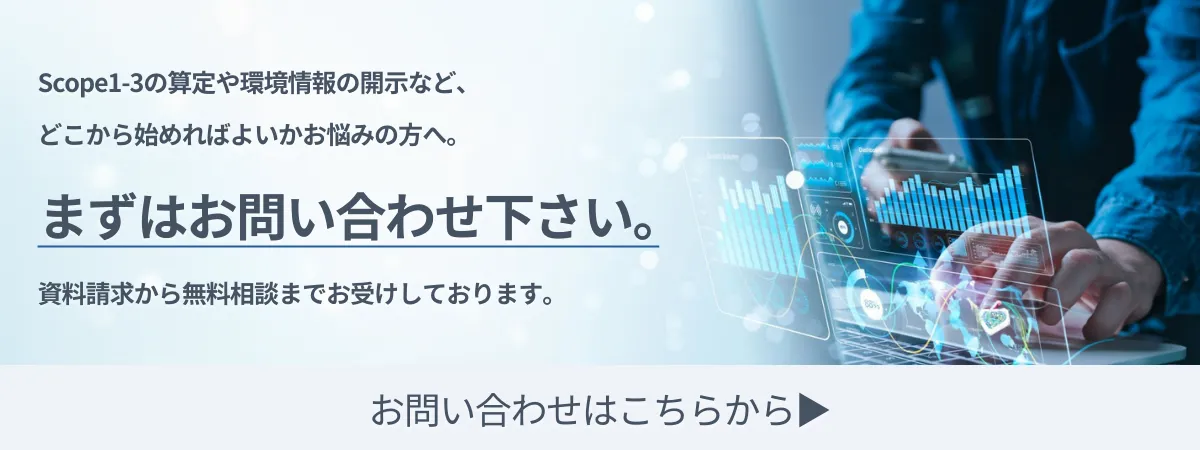
紛争鉱物調査における課題と解決策:担当者が直面する困難と対応
サプライチェーンの複雑さとトレーサビリティの確保
紛争鉱物調査における最大の課題の一つは、グローバルに展開された複雑なサプライチェーンにおいて、鉱物のトレーサビリティを確保することです 。多くの製品は、複数の部品メーカーやサプライヤーを経由して製造されており、最終製品メーカーが川上の鉱山や製錬業者まで遡って情報を追跡することは容易ではありません 。この課題に対して、ブロックチェーン技術を活用して鉱物の原産地から最終製品までの流れを記録し、透明性を高める取り組みも始まっています 。
サプライヤーとの連携と情報開示の促進
サプライヤーからの正確かつタイムリーな情報開示を得ることも、紛争鉱物調査における大きな課題です 。特に、サプライチェーンの下位に位置するサプライヤーからの情報収集は困難な場合が多く、回答率の低さや不正確な情報が報告されることもあります 。この課題を克服するためには、サプライヤーに対して紛争鉱物問題の重要性や調査の目的を丁寧に説明し、協力を求めることが重要です 。また、サプライヤー向けのトレーニングや情報提供、サプライヤー契約への紛争鉱物に関する条項の組み込みなども有効な対策となります 。
法規制の変更と最新情報のキャッチアップ
紛争鉱物に関する法規制やガイダンスは、国際的、地域的、国内的に頻繁に変更されるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります 。特に、EU規則やスイス条例のように、新たな規制が導入されたり、既存の規制が強化されたりする動きには注意が必要です 。規制当局のウェブサイトや業界団体からの情報発信、専門家によるコンサルテーションなどを活用し、常に最新の情報を収集し、自社の対応をアップデートしていくことが求められます 。
デューデリジェンスの実施におけるコストとリソース
包括的な紛争鉱物デューデリジェンス・プログラムの実施には、相当なコストとリソースが必要となる場合があります 。サプライヤーとの連携、データ収集、分析、報告書の作成、そして必要に応じた監査の実施など、多くのプロセスに時間と労力がかかります 。このような課題に対しては、業界標準のツール(CMRTなど)の活用、業界イニシアチブへの参加、データ管理・分析のためのソフトウェアソリューションの導入などが有効です 。
まとめ:紛争鉱物問題への理解を深め、責任ある調達を実現するために
紛争鉱物問題は、企業の倫理観と社会的責任が問われる重要な課題であり、各国・地域で関連法規制が強化されています。サプライチェーン担当者は、これらの動向を把握し、自社のリスク評価と効果的なデューデリジェンスを実施することが不可欠です。サプライヤーとの連携、業界標準ツールの活用、最新情報の収集を通じて理解を深め、責任ある調達を実現していくことが、企業の持続的な成長と信頼性向上につながります。
サステナビリティへの取り組みは、紛争鉱物問題に留まりません。企業価値向上と持続可能な社会の実現には、より広範なESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みが重要です。
そこで、アスエネESGをご紹介します。アスエネESGは、企業のESG経営を総合的に支援するクラウドサービスで、サプライチェーンを含む環境負荷の算定・可視化、社会課題への対応、ガバナンス強化などを一元的にサポートします。幅広いESG課題への取り組みを効率化し、企業価値向上に貢献します。
責任ある調達とESG経営の推進に、ぜひアスエネESGの導入をご検討ください。