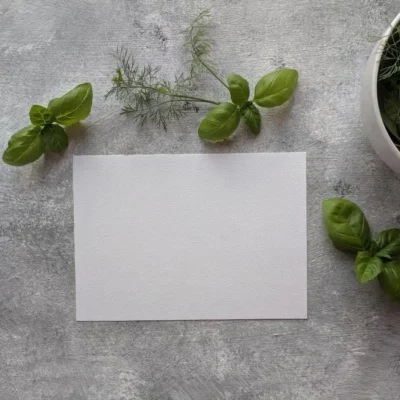持続可能なプラスチック生産を実現するために、今注目されているのが「マスバランス方式」です。この仕組みには、環境への負荷を大幅に減らしつつ、企業が環境保護と経済的利益の両立を図るための可能性が秘められています。
「マスバランス方式って何?」と思った方も多いのではないでしょうか?実は、この方式には 成功のカギとなる3つの要素 と 必ず守るべき原料表記ルール が存在します。これらを理解して活用すれば、企業は環境に優しい製品を効率的に提供できるようになるのです。
本記事では、マスバランス方式の基本的な仕組みをわかりやすく解説し、プラスチック業界における持続可能性の実現に向けた具体的なステップをご紹介します。これを読めば、あなたの企業も「環境配慮の先進企業」へと一歩近づくこと間違いありません。
INDEX
日本のプラスチック問題とCDP2025:環境情報開示が迫る水リスク対策とは
プラスチックは、私たちの生活に欠かせない素材です。軽量で丈夫、加工がしやすいという特性から、ペットボトルや食品容器、電気製品、自動車部品など、さまざまな製品に広く利用されています。
しかし、この便利さの裏側には大きな課題があります。プラスチックは自然環境で分解されにくく、不適切に廃棄されると長期間にわたって環境に残り、最終的には海へ流れ込んで深刻な悪影響を及ぼします。
特に日本は、一人あたりのプラスチック容器包装の廃棄量が世界で2番目というデータが示す通り、大量のプラスチックゴミを生み出している国です。この問題に対処するためには、プラスチックの廃棄量を削減し、適切なリサイクルや資源循環を促進する取り組みが急務となっています。
出典:経済産業省METI Journal ONLINE『【親子で学ぼう時事問題】プラスチック削減と資源循環社会』(2023/08/24)
プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定
2024年4月23日から29日、カナダのオタワで開催された第4回政府間交渉委員会(INC4)では、プラスチック汚染を2040年までにゼロにする目標が議論されました。日本は、使い捨てプラスチックの削減やリユース・リサイクル、適切な廃棄物管理の必要性を提案。さらに、条約実施には廃棄物管理システムの構築や行動計画の策定、進捗確認のための定期レビューが重要とされています。
出典:METI/経済産業省『プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第4回政府間交渉委員会の結果概要 』(2024/04/30)
マスバランス方式とは?CDP対応にもつながるプラスチック資源循環の新常識
マスバランス方式は、企業の持続可能性を高めるために非常に有効となります。ここでは、マスバランス方式についてご紹介します。
マスバランス方式とは
マスバランス方式は、特定の特徴を持つ原料(例:バイオマス由来原料)と、それ以外の原料(例:化石資源由来原料)を混ぜた際に、投入された原料の量に応じてその特徴を製品の一部に割り当てる方法です。
例えば、混合された製品に化石資源由来とバイオマス由来の原料がそれぞれ同じ割合で含まれている場合でも、マスバランス方式を適用することで、製品の一部に「100%バイオマス由来」の特性を割り当てることが可能です。この結果、その製品は「100%バイオマス由来」とみなされます。
出典:環境省『令和5年度バイオプラスチック及び再生材 利用の促進に向けた調査・検討委託業務 報告書』p,62.(2024/03/04)
プラスチックへのマスバランス方式が適用された背景
最近では、化石資源由来の原料にバイオマス由来や廃プラスチック由来の原料を混ぜてプラスチックを製造する方法が広がっています。しかし、製造ロットごとにバイオマスや廃プラスチックの割合が異なるため、それらを平均化する必要があります。現在、これらの割合が化石資源由来の原料よりも少ないことから、効率的な管理手法としてマスバランス方式が採用されています。
出典:環境省『令和5年度バイオプラスチック及び再生材 利用の促進に向けた調査・検討委託業務 報告書』p,63.(2024/03/04)
マスバランス方式×CDPで脱炭素を加速:成功の鍵となる3つの要素とは
マスバランス方式を用いてバイオマスプラスチックや再生プラスチックを利用する際、環境価値が見えにくいという課題があります。そのため、以下の3つの要素を満たすことが重要です。
1)環境効果の把握
バイオプラスチックや再生プラスチックの使用による環境負荷削減効果を正確に評価する必要があります。これを実現するためには、LCA(ライフサイクルアセスメント)などを活用し、専門家と協力してデータを収集・分析することが重要です。
出典:環境省『プラスチック資源循環におけるマスバランス方式の活用に関する基本的な考え方』(2024/09/26)
2)環境価値の適正な管理
バイオマスプラスチックや再生プラスチックの投入量(インプット)と使用量(アウトプット)を、サプライチェーン全体で正確に把握・管理する必要があります。第三者機関の評価や認証を活用し、信頼性と透明性を確保することが求められます。
出典:環境省『プラスチック資源循環におけるマスバランス方式の活用に関する基本的な考え方』(2024/09/26)
3)適切な表示・コミュニケーション
環境価値を消費者に正しく伝えるためには、環境効果の把握と適切な管理に基づく表示が不可欠です。製品特性に合った情報を分かりやすく伝えることで、消費者に環境価値を正しく理解してもらうことができます。必要に応じて第三者機関と連携し、透明性を高めましょう。
出典:環境省『プラスチック資源循環におけるマスバランス方式の活用に関する基本的な考え方』(2024/09/26)
マスバランス方式における原料表記とCDP:透明性の担保と水リスク情報の重要性
プラスチックのマスバランス方式に関する原料表記にはルールがあります。ここでは、そのルールについてご紹介します。
バイオマス由来の原料の割合を正確に表記する
バイオマス割当プラスチックが普及する中、誤解を招く表示はグリーンウォッシュと指摘されるリスクがあります。そのため、消費者に正確な情報を提供することが重要です。例えば、「バイオマス原料由来を〇%割り当てたプラスチック」といった正確な表示は許容されますが、「含有」「配合」など実際の配合を誤解させる表現は禁止されています。
出典:日本環境協会『エコマーク認定基準における「バイオマス由来特性を割り当てた プラスチック」の取扱方針』p,22.(2022/05/17)
マスバランス方式と他の配合材料は区別する
将来的に、クラッキング設備でバイオマス原料の使用が増えると、同じ製品グループ内でバイオマス特性が割り当てられていない製品にも、14C法でバイオマス由来の炭素が検出される可能性があります。この場合、既に特性が割り当てられているため、配合されていると主張することは禁止されます。また、多層フィルムや部分的にバイオマスを含む製品では、マスバランス方式の材料と実際の配合材料を区別して表示する必要があります。
出典:日本環境協会『エコマーク認定基準における「バイオマス由来特性を割り当てた プラスチック」の取扱方針』p,22.(2022/05/17)
まとめ:CDP2025に備えたマスバランス方式の実践と水環境配慮のポイント
マスバランス方式とは、バイオマス原料と化石資源原料を混ぜて使用する際、その使用量に応じてバイオマス原料の特性を製品に割り当てる方法です。プラスチックは自然環境で分解されにくく、海洋汚染など深刻な環境問題を引き起こすため、この方式は効果的な対策として注目されています。
重要な3つの要素
- 環境評価の把握
バイオマスプラスチックの利用による環境負荷削減効果を、LCA(ライフサイクルアセスメント)を活用して正確に理解すること。 - 環境価値の適正な管理
サプライチェーン全体で投入量と使用量を適切に把握し、第三者機関の評価を活用して透明性を確保すること。 - 適切な表示とコミュニケーション
ユーザーや消費者が正しく理解できるよう、原料の割合を正確に表記し、マスバランス方式と他の配合材料を明確に区別すること。
企業がこれらの要素を確実に実践することで、環境保護に貢献して持続可能な社会の実現を目指していきましょう。