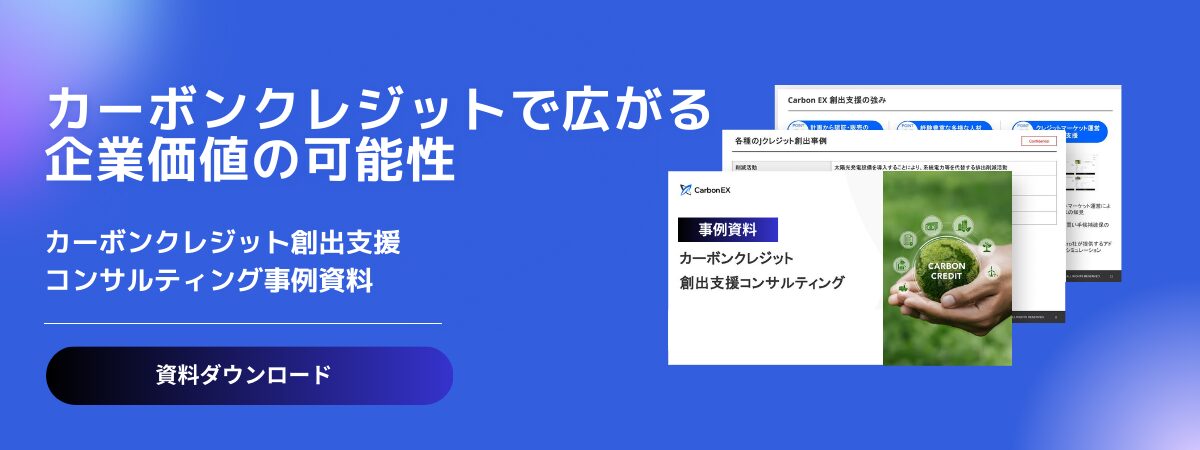2020年6月、政府は電力買い取りの新しいしくみであるFIP制度の導入を決定しました。政府は再生可能エネルギーを主電源にするため、2022年4月のからのFIP制度導入を目指します。FIP制度とはいったいどのような制度なのでしょうか。また従来のFIT制度とはどのように違うのでしょうか。
今回はFIP制度の概要やFIP制度とFIT制度の違い、FIP制度の種類や先行して導入している欧州の事例などについて解説します。
INDEX
電力買取の仕組みであるFIP制度とは?
FIPとは、Feed-in Premiumの略語です。資源エネルギー庁はFIPを「再生可能エネルギーの自立普及・完全自由競争に向けて、再エネ発電事業者が市場価格で電力販売する場合(市場での売却など)に、市場価格にプレミアム上乗せする方式」と説明しています。ここでのプレミアムとは補助金のことを指します。
出典:資源エネルギー庁『再生可能エネルギーの大量導入時代における 政策課題と次世代電力ネットワークの在り方』(p35)(2017/12/18)
現在、FIP制度はドイツやフランス、イギリス、イタリアなどのヨーロッパ諸国で積極的に採用されています。早くからFIP制度を取り入れたドイツやイタリアでは段階的にFIP制度の適用対象を増やしています。
FIP制度は、再生可能エネルギーの買取価格を市場価格に連動したものに近づけるこための試みといえるでしょう。

出典:資源エネルギー庁『固定価格買取制度等 ガイドブック 2021年度版』(p4)(2021)
FIP制度とFIT制度の違い
FIP制度と比較されるのが現行制度であるFIT制度です。FIT(Feed-in Tariff)制度は「固定価格買取制度」と訳される仕組みで、「再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度」です。
fit出典:資源エネルギー庁『資料1 FIP制度の詳細設計②』(p5)(2020/8/31)
出典:資源エネルギー庁『制度の概要|固定価格買取制度|』
FIT制度は、買取価格が需給に関係なく常に一定で、電力事業者からすれば経営計画が立てやすい制度です。しかし、FITを持続するには巨額に資金が必要です。その財源を捻出するため、国は電力利用者から「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を徴収しています。
それに対し、FIP制度は買取価格が市場価格と連動します。補助金は市場価格に上乗せされるので、市場価格が低ければ、FIT制度より買取価格が下がります。反対に、市場価格が高ければ、FIT制度より買取価格が上がります。FIT制度に比べ、補助金が少なくて済むことが期待されます。

出典:資源エネルギー庁『FIP制度の詳細設計と アグリゲーションビジネスの更なる活性化④』(p8)(2021/1/13)
将来的に政府はFIT制度からFIP制度へと移行させようと考えています。完全にFIT制度を廃止しないにせよ、今後はFIP制度が再生可能エネルギー買取の主流となると考えるべきでしょう。
FIP制度の種類

出典:資源エネルギー庁『再生可能エネルギーの大量導入時代における 政策課題と次世代電力ネットワークの在り方』(p35)(2017/12/18)
FIP制度の特徴は市場価格に補助金(プレミアム)がつくことにあります。このプレミアムのつけかたによって、FIP制度は2つに大別できます。以下、上記の資料を元に、二つのFIP制度の特徴をまとめます。
(1)プレミアム固定型FIP
プレミアム固定型FIPとは、電力の市場価格にプレミアムとして一定の補助金をつける方式です。この場合、基本となる電力の市場価格が高いとき、言い換えれば需要が大きいときに電力を販売すると大きな利益を得られます。
その反面、電力需要が小さく、市場価格が低い状態が続けば発電業者の収入が減ってしまい経営に打撃を与えかねません。こうした不安定さを解消できるのが最低価格と最高価格を設定する上限・下限付きのプレミアム固定型FIPです。
ただ、上限や下限をどのように決めるのかは非常に難しい問題であり、実施に当たっては紆余曲折が予想されます。
(2)プレミアム変動型FIP
プレミアム変動型FIPとは、プレミアムの金額を電力の市場価格に応じて変動させる方式です。電力価格が低いときはプレミアムを多く付与し、電力価格が高くなればプレミアムを少なくします。そして、想定される金額より電力価格が上昇した場合にはプレミアムを付与しません。
プレミアム変動型FIPの場合、電力業者は一定以上の収入を保証されるため経営が安定しやすくなります。しかし、電力価格が低迷すると、プレミアム固定型FIPよりも多くの補助金を必要とします。そうすると、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」などの国民負担が増大してしまいます。
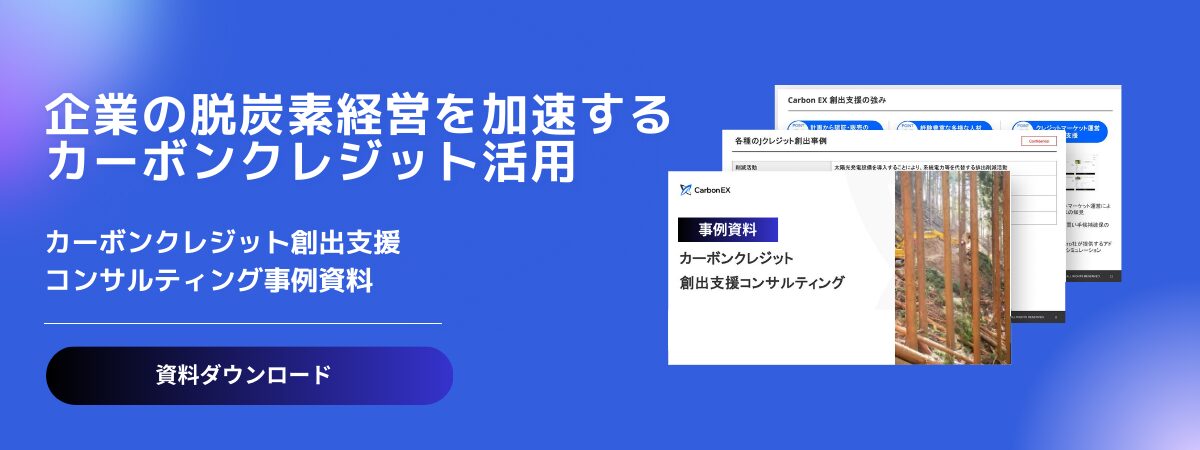
FIP制度による各国の電力買い取り事例

出典:資源エネルギー庁『資料1 FIP制度の詳細設計②』(p15)(2020/10/9)
ドイツでは2012年にFIP制度がはじまりました。全ての電源が、規模の大小を問わず、FIT制度かFIP制度を選択できるようになりました。
2014年からは500kW以上の新規申請はFIPのみとされます。2016年以降は100kW以上の新規申請をFIPのみとし、徐々にFIT制度の対象を狭めています。
イタリアでは2013年からFIP制度を導入しました。こちらも全ての電源が対象です。1MW以上の電源はFIP制度のみとしました。これが2016年、2019年と年を追うごとにFIP制度の対象が拡大されます。基本的な流れはドイツと同じと考えてよいでしょう。
また、イギリスではFIP制度によく似たCfD制度を2014年から導入。5kw超の新規申し込みについてはCfD制度のみ適用としました。さらに2016年にはフランスでもFIP制度導入されます。
まとめ:FIP制度を理解し、電力売却で利益を得よう!

出典:資源エネルギー庁『FIT制度の抜本見直しと 再生可能エネルギー政策の再構築』(p13)(2019/4/22)
再生可能エネルギーを普及させるため、日本政府は2012年度からFIT制度を導入しました。その効果は非常に大きく、再生可能エネルギー比率は大きく上昇しました。
その一方、電力利用者の負担である「再生可能エネルギー発電促進賦課金」は増加の一途をだどっています。再生可能エネルギーの普及促進という点からも、国民負担の増加という点からも、FIT制度は見直すべき時期に来ています。
国が事業者に支払う補助金(プレミアム)を減らしつつ、市場価格に連動したFIP制度への以降は不可避の流れといえるでしょう。
そうであるならば、FIP制度の内容を理解し、企業の利益を拡大するチャンスを掴むべきです。太陽光発電設備などを使って生み出した電力をタイミングよく売電できれば企業収益の増加に寄与するでしょう。
需要が少なく、市場価格が低いときは電力を蓄電池にたくわえ、需要が増え、電力の市場価格が上がった時に売電したり、自家用として消費し電力料金を節約したりすることが可能となります。FIP制度の理解は会社の利益を増加させるきっかけになるかもしれません。