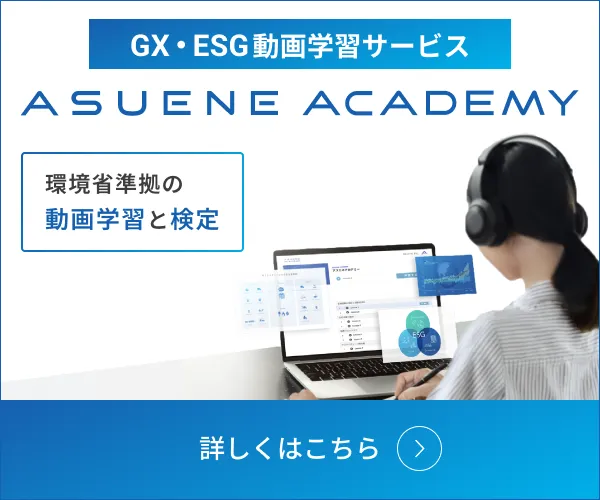IFRSが開発する「S1」「S2」について、それぞれの内容や日本がどのように対応しているのか詳しく解説します。
IFRSは、2021年にイギリスのグラスゴーで開催されたCOP26で、国際持続可能基準理事会(ISSB)の設立を発表し、高品質で包括的な世界でのベースラインとなるサステナビリティの情報開示基準「S1」「S2」を開発しています。
現在、各国や機関投資家が2050年カーボンニュートラルなどの脱炭素目標を宣言する中、企業においても脱炭素経営が求められています。持続可能な社会を目指すためには企業として何をすべきなのか、ぜひ参考にしてみてください。
INDEX
IFRSとは?
IFRS財団は「より優れた情報がより良い経済および投資の意思決定をサポートする」という信念に基づき設立された公益団体です。このIFRSが設立したISSBとはどのような委員会で、IFRS S1・S2がどのようなものなのか解説していきます。
IFRSが設立したISSBとは
IFRSでは、会計基準(企業における会計処理とその報告に関するルール)の設定や、財務報告書の作成・監査・利用、会計教育における実務経験を持った専門家が、会計基準とその解釈指針を策定する「国際会計基準審議会(IASB)」を運営しています。
出典:IFRS「International Accounting Standards Board」
IFRSでは2021年に、現在の経済や投資の意思決定においては、サステナビリティに関する情報のニーズが大きくなっていることから、IASBの姉妹委員会としてISSBを設立しました。ISSBでは、企業のサステナビリティ情報の開示に一貫性を持たせ、投資に際して比較することができるよう、気候変動リスクをはじめとするESG(企業の持続可能性をはかる、E:環境、S:社会、G:企業統治の3要素)情報の開示に関する国際基準の策定を行っています。
ISSBはCDSB、TCFD、VRF、世界経済フォーラムの、サステナビリティに関するフレームワークを作成する各機関と共同で基準を策定しており、こと気候変動関連情報に関してはTCFD提言に基づく情報開示を行うこととしています。
出典:環境省「シナリオ分析の実施ステップと最新事例」(p21)
出典:IFRS「International Sustainability Standards Board」
ISSBが作成した財務情報開示基準がIFRS S1・S2
ISBBは開発において4つの主要な目標を定めています。
- サステナビリティ情報開示の国際的なベースラインとなる基準を開発する
- 投資家の情報ニーズを満たす
- 企業が包括的なサステナビリティ情報を世界の資本市場に提供できるようにする
- 管轄区域に特化した開示や、より広範なステークホルダー(企業の利害関係者)グループを対象とした開示との相互運用性を促進する
これを踏まえ、ISSBではESG情報開示に関する国際基準の策定を進めており、2022年3月には基準案の発表、2023年6月頃にはパブリックコメントを反映した基準案の最終化を行い、2024年1月から基準の適用が始まる予定となっています。
この情報開示基準は項目により大きく以下の2つに分類されます。
- サステナビリティ関連財務情報の開示(S1)
- 気候関連情報の開示(S2)
出典:IFRS「International Sustainability Standards Board」
出典:環境省「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ」(2023/3)(p25)
IFRS S1 S2の内容について
IFRSが策定するサステナビリティ情報開示基準はS1とS2に分けられますが、それぞれの内容とはどのようなものなのでしょうか。ここではS1、S2それぞれの内容とポイントについて解説していきます。
IFRS S1の開示内容とポイント
IFRS S1の目的は、一般目的財務報告(企業の財務諸表とサステナビリティ関連情報)の利用者が、企業への資源提供に関する意思決定を行う際に有用なサステナビリティ関連情報の開示を要求することです。
S1は、企業がこの開示情報をどのように作成し、報告するかの規定となっており、開示の内容と表示に関する、サステナビリティ関連のリスクと機会を管理するために使用するガバナンスのプロセスや手順、企業の戦略、設定した目標に対する進捗などを定めています。
S1で定められている基本事項の内容は以下のようになっています。
- 報告対象企業
対象企業は「一般目的財務諸表の作成を要求されるか又は選択する企業」とする。ただし、開示対象であるサステナビリティ関連の情報は財務諸表に関わらず、報告企業のバリューチェーン全体から識別すること。
- つながりのある情報
サステナビリティ関連財務情報の開示は、財務諸表と一体にすること。そのため、関連財務情報同士のつながりや、財務諸表に含まれる情報との関連づけが理解できるような情報提供をすること。
- 適正表示
サステナビリティ関連のリスクや機会を適正に表示し、不十分な場合は追加して開示を行うこと。
- 重要性
重要性のある情報の開示を行うこと。なお、「省略、誤表示、故意に隠した時に、一般目的財務報告の利用者の意思決定に大きな影響を与えることが合理的に予想される情報」を重要性のある情報とする。
- 比較情報
比較情報は、当期に開示した全ての指標について開示を行うこと。また、比較情報の修正が不可能な場合は、その旨を開示すること。
- 報告頻度
関連する財務諸表と同じ期間を開示対象とし、財務諸表と同時に報告すること。
- 情報の記載場所
一般目的財務報告の一部として開示すること。なお、情報の記載場所について、特定の場所は指定しない。ISSBではこの内容について寄せられるコメントを踏まえて審議を行い、最終基準として決定する予定となっています。
出典:企業会計基準委員会「ISSB公開草案の全体像及びISSB公開草案IFRS S1号サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項(S1基準案)について」(p7~P9)
出典:自然エネルギー財団「企業の気候変動情報開示の新国際基準発表」(2023/7/3)
IFRS S2の開示内容とポイント
IFRS S2の目的は、企業価値の評価に有用な、「重大な気候関連のリスク及び機会」に関する重要性がある情報の開示を要求することです。
S2で定められている、気候関連のリスク及び内容について開示すべき情報は以下のようになっています。
- 重大な気候関連のリスク及び機会に関する情報
重大な気候関連のリスク及び機会の説明や影響を及ぼすと考えられる時間軸、時間軸の定義付けと資本配分計画のつながり、リスクの分類。
- 重大な気候関連のリスク及び機会が企業のビジネスモデル・バリューチェーンに与える影響に関する情報
重大な気候関連のリスク及び機会が、現在及び今後、企業のビジネスモデルやバリュー・チェーンに与えるであろう影響。特に、バリュー・チェーンのどの部分に、重大な気候関連のリスク及び機会が集中しているか。
- 重大な気候関連のリスク及び機会が企業の戦略・意思決定に与える影響に関する情報
重大な気候関連のリスク及び機会が、脱炭素戦略を含む企業の戦略や意思決定に与える影響。特にこれらに対して、使用原材料や製品仕様の変更など、どのような取り組みによって適応し、またリスクを緩和させるか。
- 重大な気候関連のリスク及び機会が財政状態、業績及びキャッシュフローに与える影響に関する情報
重大な気候関連のリスク及び機会が、現在及び今後、企業の財政状態や財務業績、キャッシュフローに与える影響。なお、これらは単一の金額や金額の範囲による定量的な情報とし、できない場合にはその理由を明示する。
- 重大な気候関連のリスクに対する企業戦略のレジリエンスに関する情報
今後起こりうる気候の変動や、リスク・機会そのものの不確実性に対する、企業戦略のレジリエンス(強靭性)。特に、シナリオによるレジリエンスの分析結果とその方法。企業はS2に付属する産業別開示要求を参照しながら、重大な気候関連のリスク及び機会を識別し、これらの各項目について開示を行うことになります。こちらについても、ISSBでのコメントを踏まえた審議のうえ、最終基準が決定・公表されます。
出典:企業会計基準委員会「ISSB公開草案のIFRS S2号気候関連開示(S2基準案)について」(p5~6)
出典:自然エネルギー財団「企業の気候変動情報開示の新国際基準発表」(2023/7/3)
IFRS S1・S2についての日本の動向
IFRSによるサステナビリティ関連の情報開示基準がグローバルスタンダードと言える現在、日本ではどのように対応しているのでしょうか。ここでは関係のある日本政府や経団連の動きについて解説します。
IFRSへの金融庁の対応
金融庁では、IFRS財団がISSB設立をした2021年の同月に、IFRS財団評議員会議長宛に金融担当大臣名でレターを送付しています。
内容は
- ISSBの設立を歓迎し、サステナビリティ開示基準の策定に積極的に貢献していくこと
- サステナビリティ開示におけるアジア・オセアニア地域の拠点として東京にあるオフィスを活用することを支持する
- ISSBに対する資金拠出として約1億1千万円の予算措置を予定していること
となっており、ISSBに協力する姿勢が示されています。
出典:金融庁「国際サステナビリティ基準審議会に関するIFRS財団評議員会議長へのレター発出について」
出典:金融庁「鈴木俊一金融担当大臣よりIFRS財団評議員会議長に宛てたレター」(2021/11/26)
また、ISSBのサステナビリティ開示基準を踏まえ、金融審議会では有価証券報告書にサステナビリティ情報の記載欄の新設を提言し、2022年に設立するサステナビリティ基準委員会(SSBJ)で具体的開示内容の基準を検討することになっています。
出典:金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令等改正の解説」(2023/5)(p4)
出典:金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正案の公表について」(2023/11/7)
経団連がIFRSの報告基準を支持
日本の代表的な企業1400社以上から構成される、日本最大の総合経済団体である経団連では、IFRSが公表した「サステナビリティ報告」についてコメントしています。
内容は
- IFRS財団のサステナビリティ報告基準の開発という取り組みに敬意を払い、その活動を支持する。
- サステナビリティ情報の開示については、投資家を含めた資本市場からの要請が高まっており、日本においてもサステナビリティ情報を積極的に開示しようとする企業が増えている。
- 経団連でも2050年のカーボンニュートラルの実現に向けイノベーションの創出やサステナブルファイナンスの推進に取り組んでおり、IFRSの活動は軌を一とするもので歓迎し積極的に貢献する用意がある。
- 日本の企業の多くがIFRSを適用しており、サステナビリティ報告基準においてもIFRSの高品質化に向けたIASBの取り組みに悪影響を及ぼさないことを求める。
となっています。
出典:日本経済団体連合会「経団連:IFRS財団 市中協議文書「サステナビリティ報告」に対する意見 」(2020-12-18)
まとめ:事業のグローバル化推進のためにIFRS S1・S2を正しく理解しよう!
投資家によるサステナビリティ関連情報の開示へのニーズを受け、IFRSは新たにISSBを設立し、国際的に画一された開示基準である「IFRS S1・S2」を策定しました。IFRS S1・S2はサステナビリティ開示基準として世界的なスタンダードとなることは間違いありません。これからの企業経営の大きな要素となるサステナビリティについて考えるのであれば今後重要な基準となるでしょう。
日本においても政府や企業団体が賛同の意を示し、活用に積極的な姿勢を示しています。企業の環境問題の取り組みについて必要なことをしっかり理解し、事業の発展につなげていきましょう。