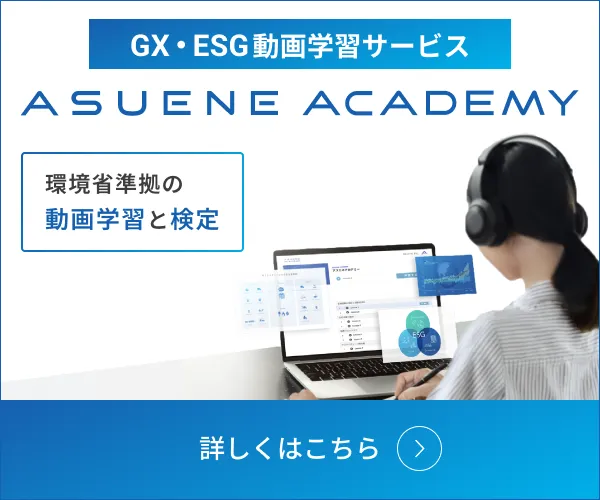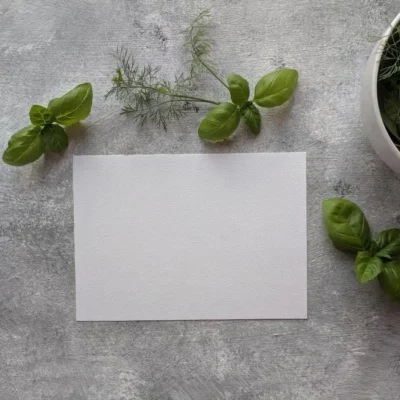電気自動車は、二酸化炭素排出が少なく環境に優しいエコな車だと言われており、SDGsを目指す近年において、電気自動車の普及はとても重要です。しかし、その一方で普及率は低く、その原因の一つが生産に必要な資源問題だとされています。この記事では、そんな資源問題についてや、資源問題への対策などを解説していきます。
INDEX
電気自動車による環境への配慮とテスラの役割
電気自動車が世界的に注目される理由は、走行時の二酸化炭素排出量を極限まで減らせるためです。従来の自動車は、ガソリンを燃焼させると共に二酸化炭素を排出していましたが、電気自動車のエネルギーは電気であり、二酸化炭素を排出せずに走行が可能となります。
また、電気の発電を再生可能エネルギーで行なうことで、二酸化炭素の排出量はさらに削減されます。水力発電・太陽光発電・風力発電などの「ゼロエミッション電源」だけで発電できれば、二酸化炭素の排出量をゼロにする(カーボンニュートラル)ことも夢ではありません。
ゼロエミッション電源比率は年々増えてきており、日本政府は2030年時点での電気供給量の目安として、約44%(再エネ:22〜24%、原子力20〜22%)を見通しています。地球温暖化対策は世界的にも取り組まれ、日本はもちろん、世界中で電気自動車の有用性に注目されているのです。
電気自動車についてさらに詳しく知りたい方はこちら▼
出典:経済産業省 資源エネルギー庁『電気自動車(EV)は次世代のエネルギー構造を変える?!』(2017/10/12)
電気自動車が抱える環境問題の裏側 ― バッテリーに必要な資源とそのリスク
電気自動車が抱える資源問題と実際にどのような原材料が使用されているのか?について、解説します。
(1)電気自動車が抱える資源問題とは?
電気自動車(EV)は、持続可能な社会の実現に向けた重要な技術として、世界中で注目を集めています。しかし、その普及には、バッテリーやモーターに使用される資源の供給に関する課題が大きく立ちはだかっています。
電気自動車の普及を支える資源
電気自動車の心臓部であるバッテリーには、リチウム、コバルト、ニッケルなどのレアメタルが不可欠です。これらの資源は、エネルギー密度が高く、軽量で、充放電を繰り返しても劣化しにくいという特性を持つため、電気自動車の性能を左右する重要な要素となっています。
また、電気自動車のモーターには、ネオジムやジスプロシウムなどのレアアースが使用されています。レアアースは、強力な磁力を生み出すことができるため、小型で高性能なモーターの製造に不可欠です。
出典:東洋経済 ONLINE『EV電池に必須の「リチウム」の確保は大丈夫か』
出典:Bloomberag『イーロン・マスク氏安堵、常軌逸したリチウム価格にデフレ圧力』
(2)電気自動車普及の鍵を握るレアアースとは?
電気自動車を含む電動車(xEV)普及のカギを握っているのが希少鉱物であるレアアースです。ここでは、レアアースの定義や用途、電動車の普及に必要なレアアースなどについてまとめます。
レアアースの定義
金属は大きく分けて鉄と非鉄金属に分けられます。非鉄金属のうち、銅や亜鉛、鉛、アルミニウムといった生産量が多く、様々な材料に加工される金属をベースメタルといいます。
一方、存在する量が少ない、あるいは大量に存在していても精錬が難しく生産量が少ない金属をレアメタルといいます。なかでも、希土類とよばれる17の元素は「レアアース」とよばれ入手が困難な金属となっています。
出典:外務省『わかる!国際情勢 金属鉱物資源をめぐる外交的取組~ベースメタルとレアメタルの安定確保に向けて』
出典:資源エネルギー庁『2050年カーボンニュートラル社会実現 に向けた鉱物資源政策』(2021/2/5)(p23)
日本はレアアースの60%以上を中国からの輸入に依存しています。資源エネルギー庁は高性能モーター磁石用ネオジムに使用するレアアースは需要量と供給量がほぼ「需給均衡」の状態が続くとし、常に供給不安があると指摘しています。
レアメタル・レアアースの用途
レアメタルやレアアースはどのように使われているのでしょうか。

レアアースは電気自動車をはじめとする次世代自動車やパソコン、携帯電話(スマートフォン)、デジタルカメラ、テレビといった製品に使用されています。
特に次世代自動車ではレアアース磁石を用いた小型モータ、液晶画面の材料、排気ガス浄化装置の材料として利用されています。
電動車(xEV)に必要な主な鉱物資源

電気自動車やハイブリッド車を含む車両は電動車(xEV)とよばれます。電動車にはリチウムやニッケル、コバルトといったレアメタルやレアアースの一種であるネオジムが使用されています。
しかし、レアメタルやレアアースは国内でほとんど算出せず輸入に依存しています。電動車を安定的に生産するにはレアメタルやレアアースの確保が必須となるでしょう。
各材料の調達方法
- リチウム
鉱石と塩湖から採掘されます。鉱石由来のリチウムは主に豪州で、塩湖由来のリチウムは主にチリやアルゼンチンで採掘されます。
- ニッケル
鉱石と土壌(ラテライト)から採掘されます。土壌由来のものは技術の進展で高純度のニッケルも製造可能になっています。
- コバルト
主に銅やニッケルの副産物として採取され、大部分がコンゴ民主共和国で生産されています。
出典:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構『[カーボンニュートラル社会実現のカギを握る]バッテリーメタルの教科書(1)』
電気自動車が抱える環境問題への備え ― 日本の鉱物資源政策とEV競争への対応
日本国内で産出しないレアアースを確保するため、日本政府・民間企業が一丸となって取り組んでいます。
カーボンニュートラル社会実現のため必要な鉱物資源
2020年10月26日、当時の菅総理大臣は所信表明演説の中で2050年までにカーボンニュートラル社会を実現すると発表しました。
カーボンニュートラルとは二酸化炭素(CO2)の排出量と削減・吸収量を等しくすることで事実上、二酸化炭素の排出をゼロにすることです。

出典:資源エネルギー庁『2050年カーボンニュートラル社会実現 に向けた鉱物資源政策』(2021/2/15)(p16)
カーボンニュートラル実現のため、発電・蓄電・モーターなどあらゆる分野で新技術が導入されます。レアアースは風力発電や高性能磁石、燃料電池などで必要とされていて安定的な確保が急務です。
主な鉱物資源の自給率
日本で使用する金属はどのくらい自給できているのでしょうか。自給率といっても、日本国内で生産されるものはほとんどないため、日本企業が外国で確保した権益ベースでの自給率で考えると以下のとおりです。
 出典:資源エネルギー庁『2050年カーボンニュートラル社会実現 に向けた鉱物資源政策』(2021/2/15)(p24)
出典:資源エネルギー庁『2050年カーボンニュートラル社会実現 に向けた鉱物資源政策』(2021/2/15)(p24)
ベースメタルでは銅や鉛、レアメタルではマンガンやニオブなどが必要量の50%近く確保できています。しかし、モリブデンやチタン、アンチモンといった物質は10%も確保できていません。
後述しますが、レアアースは主要生産国である中国の輸出管理が厳しいため権益確保が難しい状態です。
資源問題への対策
資源問題として以下のような対策が研究・開発されています。
資源量を減らしたバッテリー(リチウムイオン電池)の改良
電気自動車(EV)の普及にはレアメタル(鉱物資源)が必要であり、その供給が課題となっています。EVの車体価格の約3分の1はバッテリーによって占められ、そのバッテリーにはリチウム、コバルト、ニッケル、グラファイトなどのレアメタルが使用されています。これらのレアメタルは、価格が高騰する可能性があり、また供給国には政治的リスクも存在します。
そのため、以下の3点が懸念されており、改良が必要とされています。
- コスト削減
バッテリーがEVの車体価格の大部分を占めているため、コスト削減が必要です。
- 供給安定
レアメタルの供給が不安定であり、特定の国に依存している場合が多いため、供給を安定させる必要があります。
- 性能向上
現在のバッテリー技術では、充電時間や走行距離に制限があります。これを改良することで、EVの普及がさらに進むでしょう。
出典:経済産業省 資源エネルギー庁『EV普及のカギをにぎるレアメタル』(2018年4月20日)
製造拠点の増設
価格高騰による問題対策として、製造拠点の増設が挙げられます。採掘されるリチウムは一旦中国などで炭酸リチウムに精製されますが、他国で精製を挟むことでその分のコストが増加してしまいます。コスト削減を考えるなら、精製を挟まなくても済むよう、採掘拠点である国か、もしくは自国に精製拠点を用意することが大切です。
リチウム価格の高騰によって悩んでいたイーロン・マスク氏も、価格を安定化させるため、アメリカのテキサス州にリチウム精製所の着工を開始しています。電気自動車の増産を考えるなら、新しい生産形態が必要になってくるでしょう。
ただ、日本国内での精製は現状難しいといえます。リチウムの精製には大量の廃棄物が発生し、日本国内だけでは処理しきれないからです。リチウムの精製を主に中国が行っているのも、国土の広さと環境規制の緩さが理由といえるでしょう。
最近では採掘国であるオーストラリアでリチウムの精製も行なわれていますが、リチウムはほかの国も必要としており、日本が都合よく調達できるとは限りません。
日本では国内精製が難しいことから他国へ依存する必要があり、国内での電気自動車の生産は安定しないのが現状です。
出典:X Tesla Japan『世界最大級のリチウム精製施設をアメリカテキサス州で着工』
出典:東洋経済『EV電池に必須の「リチウム」の確保は大丈夫か』
新しい次世代電池の開発
リチウムやコバルトなどを必要としない方法として、資源を必要としない次世代電池の開発も進められています。代表的な技術として、水素技術が挙げられます。ガスや水などから水素を作りエネルギーとする技術であり、生産にリチウムを必要としないため、再生可能エネルギーから作ることも可能であり、注目されています。
出典:東京新聞『次世代電池の大本命 全固体電池、開発に期待 リチウムイオン電池の弱点改良』(2022年6月19日)
出典:みずほリサーチ&テクノロジーズ『蓄電池技術はどこに向かうのか?(4/6)』
緊急時に備えた備蓄
日本の政府や企業は国際環境の変化などによる緊急事態に備え、レアメタル・レアアースなどの備蓄を行っています。政府は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)を通じて60日分の国内消費量に相当するレアメタル・レアアースを備蓄しています。また、政府はJOGMECの借り入れには政府保証を付けるなど金融面でも支援しています。
出典:資源エネルギー庁『2050年カーボンニュートラル社会実現 に向けた鉱物資源政策』(2021/2/15)(p32)
電気自動車が抱える環境問題解決へ― 鉱物資源を巡る各国の戦略とは?
重要な鉱産資源について、各国政府はどのように対応しているのでしょうか。中国・アメリカ・ヨーロッパでの対応を紹介します。
中国の動向
中国政府は国内レアアース産業の管理を強化しています。1990年代まで中国産レアアースは安価に入手できました。しかし、2010年以降、中国政府はレアアースの輸出枠を大幅に削減したため、レアアース価格が高騰しました。
2020年12月、中国で輸出管理法が施行され、「中国製の規制品目を含む製品の再輸出の際に、中国域外であっても中国政府の許可を義務付け」られました。
また、2021年にレアアースに対する規制を強化するレアアース管理条例の案が公表されるなど中国政府による輸出規制が強化されています。
出典:資源エネルギー庁『2050年カーボンニュートラル社会実現 に向けた鉱物資源政策』(2021/2/15)(p7)
アメリカの動向
トランプ政権のころ、アメリカと中国の関係は悪化し互いに関税をかけあう米中貿易戦争といってもよい状態になりました。
2020年9月、トランプ政権はレアアースなどを中国に依存度が高い重要物資として言及。重要鉱物に関する調査結果や提言の報告を義務付けました。バイデン政権成立後、米エネルギー省の下に重要鉱物を確保するための「鉱物持続可能課)を新設し、重要鉱物に関する技術開発や国際連携推進を図っています。
出典:資源エネルギー庁『2050年カーボンニュートラル社会実現 に向けた鉱物資源政策』(2021/2/15)(p9)
EUの動向
環境規制が厳しいEUでは脱炭素化を推進しています。そのためにはレアメタルやレアアースの確保が欠かせません。2020年9月、欧州委員会は「重要鉱物(Critical Raw Material)に関する行動計画」を発表しました。主な内容は以下のとおりです。
- EU域内で強靭なサプライチェーンを構築する
- 資源の利用循環や持続可能な製品とイノベーション
- 欧州域内からの供給
- カナダやアフリカからの調達強化
出典:資源エネルギー庁『2050年カーボンニュートラル社会実現 に向けた鉱物資源政策』(2021/2/15)(p10)
電気自動車が抱える資源問題以外の課題
電気自動車についての課題は、資源問題だけではありません。鉱物資源を発掘する際に発生する環境汚染も問題視されています。電気自動車の生産、特にバッテリーの生産は多数の鉱物資源を必要としており、その鉱物資源を採掘し精製する過程で水質汚染や土壌汚染といった環境汚染が発生してしまうのです。
製造で二酸化炭素を排出することから、「電気自動車は環境問題に効果がない」と考える人は少なくありません。今後電気自動車の普及を促進させるためにも、生産過程における対策が必要となります。
出典:CIGS キャノングローバル戦略研究所『電気自動車(EV)は本当に環境にやさしいのか』(2021年11月8日)
まとめ:電気自動車と環境問題、持続可能な社会に向けて
資源問題は、資源の供給量が消費量の増加に追いつかないことで発生します。これは、環境に優しいイメージのある電気自動車においても例外ではありません。電気自動車の普及には、リチウムやコバルトなどのレアメタルが不可欠ですが、これらの資源の採掘や精製は環境負荷を伴う場合があります。つまり、電気自動車が環境に貢献する一方で、新たな環境問題を引き起こす可能性も孕んでいるのです。
この事実は、企業活動においても同様の視点を持つことの重要性を示唆しています。例えば、自社が推進する事業が、直接的には環境に配慮しているように見えても、サプライチェーン全体や長期的な視点で見ると、新たな資源問題や環境負荷を生み出している可能性があります。
現在、世界はウクライナ戦争や円安など、予測不可能な国際情勢の変化に直面しています。これらの変化は、資源の安定供給や価格高騰に影響を与え、企業の持続可能な経営を脅かす要因となり得ます。
したがって、企業は電気自動車の例のように、常に広い視野を持ち、自社の事業活動が環境に与える影響を多角的に評価する必要があります。そして、国際情勢の変化を注視しながら、資源の効率的な利用、リサイクル、代替資源の活用などを推進し、持続可能な経営を目指すべきです。
つまり、企業は電気自動車の普及を通して、資源問題の複雑さを理解し、自社の事業活動においても、環境への影響を最小限に抑えつつ、持続可能な社会の実現に貢献していくことが求められます。