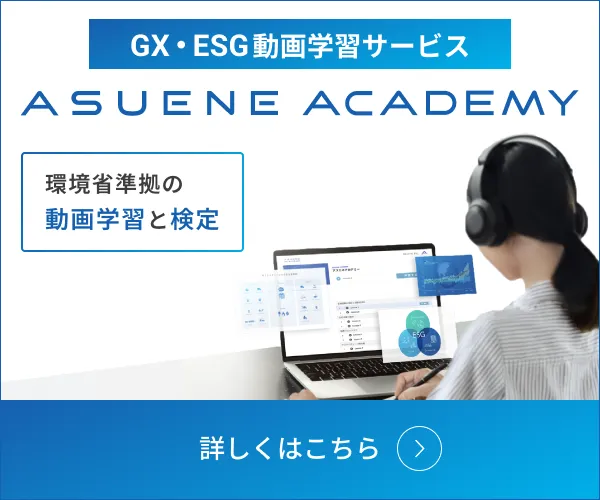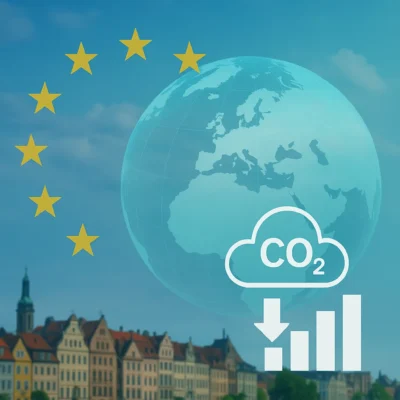水資源について考えるうえで「ウォーターフットプリント」という概念は非常に重要となります。この記事ではウォーターフットプリントがどのようなものか、またその計算方法について詳しく解説します。
現在、日本ではあまり重要視されていませんが、世界的には水資源の枯渇、汚染は深刻な問題となっています。これから日本でも起こりえるであろう問題について考えてみましょう。
INDEX
ウォーターフットプリントとは?
まず、ウォーターフットプリントがどのようなものなのかご紹介します。
ウォーターフットプリントとは?
ウォーターフットプリントは直訳すると「水の足跡」。つまり、食料や衣類などの生産に使われる水の量を定量的に評価するものです。
使う、着る、買う、売る、食べるといった人間の生活にはすべての過程で水が使われています。生産から廃棄、リサイクルまでのライフサイクル全体で限りある水資源がどのような目的で消費されているのかを把握することは持続可能な社会の実現にとってとても重要なことです。
ウォーターフットプリントは大きく3つに分類されます。
(1)ブルーウォーターフットプリント
河川や地下水が消費された量を示すものがブルーウォーターフットプリントです。ここでの消費は、作物や製品に取り込まれた分以外にも取水地点に戻らない分も含まれます。
(2)グリーンウォーターフットプリント
- 雨水から作物に取り込まれた量をグリーンウォーターフットプリントといいます。土壌に水分として蓄えられた量がどのくらいかを表しています。
(3)グレーウォーターフットプリント
- 農産物や畜産の飼料となる穀物を生産する際の肥料・農薬による水質汚染物質を環境基準に抑えるために希釈する水の量をグレーウォーターフットプリントといいます。
水環境の現在とウォーターフットプリントの必要性とは
世界の水環境は様々な調査により深刻な結果が公表されています。WWFではレポートの中で、「世界の淡水生物の多様性の豊かさが1970年と比較し、2020年では84%減少している」ことを指摘しています。
また、IPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム)のデータでは、アジア・オセアニア地域の急速な人口増加、経済成長により、早ければ2048年には漁業可能な水産資源が枯渇、2050年までに90%のサンゴ礁が劣化、また食品廃棄物は、2014年で推定8億7,000万トンの一般固形廃棄物が2030年には約14億トンにまで増加すると報告されており、これによる水質汚染が懸念されています。
出典:環境省『最新資料:109560_IGES_ipbes報告書(APRA)_h01-p19_05最終.indd (biodic.go.jp)』
日本は水資源の豊かな国であり、今は影響を感じることは難しいかもしれませんが、世界では渇水による被害も深刻となっており、これに対する対策が必要で、そのための評価指標としてウォーターフットプリントの活用が期待されています。
ウォーターフットプリントの計算方法
次にウォーターフットプリントの計算方法について簡単にまとめて説明します。実際の計算方法は非常に数値化の方法が細かいので計算の手順、考え方を理解しておきましょう。
目的と範囲の設定
評価の範囲や手法はどのような目的で利用するのかによって設定する必要があります。例として次のような事例があげられます。
- 水消費に配慮した環境配慮型製品の開発のため水消費の改善度合いを評価し、その結果を販売促進の材料・ツールとして活用したい。
- 企業としての環境問題に取り組む際に水消費についての改善施策を検討するため、リスクの把握が必要となり企業全体でのウォーターフットプリントの実施が必要。
- 教育機関や自治体が、子供に対して水環境・水の大切さを理解してもらうため、特定製品でのライフサイクル全体の水消費量、水質汚染とその中で自分の行動の影響を数量で示したい。
などとなり、目的として通常のLCA(ライフサイクルアセスメント)と同様の「調査結果の利用用途」、「調査の実施理由」、「調査結果の伝達先」、「比較主張を意図しているか」、「ウォーターフットプリントのみの評価かLCAの一部としての評価か」などを示していくことになります。
それぞれの場合により範囲や調査手法も変わってきますので、目的の設定は非常に重要なものとなり、細かく明確にしておく必要があります。
インベントリ分析
インベントリ分析では目的の設定に合わせ、対象となる製品の「製造段階」、「流通段階」、「廃棄・リサイクル段階」に分けられそれぞれ「水使用量・排水量及び水質汚染物質排出量」や「投入材料・エネルギーの製造、廃棄物の処理」などについて算出します。
例えば衣料品のウォーターフットプリントを調査する場合、原料となる繊維の栽培、加工に伴う水使用・廃棄量、流通にかかる軽油消費量、使用時のクリーニングにかかる水使用・廃棄量、廃棄処理にかかる水質汚染への影響などの要素を細かく評価する必要があります。
ウォーターインパクト評価
インベントリ分析での結果をもとに評価を行います。実施は次のような手順で行われます。
- 影響領域・影響カテゴリ指標と特性化モデルの選択
- 選択された影響領域への割り振り(分類化)
- 結果として得られたカテゴリ指標の計算(特性化)
- 参照情報に対する結果として得られたカテゴリ指標の強度計算(正規化)
- 影響領域の並べ替え・順位付け(グルーピング)
- 結果として得られた指標を換算し、影響領域にわたって集計(統合化)
- 結果として得られた指標の信頼性を理解する(データの品質分析)
こうして得られた結果を基に製品ごとの水環境に与える影響を判断していきます。影響評価は特定の手法を用いることが義務付けされているわけではなく、算定の目的や利用可能なデータに応じて評価者自身が適切な手法を選択する必要があります。
ここでの課題としては
- 影響評価結果の分かりやすさ
- 影響評価結果が民間事業者や消費者などの利用者にとって分かりやすいものであるかが重要で、厳密性を追求しすぎて利用者が理解できないものにならないように留意する必要があります。
- 水の地域性・季節性
- 水は地域や季節によって利用できる量が大きく異なります。評価にはこのような違いを正しく組み込む必要があります。
- 水質汚染物質が水利用可能量へ与える影響の評価
- 水質汚染物質が水環境へ与える影響は既存評価手法で表せますが、水利用可能量への影響を評価する手法はまだ開発が不十分となっています。
などがあげられています。
出典:環境省『ウォーターフットプリント算出事例集』(2014.8)
ウォーターフットプリントで分かったこと
WFN(Water Footprint Network)が公表している原単位をもとにWWFが算出した日本のウォーターフットプリントはテキスタイル(繊維)や畜産物の生産での比率が高いことが分かっています。
ブルーウォーターフットプリントでは「綿製品」、すなわち衣料品での消費が大きな環境負荷となっています。これは綿花を栽培するために使われる灌漑用水の影響です。日本が2018年に輸入した綿、羊毛、合成繊維の生産に伴うグリーンウォーターとブルーウォーターは5,384百万m3でした。
また、畜産物の生産においても飼料となる穀物の生産のため、大量のグリーンウォーターフットプリントが使用されています。日本の2018年に消費された輸入家畜製品の生産に伴うウォーターフットプリントはグリーンウォーターで14,739百万m3、ブルーウォーターで871百万m3となり、特に牛肉の生産分が56%と多くなっています。
出典:WWF『日本が世界の水環境に及ぼす影響を明らかにする「ウォーターフットプリント」』(2021.3.23)
まとめ:ウォーターフットプリントの活用で水リスクを見える化し、サステナブル経営へ
製品あたりのCO2消費量を評価する「カーボンフットプリント」という言葉は比較的耳にするようになり、少しづつ浸透してきている印象はありますが、同じように地球環境を考えるうえで水環境について考えることも大切なことです。
国が主導して取り組むことが重要となりますが、消費者の意識変革を促すうえでは企業の活動も大切な要素となります。ウォーターフットプリントについて理解を深め、持続可能な社会の実現に向けて水資源の健全化に取り組んでいきましょう。