2025年以降にスタートする環境法規制強化について、わかりやすく解説します。カーボンネットゼロ社会の実現に向けて、脱炭素化の潮流はますます加速しています。環境課題に関連する各種法規制も、どんどんハードルを上げていくことが予想されます。こうしたルール改正については、早めに情報をキャッチして備えておくことが重要です。それは、単なるコンプライアンス遵守ではなく、規制を味方につけた成長戦略にもなり得るのです。本記事では2025年以降の環境関連法改正、国際的なトレンド、LCA/CFPの重要性と企業における対策などについて取り上げます。アスエネが提供する環境課題ソリューションもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
INDEX
2025年の環境法規制:押さえるべき最新動向
環境関連の法改正や、ガイドライン改定の動向について解説します。
エコマーク認定基準におけるLCA/CFPの取り扱い
環境に配慮した商品であることを示すエコマークについて、2025年4月1日から製品系のエコマーク商品類型において、LCA または CFP の算定および開示を求める基準が、配慮事項として設定されています。すなわち、エコマークの認定要件ではないものの、製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること、算定はLCAまたはCFPによって行われていることが、エコマーク取得において望ましいことがエコマーク認定基準へ明記されました。これは需要家や消費者のニーズを捉えた情報提供の望ましい姿を、エコマーク事務局が検討してきた結果です。また今後、グリーン購入法の判断基準でLCAやCFPが必須基準として設定される品目は、エコマークにおいても必須基準に設定することが予定されています。
※LCAやCFPの詳細については、こちらやこちらの記事をご参照ください。
出典:公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局「定量的環境情報(CFP、LCA)の配慮事項への追加について(改定)」p1-2(2025/4/1)
資源有効利用促進法の一部改正
資源有効利用促進法(資源法)の改正施行令が2025年秋ごろに公布、2026年4月に施行される予定です。改正のポイントは、以下4点です。
・再生材の利用に関する計画の提出及び定期報告を求める
・特に優れた環境配慮設計の認定制度創設
・GXに必要な原材料等の再資源化の促進
・CE(サーキュラーエコノミー)コマース事業者が満たすべき基準を設定
この改正は、成長志向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しの一環で、どのような製品がこうした改正の対象になるのか注目されます。
出典:経済産業省「第11回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会 事務局資料」p3-5(2025/6/26)
その他、国内での製品環境規制の動き
日本国内では2025年、特に化学物質規制に動きが見られます。化学物質審査規制法において、1月にはPFOA関連物質、2月にはデクロランプラス、メトキシクロル及びUV-328が「第一種特定化学物質」に指定されました。さらに4月にはNPEが「第二種特定化学物質」として指定されています。また水銀汚染防止法においては、2024年12月改正で特定の電池や蛍光ランプ等の水銀添加製品が「特定水銀使用製品」に追加指定されています。
出典:経済産業省「化学物質管理政策をめぐる最近の動向」p3(2025/3/10)
世界の製品環境規制トレンドと日本企業の課題
海外でも、さまざまな製品に対して環境規制が強化されています。
欧州:CBAM、欧州電池規則、エコデザイン規則など
欧州ではCBAMによって、EU域外で生産された製品への炭素課金を準備中です。EU域外から対象品を輸入する事業者は近い将来、製品の排出量に応じたCBAM証明書を購入しなければならなくなりますので、よりCFPが低い製品の流通促進が予想されます。また欧州電池規則も、CFP情報開示義務化や閾値規制等によって、欧州域外からのバッテリー流入を制限することになると予想されます。さらにEUのエコデザイン規則では、主要な製品を対象に、CFP等の情報開示や持続可能性に関する要件を定めており、規制対応コストが域外企業にとって参入障壁となる可能性が大きいと考えられます。
出典:経済産業省「GX実現に向けたカーボンフットプリント活⽤に関する研究会(第1回)p22-25(2025/2/28)
アジア諸国:各国の動向と日本への影響
日系企業の多いアジア諸国にも、さまざまな環境規制が存在します。まとめると下表のとおりで、〇:該当制度あり、△:草案段階、×:該当制度なしを表しています。
| 建物・工場省エネ規制 | GHG排出量報告制度 | 国内排出量取引 | 炭素税制度 | |
| 韓国 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| インドネシア | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 台湾 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| シンガポール | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| タイ | 〇 | △ | △ | △ |
| インド | 〇 | 〇 | △ | × |
| ベトナム | 〇 | △ | △ | × |
| フィリピン | 〇 | △ | △ | × |
| マレーシア | △ | △ | △ | × |
各国の環境規制は、日系企業に対する直接的な影響に留まらず、海外サプライヤーと取引を行う国内企業にとっても、サプライチェーンの不安定化や不必要な取引コストの増加などのサプライチェーンリスクとして、重大な影響を及ぼす可能性があります。
出典:環境省「アジア各国の環境規制に関する最新動向」p1,3
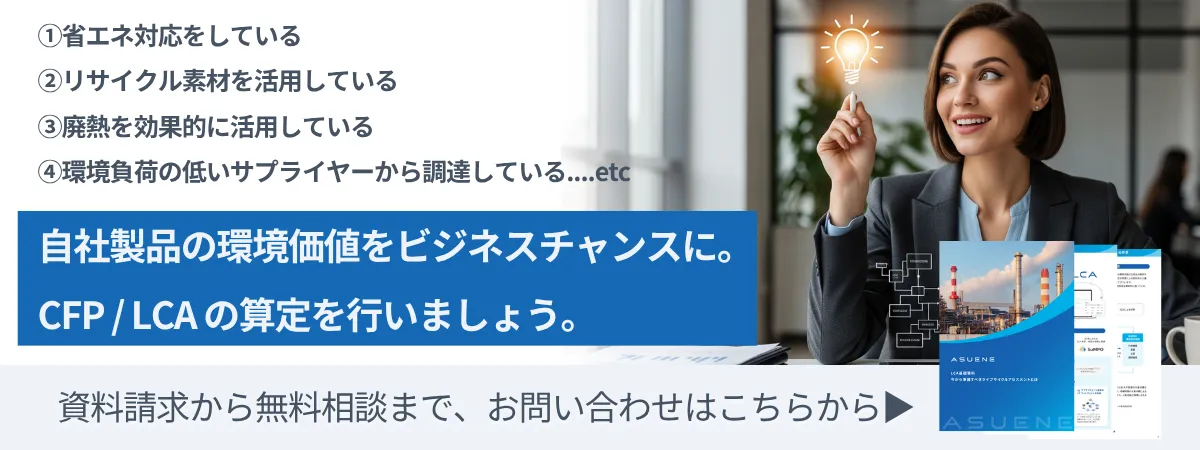
世界の製品環境規制トレンドと日本企業の課題
海外でも、さまざまな製品に対して環境規制が強化されています。
欧州:CBAM、欧州電池規則、エコデザイン規則など
欧州ではCBAMによって、EU域外で生産された製品への炭素課金を準備中です。EU域外から対象品を輸入する事業者は近い将来、製品の排出量に応じたCBAM証明書を購入しなければならなくなりますので、よりCFPが低い製品の流通促進が予想されます。また欧州電池規則も、CFP情報開示義務化や閾値規制等によって、欧州域外からのバッテリー流入を制限することになると予想されます。さらにEUのエコデザイン規則では、主要な製品を対象に、CFP等の情報開示や持続可能性に関する要件を定めており、規制対応コストが域外企業にとって参入障壁となる可能性が大きいと考えられます。
出典:経済産業省「GX実現に向けたカーボンフットプリント活⽤に関する研究会(第1回)p22-25(2025/2/28)
アジア諸国:各国の動向と日本への影響
日系企業の多いアジア諸国にも、さまざまな環境規制が存在します。まとめると下表のとおりで、〇:該当制度あり、△:草案段階、×:該当制度なしを表しています。
| 建物・工場省エネ規制 | GHG排出量報告制度 | 国内排出量取引 | 炭素税制度 | |
| 韓国 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| インドネシア | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 台湾 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| シンガポール | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| タイ | 〇 | △ | △ | △ |
| インド | 〇 | 〇 | △ | × |
| ベトナム | 〇 | △ | △ | × |
| フィリピン | 〇 | △ | △ | × |
| マレーシア | △ | △ | △ | × |
各国の環境規制は、日系企業に対する直接的な影響に留まらず、海外サプライヤーと取引を行う国内企業にとっても、サプライチェーンの不安定化や不必要な取引コストの増加などのサプライチェーンリスクとして、重大な影響を及ぼす可能性があります。
出典:環境省「アジア各国の環境規制に関する最新動向」p1,3
LCAとCFPが義務化される背景とは
各種環境規制の中で最近注目されているのが、LCA/CFPです。その理由について解説します。
製品ライフサイクル全体の環境負荷低減の必要性
CFPに取り組んだ企業は、製品のライフサイクルの各段階におけるGHG排出量データを元にして、排出量が多いポイントを理解して効果的な排出削減対策を検討したり、排出削減の効果をモニタリングすることができます。またCFPの表示が消費者に対する気候変動問題に関する関⼼の啓発に繋がったり、政府や企業におけるグリーン調達においてCFPの低い製品を優先的に選択することで、環境負荷の低減につながります。ただしCFPの算定と削減に取り組む⼀⽅で、そのために気候変動以外の環境影響評価に悪影響を及ぼすようなことがあってはなりません。LCA を⾏うことを通じて、総合的な環境影響の評価・対策にも目を向けることが必要です。このようにCFP を⼊り⼝として LCA に取り組むことで、気候変動以外の環境問題への対応⼒向上も期待されます。
出典:経済産業省「カーボンフットプリント ガイドライン」p7(2023/5)
グリーンウォッシング対策としての透明性確保
グリーンウォッシュとは、企業が自身のビジネスモデルや活動、商品について、実際には環境に害を与える可能性があるにもかかわらず、環境に対する影響がないかのように示すことを言い、消費者や投資家などが環境に配慮されていると信じて、適切な選択肢を選べず、結果的に環境問題が深刻化してしまうリスクをもたらします。これに対し世界各国では、「グリーンクレーム指令(EU)」「グリーンガイド(米国)」「グリーンクレームコード(英国)」など、法規制を強化しています。グリーンウォッシュとみなされないために、CFPの表示ガイドについてもグリーンウオッシュ規制など世界の最新の動向に準拠することや、SBTiや、RE100など国際イニシアティブに承認される内容であることが求められます。適切なCFP算定と表示をすることによって透明性を確保し、グリーンウォッシュではないと理解を得ることができます。
出典:環境省「CFP表示ガイドの作成に向けて国際的なグリーンウォッシュ規制の動向」p4,6,13(2024/10/25)
企業の競争力維持と新たな市場機会
近年の気候変動問題への関⼼の⾼まりを踏まえ、企業のさまざまなステークホルダーがCFPを企業に要請し始めており、CFPは企業の競争⼒を左右するものになりつつあります。CFPが求められる理由としては、以下のようなものが挙げられます。
・CFPを活⽤した公共調達
・CFPを活⽤した規制
・ESG投資におけるサプライチェーン排出量の把握・開⽰要求
・顧客のグリーン調達
・顧客のサプライヤーエンゲージメント
・消費者へ向けた脱炭素に関する企業ブランディング、製品マーケティング
こうしたCFP対応は一定の負担を伴いますが、同時に新たな市場機会も生み出します。こうした社会状況も、LCA/CFP義務化の背景として存在しています。
出典:経済産業省「カーボンフットプリント ガイドライン」p7-8(2023/5)
企業が今すぐ始めるべき環境対応ロードマップ
環境関連の法規制に対し、企業はどのように対応する必要があるでしょうか。その対策とロードマップについて解説します。
法改正情報の継続的なキャッチアップ
環境関連の法改正情報は、継続的にキャッチアップしましょう。たとえば環境省のホームページでは、環境に関連する法令・告示・通達が「総合目次」から環境技術・環境影響評価・自然保護・公害・費用負担・化学物質・廃棄物とリサイクル・悪臭・地盤沈下・振動・騒音・土壌と農薬・水質保全・大気保全・地球環境・行政組織・環境基本などカテゴリー別に調べられるようになっており、改正が公布されるとタイムリーに反映されます。
自社製品のLCA/CFP算定の先行実施
まずは自社製品のLCA/CFPを簡易な方法でもよいので算定してみると、具体的なイメージが掴めるようになります。そのためには、利害関係者を募っての製品別算定ルールの策定はせず、自社ルールで算定することが推奨されます。また必要十分な精度を心掛け、複雑になり過ぎないように留意することも必要でしょう。算定に必要なデータは1次データ(実測値、実測値の配分)を取得することが基本ですが、取得が困難な場合には、シナリオ(活動量の把握が難しいプロセスに対して設定する仮定)も使用します。
出典:経済産業省「カーボンフットプリント ガイドライン(別冊)CFP 実践ガイド」p8(2023/5)
サプライチェーンとの連携強化とデータ共有体制構築
CFP算定にあたっては、自社と取引先が取組の意義や必要性を理解し協力して取組を行う必要があります。他方で、サプライチェーン上の企業の中には、脱炭素に向けた具体的な取組が進められていない、あるいは、そもそも自社の排出量算定の必要性を認識していないという企業が存在しています。このため、取引先に対する意識醸成を進めるとともに、取引先とのデータ連携を進める際の秘匿性・データ管理方法等の様々な働きかけも必要です。排出量算定に関するデータ共有体制の構築に成功すれば、その後の段取りがスムーズです。
出典:環境省「バリューチェーン全体の脱炭素化に向けたエンゲージメント実践ガイド」p1-2(2025/3)
専門家やLCAツールの活用
LCAは設定した仮定や前提条件で算定結果が変わってくるので、妥当性について専門家によるレビューを受ける必要があります。専門家は内部・外部いずれもあり得ますが、必要な科 学的及び技術的な専門知識を持っていなければいけません。企業としてはこうした専門家へ早い段階からコンタクトして、アドバイスを受けるとよいでしょう。また、LCA算定には専用のツールを活用することが、一番の近道です。LCAツールとしては、たとえば建築分野で使われている「建物のLCAツール」などが知られています。専門家の助言を受けながら、自社事業に合ったLCAツールを選定するとよいでしょう。
出典:経済産業省「ライフサイクルアセスメント」p127(2004/1)
出典:国土交通省「やさしいBIMを用いた発注者によるライフサイクルアセスメント業務の効率化検証成果報告会」p5(2023/7/25)
アスエネのLCA/CFP算定ソリューションで法規制をクリア
最後に、中小企業でも導入価値の高いソリューション「ASUENE LCA」についてご紹介します。
最新の規制動向を反映した算定機能
ASUENE LCAは、脱炭素ソリューション 導入社数No.1(※東京商工リサーチ調べ/2024年10月調査時点)のASUENEと、30年にわたるLCA算定・検証の実績を有するSuMPOが共同開発したCFP / LCA算定サービスで、初心者でも簡単に、最短1分でCFP/LCAの算定・分析・報告書作成が可能です。最新の規制動向が常に反映されますので、企業側で法改正に合わせて算定ロジックを変更したり、データを入れ替えるなどの作業は一切不要です。
各種報告形式への対応
CFP/LCAの算定結果はボタン一つで出力できます。SuMPO監修のフォーマットで、各種報告形式への対応もスムーズです。本記事でも取り上げたEUのBAMや電池規則はもちろん、取引先への排出量データ報告なども全てシームレスに行えます。CFPやLCAの報告先が多岐にわたる場合でも、ASUENE LCAさえ導入していれば、全部対応可能です。
専門家による導入・運用サポート
ASUENEは環境課題の専門家集団であり、ASUENE LCAの導入からその運用までを完璧にサポートします。中小企業から大企業まで、さまざまな企業規模や業種において導入実績がありますので、クライアント環境課題に関するあらゆるニーズに応えることが可能です。
まとめ:LCA/CFP算定に先行投資し環境規制をチャンスに変えましょう
国内外で、環境関連の法規制やガイドラインがどんどん強化されています。これらの変化をただ後追いするだけでは、環境課題対応への負担感ばかりが募ってしまうでしょう。重要なのは、変化の波を乗りこなして、持続可能な企業として競争優位性を確立することです。
そのためには、記事中でも触れましたが、専門家へ相談することが有効です。ASUENEのCFP算定、LCA支援をはじめ、CO2削減コンサルティングなどを通じて、競合との差別化を図りましょう。













































































































