企業の再生エネルギー導入方法について、わかりやすく解説します。脱炭素社会の実現に向け、世界中で再生可能エネルギーの導入気運が高まっています。企業においても、事業活動で消費するエネルギーを再生可能エネルギーに切り替えていくことを、投資家や消費者からますます求められるようになっていくでしょう。とは言え「再生可能エネルギーの導入なんて、莫大な設備投資が必用なのでは?」と、逡巡する声も多く聞かれます。本記事では再生可能エネルギーの調達方法、再生可能エネルギーに関する補助金や優遇税制、具体的な導入事例などを取り上げます。
INDEX
再生可能エネルギー導入のメリット、企業価値向上からサプライチェーン強化まで
再生可能エネルギーとは、自然環境を活かしたエネルギーです。その導入メリットについて解説します。
再生可能エネルギーの概要
再生可能エネルギーとは、「エネルギー供給構造高度化法」において「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」と定義されており、具体的には太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存する熱・バイオマスが該当します。これらのエネルギー源は温室効果ガスを排出しないだけでなく、国内で生産できることからエネルギー安全保障にも寄与します。
企業が再生可能エネルギーを導入するメリット
再生可能エネルギーには先述の通り環境課題の解決やエネルギー自給といった社会的意義だけでなく、導入した企業に次のようなメリットをもたらします。
・機関投資家や金融機関によるESG投資の進展にともなう、企業価値向上
・サプライチェーン全体での脱炭素化の取組にともなう、バイヤー企業からの要請への対応
サプライヤーとなることが多い中小企業にとっても再生可能エネルギー導入は、新たな事業機会獲得や競争力強化につながると言えるでしょう。
出典:環境省「はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)」p5(2022/3)
再生可能エネルギー、どうやって導入する? 企業の調達方法を徹底解説
再生可能エネルギーを導入するには、いくつかの選択肢が存在します。再生可能エネルギーの調達方法について解説します。
敷地内での太陽光発電の導入
まず考えられるのは、企業が所有または借用する敷地内で太陽光発電設備を設置し、そこから電力を調達する手法です。具体的には太陽光発電設備を、建物屋根へ設置するケースが多く見られます。太陽光発電設備は、購入・リース・発電業者による設置(オンサイトPPA)などの調達方法があります。取り組みの「追加性」によって脱炭素化の訴求効果が期待できる一方、屋根のスペースが限られる場合は十分な電力が得られないことがあります。
出典:環境省「はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)」p10(2022/3)
敷地外での太陽光発電の導入
企業が再生可能エネルギー電力を調達したい事業所の敷地外に太陽光発電設備を設置し、そこから送電することで電力を調達する手法もあります。企業専用の「自営線」を用いるケース、一般送配電事業者の送配電網を利用する「自己託送方式」、発電事業者が敷地外に設置・供給する「オフサイトPPA」などの調達方法があります。敷地内導入同様取り組みの「追加性」による遡及効果があり、企業が脱炭素化を中長期的に継続していく上で高い効果が期待できますが、調達コストが高くなる傾向があります。
出典:環境省「はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)」p10(2022/3)
再生可能エネルギー電力の購入
設備投資をせずに再生可能エネルギー電力を調達する方法として、再生可能エネルギーを購入するという手法があります。具体的には現在の電力契約を、小売電気事業者が提供する「再エネ電力メニュー」に切り替えることによって導入が完了します。現時点においては、最も簡易かつ安価に再生可能エネルギー電力が調達できる手法と言えるでしょう。購入による再生可能エネルギーの導入には、企業の脱炭素化実現に向けて短期的な貢献が期待できます。
出典:環境省「はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)」p10(2022/3)
再生可能エネルギー電力証書の購入
電力そのものではなく、再生可能エネルギーの環境価値(環境への貢献度合い)を購入するという方法もあります。具体的には、J‐クレジット・グリーン電力証書・非化石証書などの「再生可能エネルギー証書」を購入することで、再生可能エネルギーを導入したものとみなされます。再生可能エネルギー電力の購入と同様、簡易・安価な調達方法であり、再生可能エネルギー電力の購入と組み合わせて採用されるケースも多く見られます。出典:環境省「はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)」p10(2022/3)
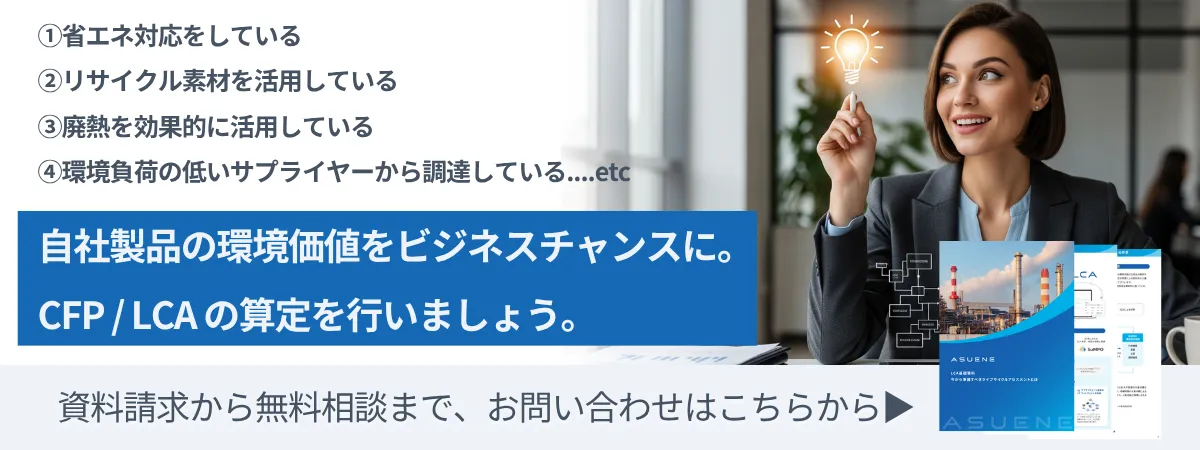
最大2億円の補助金も! 企業が再エネ導入で活用できる「お得な制度」まとめ
再生可能エネルギーの導入にあたっては、行政による支援も行われています。再生可能エネルギーに関する優遇税制や補助金について解説します。
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
再生可能エネルギー発電設備を取得した事業者については、再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税を軽減する措置があります。対象となる設備は太陽光発電設備、風力発電設備、中小水力発電設備、バイオマス発電設備(2万kW未満)、地熱発電設備で、このうち太陽光発電設備はFIP・FIT制度(再エネ電力の買取・補助)の認定を受けたもの以外、太陽光発電設備以外は同制度の認定を受けたものが対象となります。具体的な軽減内容は、固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の固定資産税の課税標準(税金の算定基準)が、設備種類や発電出力に応じ最大1/3にまで圧縮されるというものです。
出典:資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー> 各種支援制度> 税制」
環境・エネルギー対策資金
環境・エネルギー対策資金(非化石エネルギー設備関連)は、中小企業や個人事業主が、非化石エネルギー設備(再生可能エネルギー設備)を取得・改造・更新するために必要な資金を融資する制度です。貸付期間は20年以内、貸付限度額は中小企業事業:7億2千万円以内・個人事業主等:7千2百万円以内となっています。利率は5年以内貸付の場合、設備種類によって中小企業0.65~1.9%、個人事業主等1.25~1.9%です。窓口は日本政策金融公庫で、フリーダイヤル(0120-154-505)で相談が可能です。
出典:資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー> 各種支援制度> 融資」
地方自治体の補助金や助成金例
国以外にも、多くの地方自治体が再生可能エネルギー導入を支援しています。たとえば東京都は、都内に地産地消型再生可能エネルギー発電等設備又は再生可能エネルギー熱利用設備、蓄電池単独設置を設置する事業者に対して、当該設備の設置に係る経費の一部を助成する「地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業
(都内設置・蓄電池単独設置)」制度を設けており、たとえば中小企業が再生エネルギー発電設備を導入する場合、費用の2/3以内・上限2億円まで助成の対象となります(申請は令和8年まで)。
また埼玉県では、埼玉県内にある事業所に省エネ・再エネ活用設備を導入する者に対し企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金を、予算の範囲内で交付しています。太陽光発電設備の場合補助対象経費(補助対象設備の工事費、設備費、業務費)の1/3が補助率となっており、上限額は1,500万円です。※令和7年度については7/18で申請が締め切られています。
企業規模で選べる! 再生可能エネルギー導入の成功事例3選
多くの企業が、再生可能エネルギーを導入しています。具体的な事例をご紹介します。
株式会社ベルク
埼玉や北関東でスーパーマーケットチェーンを展開する株式会社ベルクは、栃木県のベルク佐野田沼店において、スーパーマーケットの屋上に非常時にも活用可能な太陽光発電を、購入方式にて設置しました。平常時の温室効果ガス排出抑制だけでなく、災害などの際に地域の人々に対して非常用コンセントを提供することなども目的に導入したものです。全17台のパワーコンディショナに自立運転機能を有する機器を導入し、停電時においても日中であればパワーコンディショナ1台当たり6kWの非常用電源を確保することが可能となっており、施設全体の日中の再生可能エネルギー比率約23%を達成しています。
出典:環境省「はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)」p13(2022/3)
株式会社加藤えのき
宮崎県にえのき生産工場を持つ株式会社加藤えのきは、オンサイトPPA方式を活用して工場の屋根へ太陽光発電設備を導入しています。検討にあたっては、初期投資なしで設置できることが採用の決め手となりました。具体的にはPPA事業者である長州産業株式会社が工場に太陽光発電設備を設置して電力を供給し、株式会社加藤えのきは、長州産業株式会社にエネルギーサービス料を支払っています。本取り組みにより日中の電力購入量が減り、施設全体の再生可能エネルギー比率8.7%を達成しました。
出典:環境省「はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)」p19(2022/3)
大昭和紙工産業株式会社
全国各地に工場や営業所を持つ大昭和紙工産業株式会社は、J-クレジットを活用して再エネ調達100%に向けた取り組みを開始しています。具体的には国内の全9営業所における年間のエネルギー消費量と同量の再生可能エネルギー由来のJ-クレジットを、宮城県内の一般家庭住宅の太陽光発電設備から調達しカーボン・オフセット(自社排出量の相殺)に活用しています。これは気候変動対策と同時にと東日本大震災の被災地支援も目的としており、J-クレジットの調達量は電力消費量約242,000kWh分、CO2削減量に換算すると110t-CO2に相当します。
出典:環境省「はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)」p36(2022/3)
まとめ:再エネ導入の鍵を握る「見える化」アスエネとNZeroが描く未来
再生可能エネルギーの導入には、設備投資なしで簡易的に始められる方法から、補助金などを活用して本格的に取り組む方法まで、様々な選択肢があります。大企業だけでなく、中小企業も自社の状況に合った手法を検討することで、カーボンニュートラルへの貢献と企業価値の向上を同時に目指すことが十分可能です。
こうした取り組みをより効率的に進める上で、重要な鍵となるのが「CO2排出量の正確な把握と見える化」です。自社の排出量を正確に知ることで、最適な再エネ導入計画を立てることができます。
この課題を解決するための一つのツールが、アスエネのクラウドサービスです。アスエネは、企業のCO2排出量をサプライチェーン全体で可視化し、削減・報告までをワンストップで支援します。
さらに先日、アスエネは米国企業NZeroの全株式を取得し完全子会社化しました。今回の全株式取得により、当社は米国企業におけるCO2排出量の見える化と削減施策の実行を加速させます。当社が有するアジアNo.1のCO2排出量見える化事業の実績と、米国州政府の導入実績がトップクラスであるNZeroの、AI活用エネルギーマネジメントシステムのテクノロジーを融合させることで、世界トップクラスの脱炭素プラットフォームを構築してまいります。













































































































