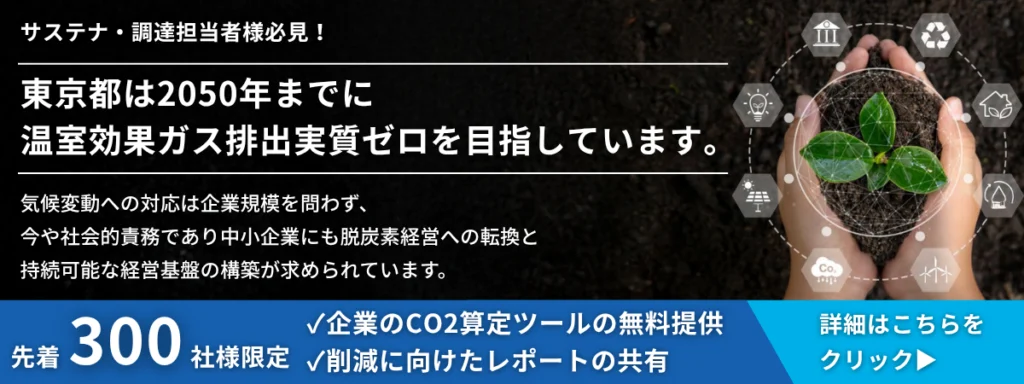資源回収再利用における法律改正について、わかりやすく解説します。資源有効利用促進法の元となる法律は30年以上前に制定されたものですが、その後何度か改定を経て現在に至っています。日本政府が推進する「3R政策」の柱となる法律ですが、昨今のサーキュラーエコノミーの流れがここにも見られます。限りある資源を持続可能な形で利用するために、消費者や企業はどのように取り組む必要があるでしょうか。本記事では資源有効利用促進法の概要とポイント、資源有効利用の将来展望などについて取り上げます。
INDEX
GX実現の鍵を握る「資源有効利用促進法」改正で変わる企業の取り組み
資源有効利用促進法は、循環型社会システムの構築を促す法律です。
資源有効利用促進法の概要
資源有効利用促進法は、正式には「資源の有効な利用の促進に関する法律」と言い、平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」を一部改正し平成13年4月に施行されました。この法律は以下3つの観点で、循環型経済システムの構築を目指しています。
(1)事業者による製品の回収・再利用の実施などリサイクル対策を強化
(2)製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)
(3)回収した製品からの部品などの再使用(リユース)のための対策
出典:経済産業省「3R政策」
資源有効利用促進法改正の背景
資源有効利用促進法は、2025年5月28日に参議院で改正案が可決されました。同時に「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」も改正されており、議案全体として2050年カーボンニュートラルと経済成長の両立(GX)を実現するため、成長志向型カーボンプライシング構想の具体化と、サーキュラーエコノミーの実現に向けた制度の基盤を整備を企図しています。
資源有効利用促進法の一部改定は、主に特定の製品を扱う製造業者や、関連事業を行う企業を対象としています。脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行を推進するため資源循環強化のための制度を新設することが目的となっており、さらにGXの観点も盛り込まれています。
出典:環境省「「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について」(2025/2/25)
出典:参議院「議案情報」(2025/6/4)
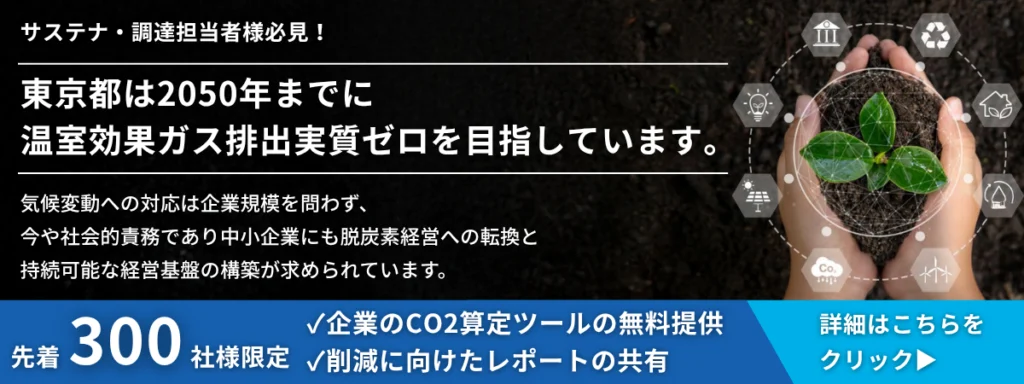
製造業はどう変わる?「資源有効利用促進法」改正のポイントと影響
資源有効利用促進法の一部改定には、4つのポイントがあります。それぞれについて解説します。
再生資源の利用義務化
今回の改定によって、再生材の利用義務を課す製品が特定され、当該製品の製造事業者等に対して再生材の利用に関する計画の提出及び定期報告が義務付けられました。これは再生資源の利用をモニタリングする仕組みを構築し、必要に応じて再生資源利用の改善を促していくことが目的です。
対象となる製品はこれから政令で定められますが、「再生材の利用によるCO2削減効果が大きいこと」「市場に任せていては再生材が利用されないこと」などが指定要件となっています。対象製品の候補としては容器包装(食品や医薬品以外)、家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)、自動車などが挙げられています。
出典:経済産業省「第11回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会 資料3」p7,10-11(2025/6/26)
環境配慮設計の促進
特に優れた環境配慮設計(解体・分別しやすい設計、長寿命化につながる設計)の認定制度創設と認定事業者に対する特例措置が、今回の改定で定められました。従来も環境配慮設計を進めるべき製品50品目が指定されていましたが、環境配慮設計が特に優れた製品を積極的に評価し、全体レベルを底上げする仕組みはありませんでした。このため、特に優れた環境配慮設計(資源有効利用・脱炭素化促進設計)を認定し、認定を受けた製品については以下のような扱いが予定されています。
・国による公表と周知
・差別化できる製品表示
・グリーン購入法における国の調達の基本方針における配慮
・関連設備投資への産廃処理施設整備法の指定法人による債務保証
具体的な認定基準は、今後製品分野ごとに策定されます。
出典:経済産業省「第11回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会 資料3」p17-18(2025/6/26)
GXに必要な原材料等の再資源化の促進
今回の改定によって、高い回収目標等を掲げて認定を受けたメーカーなどに対し廃棄物処理法の特例が新たに設けられました。現制度でも、小型リチウム蓄電池やその使用製品のメーカーなどには、リチウム蓄電池の回収・再資源化が義務付けられています。しかしながら回収再資源化の実施状況をモニタリングする仕組みとなっておらず、また広域回収には個別の自治体許可が必要であったり、さらにはリチウム蓄電池を取り外せない一体型製品が増加したことなどによって、回収率は低いのが現状です。そこで自主回収計画を申請し認定を受けたメーカーなどは業許可不要とすることで回収を促進し、一体型製品も政令で義務の対象に追加予定です。
alt属性:GXに必要な原材料等の再資源化の促進
出典:経済産業省「第11回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会 資料3」p25-27(2025/6/26)
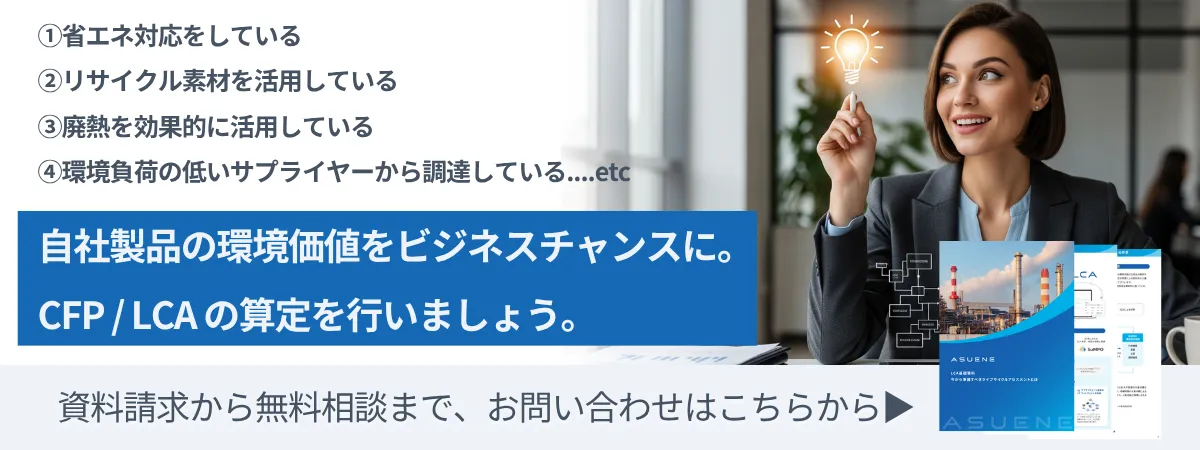
CE(サーキュラーエコノミー)コマースの促進
CEコマースとは、シェアリング、リユースなど資源の有効利用につながる新たなビジネスのことです。このCEコマースを健全に育成する適切な規律が存在していなかったことから、今回の改定でCEコマース事業者に対し、資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定することとなりました。たとえば中古製品の修理歴や使用状態などの重要情報が消費者に適切に開示されず、製品事故が発生するケースなどは、不適切なCEコマースに該当します。CEコマースの対象製品は今後選定されますが、BtoC分野では家電4品目や衣料品が候補として挙げられています。
出典:経済産業省「第11回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会 資料3」p32-36(2025/6/26)
なぜ今、資源有効利用促進法が改正されたのか?欧州のサーキュラーエコノミー潮流と日本の戦略
資源有効利用促進法の改定によって、資源のさらなる回収再利用などが期待されます。
政府による検討
改正資源法の円滑な制度開始に向けて、政府の資源循環経済小委員会では、製品指定の考え方を踏まえた具体的な指定製品の決定、制度の点検・見直しの実施を、また小委員会の下部にあるワーキンググループでは、各業界へのヒアリング等を実施しその結果を小委員会へ報告することを、それぞれ予定しています。また環境配慮設計の設計指針やCEコマース事業者の判断基準等についても、それぞれの下部ワーキンググループで検討されることとなります。
出典:経済産業省「第11回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会 資料3」p47(2025/6/26)
欧州を中心としたサーキュラーエコノミーの潮流
資源の有効利用促進は日本国内だけではなく、特に欧州を中心としたサーキュラーエコノミーの潮流が世界各国で広まっています。欧州委員会は2022年3月30日、「持続可能な製品を規準とし、欧州の資源独立性を高めるための新提案」として、エネルギーや資源依存から脱却し、外的影響に対してより強靱な循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行に向けた取組強化のための一連の措置を提案しました。その中ではメンテナンスやリユース、リサイクル、改装、修理、中古品販売市場の活性化も取り上げられています。欧州の産業政策は、目標設定→規制→市場ルール化による製品・市場の囲い込みという「勝ちパターン」を踏襲することが多く、CE関連政策においても将来的な製品市場のアクセス要件化が予想されます。
出典:経済産業省「資源循環経済政策の現状と課題について」p46,56(2023/9)
なぜ企業はサーキュラーエコノミーに取り組むべきなのか?競争力を高める4つの段階
サーキュラーエコノミーでは、従来の3R(リデュース、リユース、リサイクル)の取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化などを通じて付加価値を生み出す経済活動が求められます。各企業は、自ら提供する製品・サービスに一層の循環性を備えるべく、技術やビジネスモデルのイノベーション創出に向けた取組を進めることが必要です。サーキュラー・エコノミーへの移行は、企業の事業活動の持続可能性を高めるとともに、中長期的な競争力の源泉となりえます。
具体的な取り組みとしては、以下のようなものが挙げられるでしょう。
| 設計段階 | ・リデュース設計(希少金属の削減や軽量化など)やリユース・リサイクルに適した設計(易解体設計やモノマテリアル化など) ・再生材、再生可能資源由来素材などの環境配慮素材の積極利用 |
| 生産段階 | ・生産工程の最適化による生産ロスの削減や端材・副産物の再生利用・ 需要に応じた供給を徹底することによる販売ロスの削減 |
| 利用段階 | ・シェアリング等を活用した遊休資産の有効活用・ 中古品のリユースやカスケード利用 |
| 廃棄段階 | ・製品自主回収等を通じたリサイクルの推進・ 産業廃棄物の削減・リサイクルの徹底 |
出典:環境省「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」p1,18,52(2021/1)
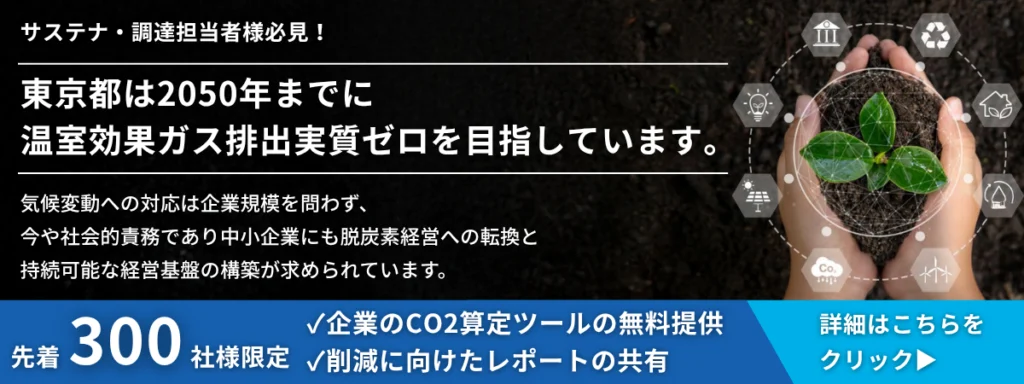
ユニクロ、三井化学、エフピコに学ぶサーキュラーエコノミーの実現戦略
ユニクロ
株式会社ファーストリテイリングの中核事業であるユニクロは、生産数量の予測精度の改善や物流改革などにより、顧客が求める商品を最適なタイミングで届けることで、生産や販売における無駄をなくす取り組みを進めています。さらに一部売れ残った商品は、値下げや翌期以降に持ち越すことで売り切り、廃棄を発生させない販売戦略をとっています。また販売後の商品についても、顧客から着なくなった服を回収・リサイクルする活動を行っています。店舗で回収した服は、難民キャンプや被災地への緊急災害支援など、世界中の服を必要としている人々に届けることでリユースを行い、リユースできない服は、燃料や防音材として加工してリサイクルしています。このような取組は、限られた資源を効率的に使用するという観点から社会のサステナビリティ向上に貢献しています。
出典:環境省「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」p20(2021/1)
三井化学株式会社
三井化学グループでは、プラスチック事業に再生材量を取り込んでいく方針です。廃プラスチックのリサイクル手法やリサイクルしやすい包装材料の開発に加え、廃プラスチック削減に貢献するスタートアップ企業の支援なども行っています。またCO2を吸収し成長した植物を原料とするバイオマスプラスチック製品群の拡充を図り、独自の発酵技術を用いた世界初のバイオポリプロピレン製造技術の確立・実用化を目指しています。バイオマス原料への転換は、資源循環を促進すると考えられています。さらに海洋プラスチックごみ問題についても、国内外のアライアンスに参画し、プラスチック資源循環のバリューチェーン一体としての対策を進めています。
出典:環境省「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」p36(2021/1)
株式会社エフピコ
株式会社エフピコでは、1992 年に環境対応の「エコトレー」(発泡トレー)の販売、2007年には透明容器の回収を開始し、2012 年には使用済み PET ボトルをリサイクルした素材として製品化した「エコAPET」(透明容器)を発売するなど、使用済み製品やPETボトルを製品の素材として調達する環境負荷低減のシステムを構築しています。さらに自社物流を展開しているため、製品配送後の空のトラックで使用済み容器を回収することで循環の輪を回す原動力としています。同社ではライフスタイルの変化に伴うニーズの多様化に対応していくため、バリューチェーンを構成する調達・製品開発・製造・物流・販売・リサイクルの 6 つの部門がそれぞれにアイデアを出し合い、それを製品開発部門が形にするという作業を継続しています。
出典:環境省「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」p39(2021/1)
まとめ:資源有効利用促進法改正はGXへのチャンス?企業が今、取り組むべきこと
資源有効利用促進法の改正によって、今後資源循環に資する各企業の取り組みが一層進展することが期待されます。資源の有効利用については過去からさまざまな検討や取り組みが行われてきましたが、現在では3Rの枠を超えたサーキュラーエコノミーの実践が求められており、ビジネスモデルやプロセスの見直しが重要になってくるでしょう。その意味では今回の改定は単なる法律改定ではなく、GXに向けたチャンスの到来ととらえることができるかも知れません。
サーキュラーエコノミーの一環として資源回収・再利用を促進し、循環型社会の実現に貢献しましょう。