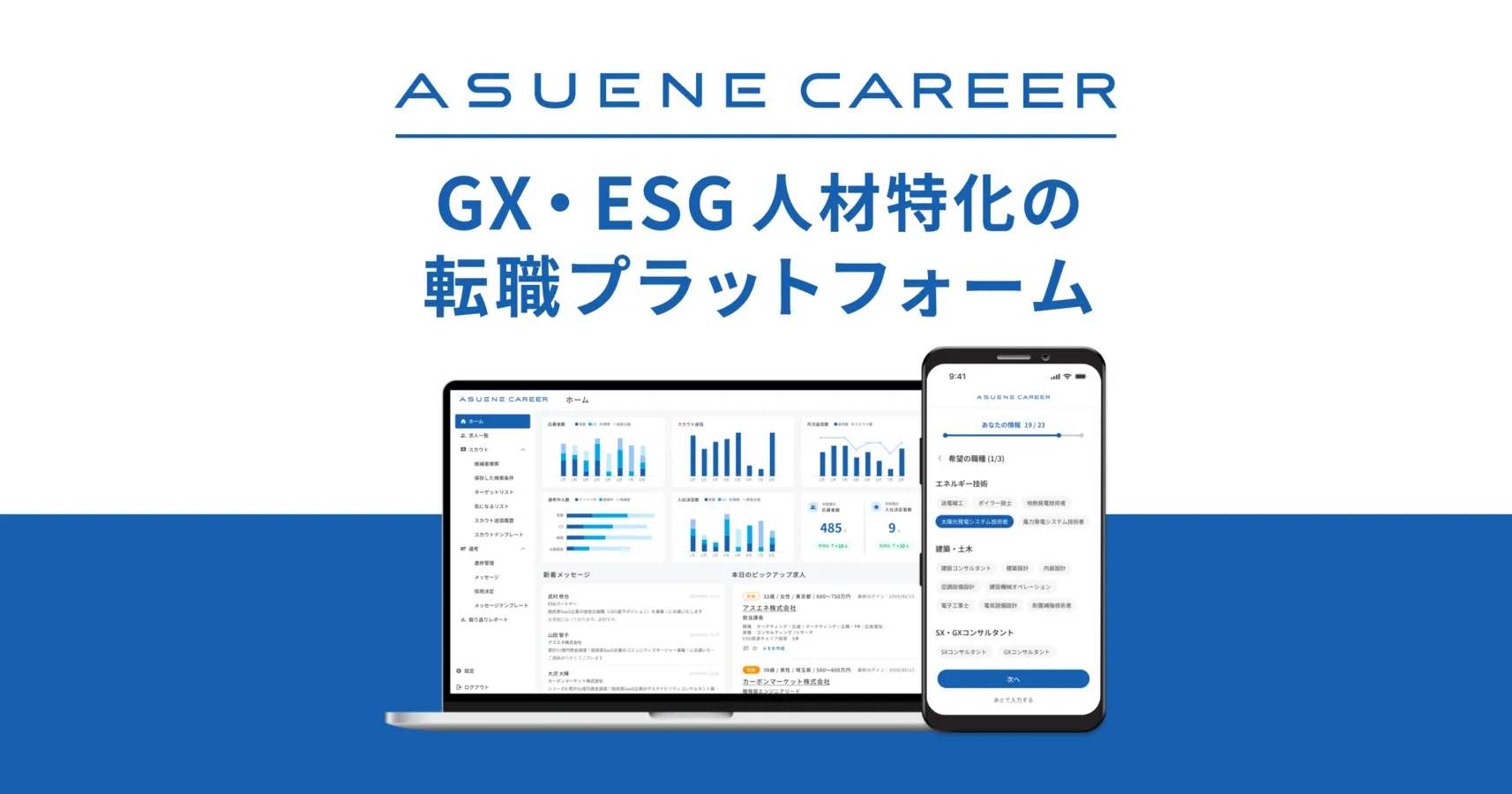戦後から廃棄物処理業を行い、今年で創業75年目を迎える老舗企業の新井紙材。気候変動という社会課題に対し、従来の「回収・処分」から一歩進み、「リサイクル・資源化」による循環型社会の構築を目指しています。新たに手掛ける「資源循環サービス」について、新井紙材株式会社 資源循環事業部長 小野寺 誠氏に、インタビューしました。

新井紙材の「資源循環サービス」とは?
新井紙材は、戦後の不況の最中に古紙の回収・リサイクルを行う会社として創業し、75年の歴史がある会社です。メインエリアを関東圏として、オフィスや印刷・製本会社、物流倉庫から、機密書類や段ボールなどの古紙を回収してきました。当社は、古紙を回収し、資源化することを得意としてきました。
ペーパーレスやDX化に伴い、古紙の発生量は2007年をピークに右肩下がりで、古紙回収の市場規模は縮小しています。そこで、当社は、廃棄物処理の許可証を取得し、廃棄処理の取り扱い範囲を拡大しました。現在は古紙に限らず、プラスチックや金属など、幅広い廃棄物の回収とリサイクルを行っています。
昨今は、SDGsへの貢献が企業価値を左右する時代です。事業活動に伴う「廃棄物」への対応は、スコープ3のカテゴリ5,12にも当てはまり、企業の環境保全へのアクションとして最重要課題の一つであると言えます。しかし、品目毎の様々な処理方法や地域ごとに異なる煩雑な業者選定は、多くのお客さまの悩みの種となっています。大手企業も廃棄物のリサイクルや資源循環への課題感はありつつも、複数の素材が複雑に絡み合った廃棄物は管理業務が多く、資源を有効活用するリサイクルまで実行に移せていないのが現状です。そのため、廃棄物の中に、まだ再利用できる資源が残っているにも関わらず、単に焼却処理されるだけに終わってしまうケースが少なくありません。
このような、ニーズや課題に向き合うためにも、当社は「資源循環サービス」の提供を始めました。「資源循環事業部」は、新井紙材としてこれまで培ってきた「企業ネットワーク」と「リサイクルや再資源化のノウハウ」を持つ、産業廃棄物処理の専門チームです。 「資源循環サービス」のお客さまの業種は多種多様で、製本会社や段ボールの生産工場、EC物流や倉庫事業者からの段ボール資材の回収に加えて、自動車や半導体素材、プラスチック製品などの生産工場からのご相談もあります。業種や業態に応じて、ご相談の内容はさまざまですが、お客さま(企業や工場、物流)の廃棄物の課題に対して、ワンストップな解決策をオーダーメイドでご提案しています。
不用品買い取りから適正処理までトータルサポート

当社は、「資源循環サービス」を通じて、「廃棄物処理コストの削減」と「環境負荷の低減」を両立させることを目指しています。そして、お客さまがこれまで「廃棄物として処理・処分してきたものを資源化し、“価値”に変える」お手伝いをしています。「資源循環サービス」では、まず現地調査を行い、分別が必要なものがあれば、その適切な分別方法をレクチャーするなど、資源リサイクルのご提案を行います。
近年では、廃プラスチックの資源リサイクルのご相談が増えており、当社の実績として特に強みとしている分野です。廃プラスチックと一口に言っても、そこにはさまざまな種類があります。廃棄物を資源としてリサイクルするためには、素材ごとに分けて、物量を貯める必要があります。逆に、素材の中に少しでも不純物が混じると、それは廃棄せざるを得なくなってしまうのです。
例えば、紙製のラベルが付いた包装フィルムは、ラベルを剥がすと資源としてリサイクル可能になりますが、その一手間を省くと、焼却処理しか選択肢がなくなってしまいます。
このようなアドバイスを行うと、「分別の作業の仕方がわからない、どの種類をどのように分けると資源化できるかわからない」といった別の課題が出てくるため、当社がお客さまの分別の方法や取り扱う素材を実際に見て、具体的な方法をご提案します。
また、当社は、オフィス移転や事業所閉鎖の際の不用品撤去のトータルサポートにも力を入れています。瞬間的に多くの不用品を撤去する必要があるため、各業者の選定やスケジュール調整に煩わされている会社も少なくありません。
お客さまから「産業廃棄物を有価物化(リサイクルや再利用を目的として、有償で売却)したい」というニーズがあれば、可能なものは当社で買い取ります。買い取りが難しいものは、リサイクル率向上と環境負荷低減のための処理方法として、マテリアルリサイクルや燃料化などを提案します。当社では、オフィス什器の買い取りから、リサイクルと産業廃棄物の分別方法のご提案と、その後の処理までをワンストップでサポートすることが可能です。 その他、法令遵守が求められる処理困難物や少量多品種の滞留品など、他社で取り扱いが難しい廃棄物にも対応しており、安全かつ適正に処理・リサイクルすることで、環境汚染リスクを未然に防ぎます。
産業廃棄物を資源化し、“価値”に変える

「資源循環サービス」は、廃棄物の中のまだ再利用できる資源を徹底的に洗い出してリサイクルすることで、産業廃棄物を削減し「廃棄物処理コストの削減」に貢献します。さらに、リサイクルした資源の中から有価物を買い取ることで、処理にかかる経費を相殺することができます。一部のプラスチック製容器は洗浄・整形の上、再納品することで廃棄物を使える資源へと変換。これは、処理コストの削減とともに、輸送・焼却に伴うCO2排出量の削減にも繋がります。
一方、「環境負荷の低減」の側面で見ると、廃棄物の量を減らすことで、焼却処理や輸送にかかるCO2排出量を削減することができます。また、廃棄物の中から再資源化を進めることで、資源循環を推進します。
「廃棄物処理コストの削減」と「環境負荷の低減」、いずれの場合にも最も重要なのは、廃棄物を正しく分別し、処理することです。当社は、3R(リデュース・リユース・リサイクル)による徹底的な資源化と有価物買い取りを追求しています。その結果、廃棄物処理コストの削減とCO2排出量の削減をはじめとする環境負荷の低減を同時に実現します。
産業廃棄物を「資源」として捉え直し、有効活用することは環境負荷を低減するだけでなく、新たなビジネスチャンスや企業価値の向上にも繋がると、私たちは考えています。
当社は、廃棄物の分別指導から収集運搬、中間処理やリサイクル、そして有価物買い取りまで、トータルサポートが可能です。複数業者とのやり取りや管理の手間を削減し、コンプライアンスを遵守した適正処理を確実に行います。 私たちは、お客さまが産業廃棄物について悩んだ時に、一番に相談できる企業でありたいと考えています。お客さまへのサービスの提供を通じて、当社自身も脱炭素やSDGs、サーキュラーエコノミーの一助となるような活動を続けていきたいです。
まとめ
差別化が難しく、価格競争になりがちな廃棄物処理業界の中で、新井紙材は、「資源循環」をキーワードに、廃棄物に関して、お客さまのあらゆるお悩みを解決します。「廃棄物処理に関わる煩わしい業務から解放され、コア業務に集中したい」「環境経営を推進し、企業価値を高めたい」そうしたニーズに対して、新井紙材の「資源循環サービス」は産業廃棄物管理の側面から強力なサポートが可能です。廃棄物に関するお悩み、資源化やコスト削減、買い取りのご希望、突発的な不用品の撤去など、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
新井紙材株式会社 資源循環事業部 TEL:03-3408-5862 担当: 小野寺 誠 Email: m.onodera@araishizai.com