グローバル規模で加速する脱炭素の潮流。その中で、企業の真価が問われるのは、サプライチェーン全体を俯瞰した排出量削減への取り組みです。本記事では、今や避けて通れないScope3開示義務化の背景に迫り、その複雑な算定方法を紐解きます。
「自社の排出だけでは不十分」――そう突きつけるように、原材料調達から消費者の手に渡るまで、あらゆる事業活動で発生する間接的な排出、それがScope3です。その計測と削減は、まるで迷宮のよう。しかし、国際的な基準の厳格化と法規制の波は、もはや待ったなし。Scope3の開示は、企業の未来を左右する義務へと本格的にシフトしています。
だからこそ、企業は適切な算定方法を理解し、具体的な対応策を今すぐに検討しなければなりません。本記事は、その羅針盤となるべく、Scope3の算定方法から、明日から実践できる取り組み方までを徹底解説。読み終えたとき、あなたはScope3への深い理解とともに、確かな一歩を踏み出す準備ができているはずです。さあ、未来のビジネスを拓くための第一歩を踏み出しましょう。
INDEX
スコープ3とは何か?
まずは、Scope3の定義とその対象となるカテゴリについて解説します。Scope3は、企業のバリューチェーン全体にわたる間接的な温室効果ガス排出を対象としており、その範囲は広範囲にわたります。
(1)定義
Scope1・2・3は、ライフサイクル全体の温室効果ガス(GHG)排出量を把握するための基準となる考え方です。Scope1は、自社が直接排出するGHGを指し、Scope2は自社が間接的に排出するGHG(例えば購入した電力に関連する排出)を指します。
それ以外がScope3に該当し、自社事業に関連する他社の排出が含まれます。具体的には、サプライチェーンで発生する自社以外の排出や、製品使用後の廃棄物処理などが該当します。このように、企業は自社が直接管理できない部分まで排出量を算定し、全体的な環境負荷を把握する必要があります。
したがって、Scope3は温室効果ガス削減において重要な役割を果たしています。
(2)スコープ3カテゴリ-
Scope3は、15のカテゴリに細かく分類されています。製造時の部品調達や原材料の輸送といった「上流」に加え、販売会社での取り扱いや製品使用後の廃棄物処理など「下流」の活動も対象です。
また、従業員の通勤や出張による排出も含まれます。したがって、Scope3を算定する際は、上流から下流まで広範囲にわたる排出量の把握が必要です。
| カテゴリ | 排出活動 |
| 購入した製品・サービス | 原材料の調達、パッケージングの外部委託、消耗品の調達 |
| 資本財 | 生産設備の増設(建設・製造が複数年の場合は、建設・製造が終了した最終年に計上) |
| Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 調達している燃料の上流工程調達している電力の上流工程 |
| 輸送、配送(上流) | 調達物流、横持物流、出荷物流 |
| 事業から出る廃棄物 | 廃棄物(有価のものは除く)の自社以外での輸送 |
| 出張 | 従業員の出張 |
| 雇用者の通勤 | 従業員の通勤 |
| リース資産(上流) | 自社が賃借しているリース資産の稼働 |
| 輸送、配送(下流) | 出荷輸送(自社が荷主の輸送以降)、倉庫での保管、小売店での販売 |
| 販売した製品の加工 | 事業者による中間製品の加工 |
| 販売した製品の使用 | 使用者による製品の使用 |
| 販売した製品の廃棄 | 使用者による製品の廃棄時の輸送、処理 |
| リース資産(下流) | 自社が賃貸事業者として所有し、他者に賃貸しているリース資産の稼働 |
| フランチャイズ | 自社が主宰するフランチャイズの加盟者のScope1、2 に該当する活動 |
| 投資 | 株式投資、債券投資、プロジェクトファイナンスなどの運用 |
| その他(任意) | 従業員や消費者の日常生活 |
▼スコープ3カテゴリーについて詳細な説明をしている記事はこちら
スコープ3の義務化が決まった背景
スコープ3の義務化が進んだ背景には、サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量を管理・削減する社会的要請の高まりがあります。スコープ1・2は、自社内での直接排出や購入した電力・熱などによる間接排出に限定されており、企業活動全体の排出量を把握するには不十分でした。
しかし、製品のライフサイクル全体を評価するLCA(ライフサイクルアセスメント)の概念が注目され、原料調達、製造、物流、販売、廃棄といったサプライチェーン全体を対象とするスコープ3が重要視されるようになりました。
この動きは環境面での責任だけでなく、投資家からのESG評価やリスク管理の観点からも加速しています。スコープ3を算定・開示することで、企業は透明性を向上させるとともに、持続可能な社会づくりへの貢献が求められています。
出典:環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」p3(2017/11)
スコープ3の算定方法と選択基準
ここでは、Scope3の算定方法と選択基準について解説します。効果的な算定と管理を行うためには、排出量データの正確性と優先順位の付け方が重要です。
(1)算定方法の選択基準
Scope3の算定方法を選択する際は、排出量の正確性と実効性を担保するための基準が重要です。以下の基準に基づき、各Scope3の算定手法を選択するのが望ましいとされています。
- Scope3活動による排出量の相対的大きさ
- 企業の事業目標(Scope3基準の第2章を参照)
- データの入手可能性
- データ品質
- 各手法を適用するために必要なコストと努力
- その他企業が定める基準
これらの基準を考慮することで、企業はその活動からの排出量を正確かつ効率的に算定し、適切なデータを提供できます。また、社内外の関係者にとって有用な意思決定に役立つインベントリの作成に繋がります。
出典:環境省「GHG プロトコル Scope 3 排出量の算定技術ガイダンス」p10
(2)算定方法
Scope3のGHG排出量の測定には、直接測定と見積りを使用した測定の2つの方法があり、多くは見積りが含まれる可能性が高いです。見積りでは、企業が活動データと排出係数を掛け合わせて排出量を算出します。この計算式は以下の通りです。
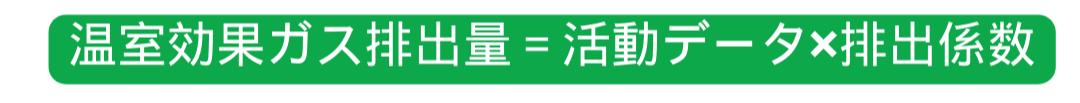
測定にあたっては、忠実な表現となる測定アプローチ、インプット、仮定を使用し、報告に含める温室効果ガス排出の範囲を適切に決定する必要があります。さらに、測定アプローチ、インプット、仮定を選択する際には、過大なコストや労力をかけず、報告日時点で利用可能な合理的で裏付け可能な情報を活用することが求められています。
出典:金融庁「第3回 金融審議会 サステナビリティ情報の開示と 保証のあり方に関するワーキング・グループ」P20(2024/06/28)
スコープ3とESG投資の関係
ここでは、Scope3排出量の測定とESG投資との関係について説明します。近年、企業の環境負荷を正確に把握し、報告することが投資家にとって重要な評価基準となっています。そのため、Scope3の開示はESG投資において不可欠な要素です。
(1) ESG投資におけるScope3の位置づけ
サプライチェーン排出量の開示は、ESG投資の評価を高め、資金調達に繋がる可能性があります。例えば、GPIF(年金積立金管理運用法人)がPRI(国連の責任投資原則)に加盟した際、PRIは投資プロセスにESG要因を組み込むことを支援しました。
このように、企業がサプライチェーン排出量を開示することは、GPIFなどの投資家から注目を集め、資金調達の機会を増やすための重要なステップです。
出典:環境省「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」P42 (2023/03/01)
(2)Scope3情報の開示で期待されるメリット
Scope3の情報を開示することにより、以下のメリットが期待できます。
■削減対象の特定
自社のサプライチェーン排出量全体を把握し、排出源ごとの割合を明確にすることで、優先的に削減すべき領域を特定できます。
■他事業者との連携による削減
排出量算定に必要な情報交換を通じて、サプライチェーンの他企業と連携し、共同で削減策を策定して実施できます。
■機関投資家等の質問応答
機関投資家や環境格付機関に対し、サプライチェーン排出量に関する質問へ適切に回答することが可能です。それにより、自社の環境経営への取り組みをアピールし、投資家等からの自社評価を向上させることができます。
■環境軽視指数に活用
自社のサプライチェーン排出量の変動を把握することが可能です。それにより、環境経営指標として有効に活用できます。
■削減貢献量の評価
サプライチェーン排出量と削減貢献量を同時に公表することで、削減効果の参考指標として活用できます。
■CSR情報の開示
企業の社会的責任の一環として、サプライチェーン排出量をCSR報告書やウェブサイトに掲載し、自社の環境活動への理解を促進できます。
Scope3の情報開示は、特に自社の透明性向上に繋がることに加え、それが投資家からの評価を高めます。
出典:環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」p3(2017/11)
スコープ3の義務化における日本企業の現状
Scope3の義務化は最近決定されたばかりですが、企業にとっては算定に大きな負担がかかると予想されています。しかし、すでにScope3の算定を実施している企業は増えており、今後の取り組みが注目されています。
以下は、日本ハム株式会社の取り組み事例です。企業の対応状況を詳しく見ていきます。
■日本ハム株式会社
日本ハム株式会社は、2014年にサプライヤーと連携して削減算定を実施しました。
具体的には、食品製造、包装材製造、輸送の各サプライチェーンにおいて、購入した製品・サービスの中から「容器・包装」に注力し、軽量化によるGHG削減量の算定です。
この取り組みでは、製品メーカーが包装材メーカーに対してフィルムやトレイの軽量化を要請し、包装材メーカーは資材投資量の削減を通じて、包装材の軽量化を実現しました。その結果、Scope3カテゴリ1の削減に成功しています。
また、調達物量の減少は輸送事業者のCO2排出にも影響を与え、輸送関連のScope1排出量を削減しました。これにより、日本ハムはScope3カテゴリ4の削減も達成し、実施した1年間で53tものCO2削減にも繋がっています。
まとめ:スコープ3の義務化に合わせて準備を進めよう
Scope3の義務化に向けて準備を進めることは、企業にとって重要なステップです。サプライチェーン全体での排出量把握や削減の取り組みが求められる中、しっかりとした算定体制を整えることで、透明性の向上や投資家からの評価アップにも繋がります。
まずは自社の排出源を整理し、実行可能な対策を見極めましょう。これからの取り組みが、持続可能な社会づくりに貢献するだけでなく企業の成長にも繋がります。














































































































