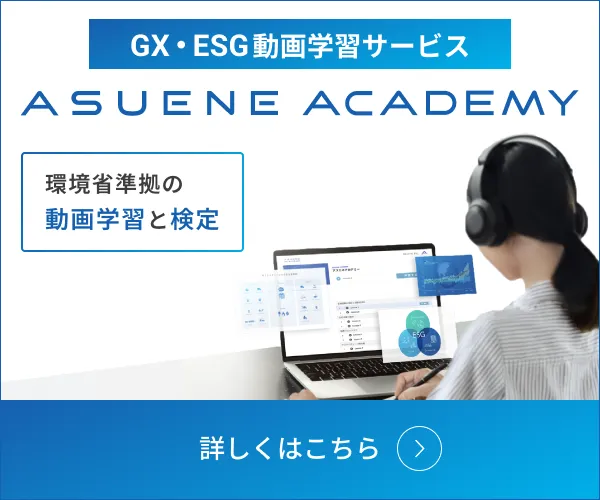近年、地球温暖化対策の重要性が増す中、企業には自社の事業活動全体における温室効果ガス(GHG)排出量の把握と削減が強く求められています。サプライチェーン全体での排出量、すなわちScope3排出量の算定は、カーボンニュートラル実現に向けた企業の取り組みにおいて不可欠な要素となっています 。Scope3は、自社の直接的な排出(Scope1)やエネルギー起源の間接排出(Scope2)以外の、事業活動に関わるあらゆる間接的な排出を指し、多くの場合、企業全体の排出量の大部分を占めています 。
これまで、Scope3排出量の算定においては、業界平均データや推計値といった二次データが用いられることが一般的でした。しかし、二次データでは、個々の企業やそのサプライヤーの具体的な排出削減努力が正確に反映されないという課題がありました 。例えば、再生可能エネルギーを導入した工場で製造された製品であっても、業界平均の排出原単位を用いることで、その低炭素な特性が適切に評価されないといったケースが見られます 。このような状況を踏まえ、環境省は2025年3月に「一次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド」Ver.1.0をリリースしました 。本ガイドは、より精緻なScope3排出量の算定を可能にし、企業の削減努力を適切に評価することを目的としています。本稿では、主に二次データを用いてScope3排出量算定を実施している企業のご担当者様に向けて、この新しいガイドの重要性、二次データとの違い、そして一次データ活用のための具体的なステップについて解説します。
INDEX
Scope3(スコープ3)とは
サプライチェーン排出量の構成要素
カーボンニュートラルの達成に向けて、サプライチェーン全体の脱炭素を目指していくことは必要不可欠です。そこで、サプライチェーン全体でどれくらいのCO2を排出しているかを把握するための指標となるのがサプライチェーン排出量です。サプライチェーン排出量はScope1・2・3の合計から算定されます。
Scope1:事業者自らによる直接排出(燃焼の燃焼、工業プロセスなど)
Scope2:他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3:サプライチェーン排出量における、Scope1・2以外の関節排出(事業者の活動に関連する他社の排出)を指しGHGプロトコル上では15のカテゴリに分類される

出典:環境省『サプライチェーン排出量算定の考え方』(p.9)
参考:Alt属性(各カテゴリへのScope3活動の分類結果)
Scope3(スコープ3)を算定する4つのステップ
Scope3は以下の4つのステップで算定できます。
STEP1:算定目的を設定する。
STEP2:算定の対象範囲を確認する。
STEP3:Scope3の活動をカテゴリ1〜15に分類する。
STEP4:カテゴリごとに計算した基本式を合計する。
基本式は活動量に排出原単位を乗じた値です。活動量の例としては電気の使用量や貨物の輸送量、廃棄物の処理量などがあります。排出原単位には電気1kWh使用あたりのCO2排出量などがあります。
出典:環境省『サプライチェーン 排出量算定の考え方』(p.7〜11)
なぜScope3排出量算定は一次データが重要なのか?二次データとの違い
サプライチェーン排出量の算定において、一次データと二次データは根本的に異なる性質を持っています。一次データとは、企業自身またはそのサプライヤーから直接提供される、実際の活動量や排出量に関する測定値のことです 。例えば、特定の製品の製造に使用されたエネルギー量、輸送距離、あるいは特定のサプライヤーが報告する自社の排出量などが一次データに該当します 。一方、二次データとは、業界平均、統計データ、排出原単位データベースなど、個々の企業の活動に特化したものではない、外部のデータソースから得られる情報です 。サプライヤーから提供された排出量データはScope3算定事業者にとって1次データに該当するとしています。たとえサプライヤーが排出量原単位データベースなどの二次データを用いていた場合でも、Scope3算定事業者が受領した数字は一次データとして扱えることが明記されています。
出典:環境省『1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド』(P28)
一次データを利用することには、以下のような重要な利点があります。
- 排出削減努力の正確な反映
一次データは、企業自身とそのサプライヤーが行った排出削減の取り組みや、よりクリーンな技術への投資を直接的に反映します 。これにより、持続可能性への貢献がより明確に評価され、さらなる削減努力へのインセンティブとなります。例えば、ある企業が再生可能エネルギー由来の電力を使用している場合、その一次データを使用することで、二次データを用いた場合よりも低い排出量を算定できます 。 - 排出ホットスポットの特定
より詳細な一次データを用いることで、サプライチェーン全体における排出量の多いプロセスやサプライヤーを特定しやすくなります 。これにより、企業は最も効果的な排出削減戦略を策定し、資源を集中させることができます。例えば、特定の原材料の調達における排出量が大きいことが一次データによって明らかになった場合、そのサプライヤーとの連携を強化したり、より低炭素な代替材料を探したりするなどの対策を講じることが可能です。 - 透明性と信頼性の向上
一次データに基づく排出量報告は、投資家、顧客、規制当局などのステークホルダーからの信頼性を高めます 。環境意識の高まりとともに、企業はより透明性の高い情報開示を求められており、一次データの活用はその要求に応えるための重要な手段となります。 - 国際的な動向との整合
世界的に、より正確な排出量算定と報告が求められる傾向にあり、一次データの利用を推奨または義務化する動きも出てきています 。環境省のこのガイドラインも、そのような国際的な潮流に沿ったものです。
出典:環境省『1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド』(P22)
Scope3排出量2次データを利用したScope3排出量算定における課題
- 個別事情の反映不足
二次データは、個々の企業やサプライヤーの具体的な状況や取り組みを反映することができません 。そのため、たとえ排出削減努力を行っていても、その効果が算定結果に表れにくいという問題があります。 - 製品・サービスの特性の無視
特に、低炭素な製造方法や再生可能エネルギーを利用して生産された製品やサービスの場合、二次データではその環境負荷の低さが適切に評価されない可能性があります 。 - 進捗状況の把握の難しさ
次データでは、具体的な排出削減イニシアチブの進捗や影響を詳細に追跡することが困難です 。
出典:環境省『1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド』(P23)
環境省主催の勉強会に参加する方法も
Scope3への取り組みを推進するために国が勉強会を開催しています。このような場に参加することで、Scope3の算定方法などについての理解を深めることができます。
たとえば、環境省が主体となり、サプライチェーン排出量の把握や管理の促進を目的とし、サステナビリティ担当者などを対象とした勉強会が2021年10月にオンラインで開催されました。勉強会の中でScope3の概論や算定方法などが解説されています。
出典:環境省『サプライチェーン排出量算定に関する実務担当者向け勉強会を開催します』
また、アスエネでも算定方法に関して面談にてご相談もできますので、お気軽にお問合せ下さい。
以下では、4つのステップに関してより詳しく解説していきます。
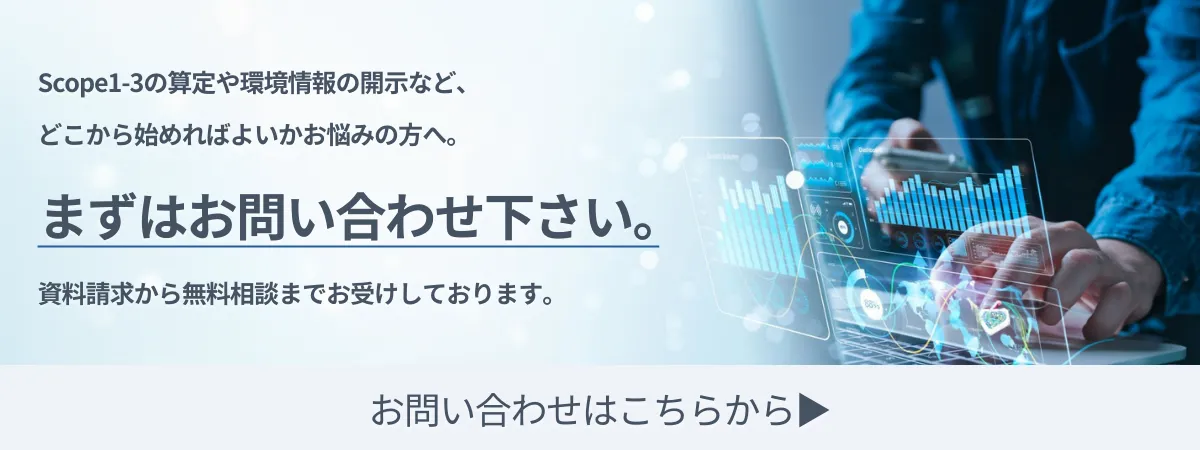
STEP1&2:目的の設定と対象範囲の確認
Scope3排出量を算定する前にすべきこととして、なぜ算定するのかという目的の設定と対象範囲の確認があります。ここでは目的の設定の考え方や具体例、対象範囲の確認についてご紹介します。
STEP1:目的の設定
Scope3の算定を始めようと考えている企業がまずすべきことは、Scope3を算定する目的の設定です。環境省が公表している基本ガイドラインでは、最初から詳細な算定は困難であるため、段階的に取り組むことが推奨されています。また、具体例として以下のような目的を紹介しています。
- 効率的な削減対策の実施
- 事業者間での削減取組の連携
- 説明責任の向上
出典:環境省『Scope3〜算定編〜』(2020年12月)(p.10.11)
STEP2:対象範囲の確認
Scope3を算定する目的を設定したら、どこまでを算定の対象とするのか対象範囲を確認します。算定する目的に合わせ、国内グループだけを対象とするのか、海外グループも対象とするのかを決定します。
STEP3&4: 15カテゴリへの分類と排出量合計
Scope3を算定する目的と対象範囲を設定したら、15あるカテゴリに分類しScope3排出量を算定します。ここでは、カテゴリの分類の仕方や計算式についてご紹介します。
STEP3:カテゴリに分類
対象範囲を決めたら、それぞれの活動がどのカテゴリに該当するのか分類します。
Scope3のカテゴリは、お金の流れで上流と下流に分類されています。カテゴリ1〜8までが上流、9〜15までが下流です。上流は原則として購入した製品やサービスに関する活動、下流は原則として販売した製品やサービスに関する活動と定義されています。

出典:環境省『サプライチェーン 排出量算定の考え方』(p.3)
STEP4:基本式を計算
対象範囲をカテゴリに分類したら、1つずつ基本式を計算します。全てを合計した値がScope3排出量になります。基本式は、活動量に排出原単位を乗じて求めます。電気の使用量や貨物の輸送量などが活動量に該当しますが、社内の各種データの他、業界平均データや文献データなどからも収集できます。排出原単位には電気1kWh使用量あたりのCO2排出量などが該当し、既存のデータベースの他に取引先からデータの提供を受けることもできます。

出典:環境省『Scope3〜算定編〜』(2020年12月)(p.4)
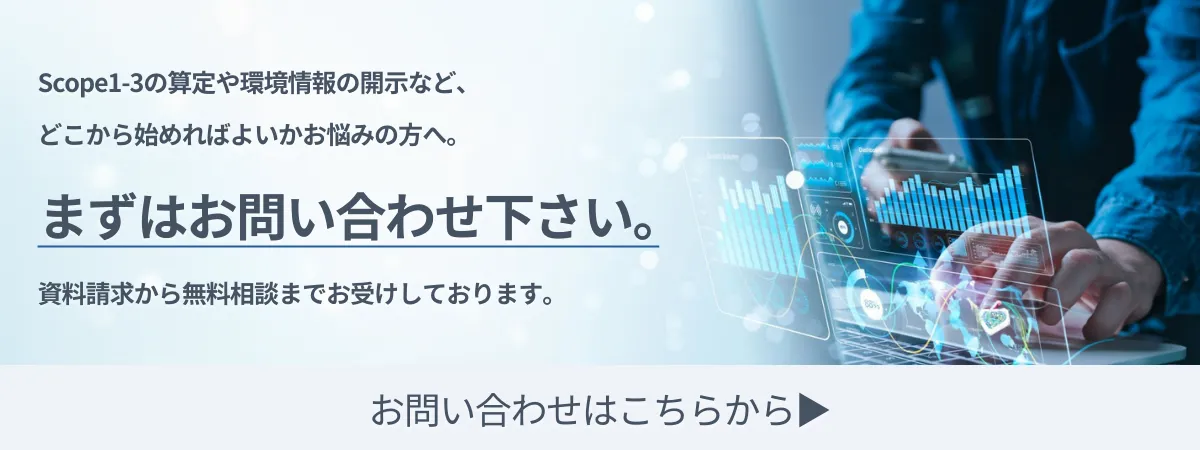
2025年3月環境省が発行した「一次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド」のポイント
環境省が発行した「一次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド」Ver.1.0は、まさにこのような背景を踏まえ、企業がより積極的に一次データを活用し、実態に即したScope3排出量算定を行うための具体的な指針を示すものです 。本ガイドは2025年3月に公開され、事業者の排出削減努力をScope3排出量に反映させることを主な目的としています 。
環境省「一次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド」はこちらから👈
このガイドの重要なポイントとして、以下の点が挙げられます。
- Scope3カテゴリ1に焦点を絞った方法論
Scope3の15のカテゴリの中でも、特に「購入した製品・サービス(カテゴリ1)」に焦点を当て、算定事業者がサプライヤーから入手した一次データをどのようにScope3算定に反映させていくかに関する具体的な方法論を整理しています 。カテゴリ1は、多くの企業においてScope3排出量の大部分を占めるため、このカテゴリにおける一次データ活用を促進することは、全体の精度向上に大きく貢献します。 - 既存ガイドラインの補完
「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」を補完する位置づけであり 、既にある算定の枠組みの中で、どのように一次データを効果的に活用していくかを具体的に示しています。 - 算定事業者の視点
排出量データを提供するサプライヤー企業ではなく、そのデータを受領して自社のScope3排出量算定に活用する側の企業の視点に立って記述されています [User Query]。これにより、Scope3排出量算定を担当する企業が直面するであろう疑問や課題に寄り添った内容となっています。 - 製品ベースの算定の推奨
新しいガイドラインでは、製品ベースでの算定を最も精緻な一次データによる算定と位置づけています 。これにより、個々の製品やサービスに紐づいたより正確な排出量把握が可能になります。 - リリースまでの経緯
当初、本ガイドラインは2024年3月末に公開予定でしたが、一次データの取り扱いについて各業界で意見が分かれ、環境省として意見を集約するのに時間を要しました 。この経緯からも、一次データ活用に対する期待と、その導入における課題の存在が伺えます。 - データの品質保証や検証
一次データを提供するサプライヤーには排出量だけでなく、補足情報や保証の有無なども含めたアンケート形式で情報提供を行うことが推奨されており特に提供されるScope3算定期間と一致し、かつ第三者による保証をうけることが望ましいとされています。製品ベースでの保証が困難な場合には、組織ベース排出量のデータを活用する選択肢についても触れており、GHGプロトコルでも製品固有性の高いデータの使用が推奨されているとしています。
出典:環境省『1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド』
まとめ:Scope3(スコープ3)排出量の算定方法を理解し、算定を検討しよう!
この記事では、環境省が新たに公開した「一次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド」を中心にScope3排出量算定の精度を高めるべく排出量の算定方法から基本的な概念までをご紹介しました。排出量の算定は企業の脱炭素化への取り組みを加速させる重要な一歩であり、Scope3排出量を重要視する大企業が増加する中、中小企業にとってもScope3に関する基本的な知識、特に算定方法への理解は不可欠であり、本記事を参考に一次データ活用への移行を検討することが、より実効性の高い排出量削減とサステナブル情報の開示における透明性の向上に繋がります。長期的な視点で見れば移行にはいくつかのステップと課題が伴うものの、導入後のメリットは非常に大きいです。
まずは環境省のガイドラインとアスエネからの発信情報を詳細に確認し、自社の状況に合わせて一次データ活用に向けた具体的な検討されてみるのはいかがでしょうか。
アスエネ株式会社ではScope3算定に関するセミナーや関連資料の配布を行っております。不明点などございましたら下記よりお問い合わせください。