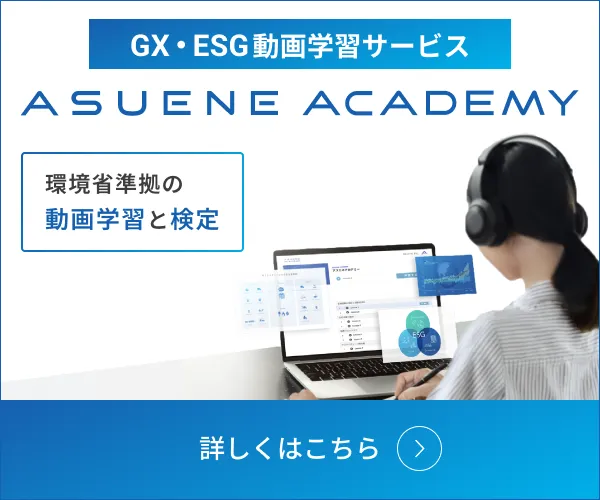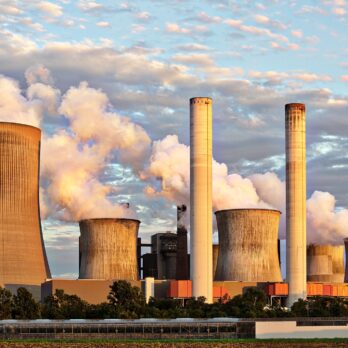脱炭素社会の実現を目指す中で、水素技術の進化とその活用が急速に進行しています。特に、世界各国の水素戦略には多くの注目が集まっており、その背景には水素の持つ多大な潜在能力があります。
温室効果ガスを発生させないクリーンエネルギーとして注目されている水素は、水などのさまざまな資源から製造できることからる「ブルー水素」や「グリーン水素」などたくさんの種類が存在します。これらは資源の乏しい日本でも調達が容易な新しい資源として期待されています。また、温室効果ガスの発生を抑制できることもあり、今後ますます注目を集める資源となっています。
この記事では、そうした水素の利用動向種類の説明から、各国の水素活用に関する最新の水素戦略動向について詳しく解説していきます。これらの水素は、温室効果ガス削減の切り札と言える存在であり、それぞれの特徴や製造方法について詳しく解説します。
INDEX
水素戦略の概要
水素戦略の概要と水素の種類について解説しています。
水素戦略と水素エネルギーとは?
使用しても二酸化炭素を排出しない次世代のエネルギーとして水素が期待されています。その水素を自動車の動力源や発電のエネルギー源として、あらゆる分野で利用する社会が「水素社会」です。各国は水素社会の実現に向けて様々な目標(水素戦略)を掲げています。
水素エネルギーの特徴
水素は、酸素と結びつけることで発電や燃焼させて熱エネルギーとして利用することができる上、CO2を排出しない物質であるため、注目を集めています。水素は環境にやさしく、輸入の依存度が高い化石燃料に比べエネルギー安全保障にも役立ちます。日本は多くのエネルギーを海外から輸入しているため、水素を利用することでエネルギーの多角化や自給率の向上が期待されます。
燃料電池自動車や燃料電池バス、家庭用燃料電池「エネファーム」など、さまざまな分野での利用が進められています。
出典:経済産業省 資源エネルギー庁『次世代エネルギー「水素」、そもそもどうやってつくる?』(2021/10/12)
出典:経済産業省 資源エネルギー庁『水素エネルギー」は何がどのようにすごいのか?』(2018/1/23)
水素にも種類がある?
クリーンエネルギーとして注目されている、ブルー水素とグリーン水素の違いについて、詳しく解説します。
ブルー水素
ブルー水素は、天然ガスや石炭等の化石燃料を、蒸気メタン改質や自動熱分解し水素と二酸化炭素に分解することで、作られる水素です。
つまり、この方法は化石燃料由来の水素製造です。CO2回収・貯留(CCS)技術と組み合わせて活用することで、CO2を抑制できるため、温暖化対策の目標達成の一助となりうる水素製造方法であるといえます。
グリーン水素
グリーン水素は、水を電気分解し、水素と酸素に還元して生産する水素のことです。この方法では、二酸化炭素などの温室効果ガスを一切発生させないことから、環境への悪影響を与えることなく水素を生産できます。
ちなみに電気分解するにあたって電気が必要となりますが、この電気を化石燃料の発電によって賄うと意味がありません。そこで、風力や太陽光など再生可能エネルギーを利用すれば、温室効果ガスを生成することなく水素を生産することが可能になります。
その他にも水素を作る方法がある?
グレー水素
「グレー水素」は、水素が生産される流れはブルー水素と同様です。異なるのは、二酸化炭素を回収せず大気中に放出するという点です。
グレー水素は、既に現在の工業生産において多用されており、現在生産されている水素の95%がグレー水素になっています。
イエロー水素
「イエロー水素」は、グリーン水素と同様に水の電気分解によって生産されます。原子力発電を利用しているため、温室効果ガスの発生は抑制されるものの、放射性廃棄物を生み出すため、必ずしもクリーンエネルギーとは言えない一面もあります。
出典:資源エネルギー庁『次世代エネルギー「水素」、そもそもどうやってつくる?』(2021/10/12)
ブルー水素vsグリーン水素!どちらが有利?
では、ここからはブルー水素とグリーン水素の比較を通し、これからの社会においてどちらが有利になるのかを考えます。
実用性
多くの企業は、「ゼロ・エミッション」を掲げて、水素を主流とするエネルギーへの展開を図っています。実用性の面で言えば、グリーン水素とブルー水素のいずれからできる水素も、水素としての違いはありません。
ただし、ブルー水素の場合は温室効果ガスである二酸化炭素を貯留し、それを水素生産に使うため、大規模な生産施設が必要となります。
グリーン水素も、水から水素を製造するため、安定して水が供給できる場所でなければ生産できない現状があります。
そのため、ブルー水素においては「供給に十分な生産施設をいかに確保するか」、グリーン水素においては「供給の安定性をどのように確立するか」が実用化の鍵を握っているといえます。
生産コスト
グリーン水素とブルー水素のどちらを優先的に導入するか、大きなカギを握るのは「どちらがより生産コストを抑えられるか」にあります。
グリーン水素とブルー水素のコストを比較した場合、グリーン水素の方がブルー水素よりもコストが高くなります。
なぜなら、グリーン水素は電気分解により水素を生成するため、その電気を確保するためのコストがどうしても必要不可欠であるからです。しかし、最近の技術革新により、グリーン水素の製造コストは、2015年から2020年までに40%のコストダウンに成功し、2025年までにさらに40%程度のコストダウンを実現すると予想されています。
コストの削減は、グリーン水素の販売価格にも影響を与えます。2021年10月時点では、世界的なグリーン水素の販売価格(1キログラム)は3ドル(日本円で342円)~5ドル(日本円で571円)となっています。
一方コストダウンを図ることで、現在の価格の3分の1にすることが現実的に可能とされています。水素が1キロ当たり120円前後で売られるようになれば、ガソリンよりも安価な燃料として市中への普及へも進みます。
それらの技術革新を踏まえて、EUでは、ブルー水素ではなくグリーン水素を普及させることを政策として掲げており、日本をはじめとする先進国も追随する可能性があります。
出典:日本経済新聞『脱炭素の救世主か 水素の課題と可能性、イチから学ぶ』(2012年10月)
出典:資源エネルギー庁『次世代エネルギー「水素」、そもそもどうやってつくる?』(2021/10/12
世界の潮流
世界における水素エネルギーの供給にあたっては、先進国による「水素エネルギーの元となる資源探し」が積極的に進められています。例えば、ASEANなどの新興経済国が排出する温室効果ガスなどを「水素エネルギーのもととなる資源」とみなし、それらを日本に輸送して水素を生産する実証実験もスタートしています。
水素は、そのままでは輸送しづらいため、他の物質と化学反応を起こさせて液体化することで、貯蔵や輸送をおこないやすくします。この「有機ケミカルハイドライド法」は、天然ガスなどを液体化して輸入してきた日本の先進的な技術の1つです。
今後、世界規模で水素の確保競争や生産競争が進む中、その原料確保をめぐる国同士の駆け引きも、一層と激化することが予想されています。
出典:資源エネルギー庁『2020年、水素エネルギーのいま~少しずつ見えてきた「水素社会」の姿』(2020年1月)
水素社会の実現に向けて
ここからは日本における水素社会の実現について、その状況や将来について詳しく解説します。
政府が描く「水素社会」とは
出典:環境省『脱炭素化にむけた水素サプライチェーン・プラットフォーム』
日本の産業界において、水素は製鉄所等の産業部門において主に利用されていました。
それが最近では、クリーンエネルギーとして自動車やバスなどの燃料や、家庭において電気と熱を同時に作るエネファーム等に活用されています。今後、自動車メーカーによる水素燃料を実用化した市販車の開発・販売をはじめ、化石燃料に代わって主たる燃料として水素が供給される社会づくりが進んでいくでしょう。
カーボンニュートラルと水素燃料
出典:環境省『脱炭素化にむけた水素サプライチェーン・プラットフォーム』
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスを排出しない社会づくりを標榜する言葉です。温室効果ガスの排出を抑制しなければ、地球温暖化はますます進行し、気候変動や超巨大な台風の発生など、未曽有の災害を引き起こす要因になります。
世界各地で起きている気候変動による被害をこれ以上大きくしないために、温室効果ガスの排出削減量を数値目標化するなどして、カーボンニュートラルに取り組む必要性が高まっているのです。
水素は、家庭における燃料として、また自動車や航空機、船舶などの輸送手段の燃料として、今後ますますの普及が期待されています。
日常生活や生産活動の部分から、温室効果ガスの排出を削減することが、世界的な急務となっているのです。
今後の課題
環境保護のために必要と言える、水素エネルギーへの転換。しかし、そのための技術革新や新たな技術の普及は、まだまだ道半ばです。特に問題であるのは、技術革新や技術普及に必要な資金が不足していることです。
経済産業省では、水素の利用を進める民間事業に計3700億円を投じる計画を実行に移します。これは、脱炭素の技術革新を支援するために創設した2兆円の基金を活用する大規模な支援プランです。
既に、日本の水素関連技術は、世界の中で最高レベルにあるとされています。ですが、その普及や製品生産に至るまでの資金確保が難しいことから、政府として財政支援を行うことで、研究開発のペースを加速させる必要があります。
特に日本は、化石燃料系の資源のない国です。今までも、オイルショックなどで資源不足が懸念され、社会や経済に大きな影響を与えた歴史があります。今後国内で水を電気分解して水素を生産できれば、エネルギーを確保することが容易となり、結果的に国家の安全保障にもつながります。
今後、環境面のみならず、国家戦略としての水素エネルギーの導入をさらに加速することが、これからの日本に求められているといっても過言ではないでしょう。
世界の水素活用に関する動向
水素の利用に特に積極的なアメリカ、中国、ドイツ、フランスの4か国における水素戦略について解説しています。
(1)アメリカの動向
アメリカでは新車販売の一定数を、排出ガスが発生しないゼロエミッション車とする規制の下、カリフォルニア州を中心に、燃料電池自動車の導入が進んでいます。2024年からは商用車においてもゼロエミッション車の規制適用が開始される予定です。
ユタ州ではグリーン水素を活用した大型水素発電プロジェクトを計画しており、2045年までにグリーン水素のみでの運転を目指しています。
また、ロサンゼルス港ではゼロエミッション化に向けて、大型輸送船での水素利用も検討されています。
これを受けて政府は、2022年2月に地域クリーン水素ハブや、クリーン水電解プログラムなどに総額約100億ドルを拠出することを発表しました。
出典:経済産業省『水素を取り巻く国内外情勢と水素政策の現状について』p7
(2)中国の動向
中国ではEV車両における取り組みが活発的で、商用車を中心に燃料電池自動車がおよそ9000台導入されており、水素ステーションの数も2022年時点で約180箇所と世界最大の数を誇っています。
さらに、燃料電池自動車などの技術開発や普及状況に応じて奨励金を与える政策も進行中です。
出典:経済産業省『水素を取り巻く国内外情勢と水素政策の現状について』p7
(3)フランスの動向
フランスは2020年9月に国家水素戦略を改定し、2030年までに電解装置による水素製造能力を6.5GWに引き上げる方針です。水素の生産にかかる電力は再生可能エネルギーや原子力発電で賄う予定で、水素の活用先としては燃料電池トラックの普及などを優先的に実施する意向を示しています。
出典:経済産業省『水素を取り巻く国内外情勢と水素政策の現状について』p7
(4)ドイツの動向
ドイツは2020年6月に国家水素戦略を策定し、国内の再生可能エネルギーによる水素製造能力を2030年までに5GWにするなどの目標を設定しました。
また、水素利用技術の開発に対して補助金を支給する意向であり、水素技術の市場創出に70億ユーロ(およそ1兆1000億円)、国際パートナーシップ構築に20億ユーロ(およそ3000億円)を助成する方針です。
出典:経済産業省『水素を取り巻く国内外情勢と水素政策の現状について』p7
オマーンとシンガポールにおける国家水素戦略
最近、国家水素戦略を発表したオマーンとシンガポールの、具体的な戦略の内容について解説しています。
(1)オマーンの国家水素戦略
オマーンの国家水素戦略とは
オマーンは2022年10月に2050年カーボンニュートラル目標を宣言するとともにグリーン水素戦略を公表しました。
このグリーン水素戦略では、およそ1400億ドル(およそ20兆円)のグリーン水素事業への投資によって、2030年までにグリーン水素を100〜125万トン生産するという目標が表明されました。その後2040年には325〜375万トン、2050年には750〜850万トンとグリーン水素の生産量を増加させる方針です。
グリーン水素事業では、鉄鉱業・石油化学工業に対して脱炭素化の機会を提供する意向です。鉄鋼業や石油化学工業といった重化学工業は化石燃料を原材料として利用しており、脱炭素化が困難な産業分野でした。
そこで注目されたのが水素の活用です。例えば鉄鋼業では鉄鉱石の還元を石炭コークスでなく水素を用いて行うことで、二酸化炭素の排出を削減することが期待できます。
国家水素戦略の背景
オマーンがグリーン水素事業を進める背景には、石油や天然ガスなどの化石燃料から脱却しなければならない事情があります。オマーンの国家収入は石油・ガス収入が一貫して70%程度以上を占めていますが、他のアラブ諸国と比べて収入が低く、今後の採取できる年数も短いと見込まれています。
オマーン政府はその事実を受け、早い段階でグリーン水素事業に舵を切りました。
COP27を通して、このオマーンの水素戦略は世界から注目されています。
出典:エネルギー・金属鉱物資源機構『「グリーン水素ハブ」を目指すエジプト・オマーン―背景・事業動向・開発ビジョン―』(2022/12/28)
(2)シンガポールの国家水素戦略
シンガポールの国家水素戦略
シンガポールは2020年10月に、水素を主力電源に転換することを柱とする国家水素戦略を打ち出しました。2050年までのカーボンニュートラル達成を目指している中での発表であり、技術革新が進めば2050年までに電力需要の最大半分を水素で賄えると表明しています。
また、新設や更新をする火力発電所について、燃料の30%以上まで水素を混ぜて焼却できる設備を義務付ける規制案を提示し、いずれは水素への全面切り替えを求める方針です。
国家水素戦略の背景
シンガポールが水素戦略に乗り出す背景には、天然ガスへの過度な依存があります。
シンガポールはエネルギーの大半を輸入に頼ることから電力供給におけるリスクが大きく、最近は市況変動の影響が直撃したため、電気料金が2021年初めから1年半でおよそ45%も上昇しました。
出典:日本経済新聞『シンガポールが水素発電にカジ 2050年5割、企業呼ぶ』
日本の水素戦略
政府は次世代の脱炭素燃料としての水素の供給を増やすための新しい基本戦略(令和5年6月6日)を策定しました。この戦略では、今後15年間で官民合わせて15兆円の投資を行い、水素の供給網、すなわちサプライチェーンを整備することが予定されています。
さらに、2040年までには水素の供給量を現状の6倍の約1200万トンに増やすことを目標としています。この「水素基本戦略」の改定は、2017年に初めて策定されて以来のもので、政府は再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議を通じてこれを了承しました。この情報は日本経済新聞の記事に基づいており、政府の水素に関する取り組みの強化が伺えます。
出典:日本経済新聞『水素供給量、40年までに6倍に 政府が基本戦略改定』(2023/6/6)
まとめ:世界の水素戦略に注目し水素を用いてビジネスチャンスを狙おう!
世界各国で脱炭素社会に向けた水素戦略が実施されています。さらに、上述に記載したように、日本でも水素発電による再生エネルギーの利用、水素を利用した燃料電池自動車の開発など、水素の有効利用に向けてあらゆる分野で研究が進められ、導入が推進されています。今後、日本が水素に関してどのような取り組みを行っていくのかということに注目してみましょう。
加えて、グリーン水素のコストは、今後減少することが期待されています。中小企業にとって、グリーン水素の普及は大きなビジネスチャンスにつながります。例えば、家庭用の水素ボンベ、水素を用いた湯沸かし器など、今後の燃料供給が水素に生まれ変わることで、民需が活発になります。それらの技術を持つ中小企業は、今後大きなビジネスチャンスを迎えることになるでしょう。また、水素燃料のコストダウンとともに、電力小売り会社の電気料金コストも図られることから、通常の事業にかかるコストダウンを見込めるようになります。燃料にかかる費用が下がれば、その分の資金を活用し、成長が見込める分野へ投入することも可能になります。このように、水素エネルギーがもたらすメリットは、環境への負荷を軽減するだけではないことを、この機会にぜひ認識しましょう。