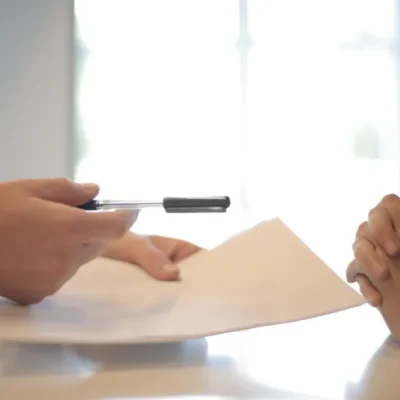地球温暖化に大きく影響する温室効果ガスを減らすためには、国だけでなく企業の温室効果ガス排出量削減の取り組みが不可欠です。地球温暖化による異常気象は、企業の経営にも大きなダメージを与えるため、早急な対応が求められます。
ここでは、改めて温室効果ガスについて振り返るとともに、今、温室効果ガスが引き起こしている問題と、温室効果ガス排出量削減に効果的な「カーボンニュートラル」を視野に入れた取り組みなどをご紹介します。
INDEX
温室効果ガスとは何か
温室効果ガスにはいくつかの種類があり、そして、私たちの生活が便利になるほど温室効果ガスは増えていきます。ここでは、私たちの生活と密着している温室効果ガスについてご紹介します。
温室効果ガスとは?
温室効果ガスとは、地球温暖化の原因となるガスで、「二酸化炭素」「一酸化二窒素」「メタン」「フロン」などが挙げられます。この温室効果ガスは、私たちが生活するために使われるエネルギーの消費で発生しており、そのほとんどは二酸化炭素となっています。
二酸化炭素は、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料を燃焼することにより発生するガスで、私たちの生活の必需品ともいえる電気、自動車、家電などから発生します。また、メタンは生ゴミや水田から発生し、フロンはエアコンや冷蔵庫の冷媒に使用されています。
出典:東京都環境局『温室効果ガスはなぜ増える?』(2018/02/09)
温室効果ガスの影響
温室効果ガスの影響を受けて、私達が直面している課題が地球温暖化です。実は人は、温室効果ガスがなければ地球では生きることができません。温室効果ガスが地球を温めてくれるおかげで、人含む生物が地球上で暮らしていけるだけの気温になるのです。しかし、技術の進歩とともに、人の活動による二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量が増え、地球上の平均気温が過度に上昇しており、これが「地球温暖化」と呼ばれています。
出典:環境省『温室効果のメカニズム』p,1.(2008/07/15)
日本の温室効果ガス排出量
2021年度の日本の温室効果ガス排出量は、11億7000万トン(CO2換算)となっており、前年度よりも2320万トン(CO2換算)の増加となっています。増加の原因としては、新型コロナウイルス感染症から経済が回復したことで、エネルギーの消費が増えたことが挙げられます。
温室効果ガス排出量全体で見ると、一番ピークだった2013年度の14億800万トン(CO2換算)に比べて、2021年度は2億3770万トン(CO2換算)の減少となっています。

出典:環境省『1. 温室効果ガス排出・吸収量』p,2.(2023/04/21)
温室効果ガスが企業に及ぼす影響
温室効果ガスは異常気象を引き起こす原因ともなっており、企業の経営にダメージを与える懸念があります。ここでは、温室効果ガスが企業に及ぼす影響をご紹介します。
地球温暖化から進んだ地球沸騰化
2023年7月、地球温暖化は地球沸騰化の時代となったと伝えられました。これは、世界の平均気温が史上最高になったことによるもので、その原因は人間が化石燃料を利用して排出された温室効果ガスであるとされています。
2023年7月の世界の平均気温は16.95度であり、人間が化石燃料に依存する前の世界の平均気温よりもおよそ1.5度上昇しているとされ、温室効果ガス排出量削減への取り組みが急がれます。
出典:BBCニュース『7月は史上最も暑い月に 国連総長は「沸騰化の時代」と警告 』(2023/07/28)
異常気象からなる自然災害による企業経営へのダメージ
地球温暖化による異常気象は、世界のあらゆるところで大きな影響を及ぼしています。一番多い影響が高温であり、日本は広範囲に渡って高温の影響を受けており、併せて気象災害も起こっています。
異常気象は企業経営にも大きな影響があり、気温の上昇による熱中症などの健康被害や、豪雨・台風発生の増加による企業保有施設の損壊などのダメージ、洪水被害での道路の寸断などによるサプライチェーン寸断のダメージなどの懸念があります。

出典:気象庁『世界の月ごとの異常気象』(2023/08/15)
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,9.p,10.(2023/03/08 )
企業の温室効果ガス排出量削減の取り組みの強化
気候変動による温室効果ガス排出量削減の取り組みとして、日本は2030年度までに温室効果ガスの排出量を2013年度比で46%削減することを目標としています。
しかし、ロシアのウクライナ侵攻の影響によってエネルギー供給が不安定となり、再生可能エネルギーと比較すると安定的な化石燃料が再び利用されるようになった現状もあり、温室効果ガスの排出削減に関しては難しい状況が続いています。
その間も、温室効果ガスによる気候変動は進んでおり、高温や豪雨、熱波など、夏の異常気象だけでなく、寒波や豪雪など1年を通した大規模災害の懸念があります。そこで、日本だけでなく全世界の企業に対して、温室効果ガス排出量削減の取り組みの強化が求められています。
出典:産経新聞『【主張】地球沸騰の時代 対応策強化に本腰入れよ 』(2023/08/04)
出典:日本経済新聞『2030年温暖化ガス10.6%増 各国目標分析、パリ協定遠く』(2022/10/26)
温室効果ガスを減らすためのカーボンニュートラル
温室効果ガス排出量を削減するためには、カーボンニュートラルの取り組みが不可欠です。カーボンニュートラルは、国だけでなく地域や企業が一丸となって取り組むことで結果が出ます。
カーボンニュートラルとは
カーボンニュートラルとは、CO2をはじめとする温室効果ガスの排出量と吸収量を均衝させ、実質的な排出量をゼロにすることです。
政府は「2050年カーボンニュートラル宣言」を提唱し、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目標としています。温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするためには、吸収作用を担う森林の適切な管理や植林などの強化と併せて、温室効果ガス排出量削減への取り組みが必要です。
出典:環境省『カーボンニュートラルとは – 脱炭素ポータル』(2023/01)
脱炭素ドミノの取り組み
2050年までにカーボンニュートラルを達成させるために、日本では国や地域、企業が協力して脱炭素の取り組みを進めています。
まずは2030年までに再生可能エネルギーの導入や住宅などの建物の省エネ化、電気自動車の導入、自然資源の保全の強化などの循環型社会の基盤をしっかりと整え、その後、その取り組みを全国へと移行し経済へとつなげる循環型経済を目指しています。
出典:環境省『カーボンニュートラルとは – 脱炭素ポータル』(2023/01)
企業が今すぐに取り組めること
地球沸騰化とささやかれる中、企業の早急な温室効果ガス排出量削減に向けた対応が求められます。ここでは、カーボンニュートラルを視野に入れた温室効果ガス排出量削減の取り組みをご紹介します。
LED照明の導入
オフィスに欠かせない照明は、エネルギー消費が意外と多く、特に冬季はオフィス全体でのエネルギー消費量の中で、割合が最も高いものとなっています。寿命が長く省エネ効果の高いLED照明を用いると、明るさはそのままに大幅な省エネを行うことができます。
さらに人感センサーや明るさセンサー、無線制御器具での照度調節を導入すると、手間がかからないにもかかわらず、最大約80%の省エネが見込めます。また、作業する場所だけ必要に応じて明かりを灯す「タスク・アンビエント照明」では、省エネ効果が期待できるだけでなく、明暗のバランスによってオフィスを快適な空間に整えることができます。
出典:環境省『省エネしながらより快適に! 建物のエコ照明化』(2017/03/07)
出典:環境省『タスク・アンビエント照明|あかり未来計画』(2017/11/21)
再生可能エネルギーへの電力切り替え
自社で使う電力を再生可能エネルギーに替えることで、温室効果ガス排出量削減に貢献することができます。近年、多くの小売り電気事業者が再生可能エネルギーを電源としたプランを用意しており、企業は自社で利用する電力を再生可能エネルギー電力に切り替えるだけで、新たに発電設備を導入することなく温室効果ガス排出量を削減することができます。
再生可能エネルギー100%の電力を選べば、温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることが可能です。

出典:環境省『再エネ電気プラン(企業・自治体向け) | 再生可能エネルギー導入方法』(2022/03/16)
ゼロカーボンドライブ
ゼロカーボンドライブとは、再生可能エネルギーを使って発電した車を使用することで、走行時のCO2の排出をゼロにする運転方法です。
ゼロカーボンドライブには、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)などがあり、営業用自動車をこれらの車に替えることで、温室効果ガス排出量削減に貢献できます。
出典:環境省『Let’s ゼロドラ!!(ゼロカーボン・ドライブ)』(2023/03/26)
まとめ:改めて温室効果ガスについて考え、企業で出来ることから始めよう
温室効果ガスによる異常気象の影響は、企業の経営を危うくさせるものであることから、温室効果ガス排出量削減は待ったなしの状況にあります。そんな中企業は、カーボンニュートラルを視野に入れた、温室効果ガス排出量削減の確実な対応が求められます。
企業の経営の危機を防ぐためにも、オフィスの照明の見直しや再生可能エネルギー電力への切り替え、営業用自動車のゼロカーボンドライブの導入など、今すぐ対応できる温室効果ガス排出量削減方法から、脱炭素経営を始めてみましょう。