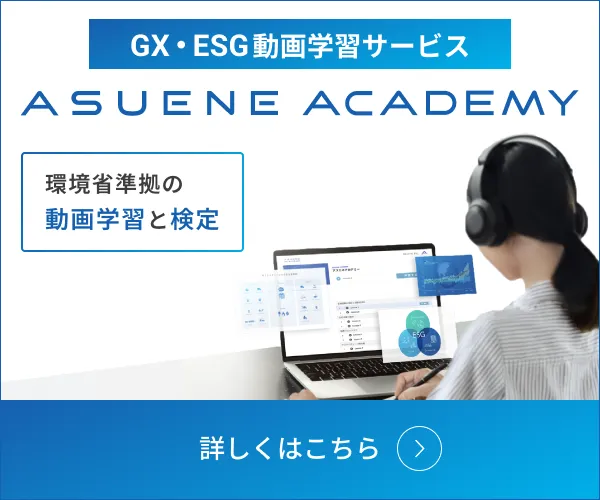環境省の発行している白書にはどのようなものがあるのか、概要やポイントをわかりやすく解説します!環境省の白書には気候変動などについて最新の状況が記載されており、人間社会が取り組むべき方向性が示されています。脱炭素・ESG経営をご検討中の法人の皆さまが押さえておくべき、「ネイチャーポジティブ」の考え方についてもご紹介します。
そもそも環境白書の「白書」とは!?
毎年さまざまな白書が、政府各機関から刊行されています。ニュースなどでもよく目にする言葉ですが、改めてその意味や位置づけについてご紹介します。
白書は政府の年次報告
白書は政治・経済・社会の実態および政府の施策の現状について国民に周知させることを主眼として、中央官庁が編集する政府刊行物であると定められています。現在日本における白書は、国会へ提出される報告書(法定白書)・閣議へ提出される報告書・通称として白書と呼ばれているものという、3種類があります。
出典:国立国会図書館「日本-白書の調べ方」(2023/4/27)
環境省の白書は主に3つ
環境省が国会へ提出する年次報告には、「環境白書」「循環型社会白書」「生物多様性白書」という3つの白書があります。環境問題の全体像を示すためにこれら3つの白書は平成21年度より合わせて編集されており、まとめて「環境白書」と呼ばれることもあります。
出典:国立研究開発法人 国立環境研究所「令和4年版『環境白書』のポイントを解説 環境省」(2022/6/7)
環境白書の内容(令和5年版)
環境白書の内容は、年度によってテーマが異なります。たとえば令和4年版においては「グリーン社会の実現に向けて変える私たちの地域とライフスタイル~私たちの変革から起こす脱炭素ドミノ~」がテーマでした。
令和5年版の環境白書のテーマは、「ネットゼロ、循環経済、ネイチャーポジティブ経済の統合的な実現に向けて~環境・経済・社会の統合的向上~」です。環境問題への対応によって、質の高い生活を将来にわたって持続可能な新たな成長につながることが示されています。ここではその要点をわかりやすくご紹介します。
(1)気候変動と生物多様性の現状と国際的な動向
第1部-第1章では地球温暖化の進行に伴い、深刻な気象災害が増加し、生物多様性への脅威にもなっていることが取り上げられています。これらの事象は災害による経済の停滞・気候変動に伴う農業生産量の減少など、人間社会にも重大な危機を及ぼしていると環境白書では指摘しています。
気候変動に伴う気象災害としては、世界各地における豪雨・熱帯低気圧・猛暑によるものが挙げられています。一方気候変動の原因とされている温室効果ガスの大気中濃度は上昇が続いており、速やかで持続的な排出削減が必要とされています。
出典:環境省「令和5年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書(要約)」P3~9
(2)持続可能な経済社会システムの実現に向けた取組
第2章では、さまざまな社会課題に対し、カーボンニュートラル・地域循環共生圏構築・自然再興を同時に達成するための、相乗効果が期待される取り組みが紹介されています。GX(グリーントランスフォーメーション)・脱炭素化・ESG金融・3R+Renewable(バイオマス化・再生材利用等)などの事例も多く取り上げられています。
こうした取り組みは「循環経済(サーキュラーエコノミー)」「自然再興(ネイチャーポジティブ)」という概念の中で語られています。
自然再興については後述します。
出典:環境省「令和5年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書(要約)」P10~14
(3)持続可能な地域と暮らしの実現
第3章では、地域循環共生圏という考え方について説明しています。地域循環共生圏とは、自立・分散型の持続可能な社会の姿です。各地域の資源を地域内で活用すると共に(自立)、地域同士が人・モノ・資金を循環させて支え合うという方法によって、環境・社会・経済課題の同時解決を目指すとされています。
また我が国の温室効果ガス排出量を消費ベースで見ると、全体の約6割が家計によるものであり、カーボンニュートラル達成のためライフスタイルを変える必要があるとも指摘しています。
出典:環境省「令和5年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書(要約)」P15~20
(4)東日本大震災・原発事故からの復興・再生に向けた取組
第4章は、東日本大震災による原発事故被災地の環境再生に関する内容です。帰還困難区域、福島県内除去土壌・ALPS処理水など今なお残る課題について、どのように復興・再生が進められてきたかを取り上げています。
出典:環境省「令和5年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書(要約)」P21~23
(5)講じた施策・講じようとする施策
令和5年版環境白書の第2部では、令和4年に講じた施策と令和5年に予定している施策を紹介しています。と言っても、両者に大きな違いはありません。一部開催される国際会議の名称が異なっている部分はありますが、基本的には同じ項目が並んでいます。
出典:環境省「令和5年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書(要約)」P24~25
ネイチャーポジティブとは
令和5年版環境白書では、先に見たように「ネットゼロ、循環経済、ネイチャーポジティブ経済の統合的な実現」が全体的なテーマとなっています。この中でも「ネイチャーポジティブ(自然再興)」は、従来の白書にはなかった新しい概念です。
令和5年版環境白書の重要テーマである「ネイチャーポジティブ」
ネイチャーポジティブは、生物多様性の損失を止めるだけでなく、回復に転じさせるという決意を込めた考え方です。日本政府は2023年3月に生物多様性国家戦略2023-2030を閣議決定しており、「2030年ネイチャーポジティブ」を達成するための5つの基本戦略を掲げています。
出典:環境省「環境白書第3節 自然再興(ネイチャーポジティブ)」
ネイチャーポジティブの事例としては、水田を保全することで自然が回復し、水害や水質悪化リスクなどの社会課題まで解決するというような取り組みが挙げられます。このように自然の再興が環境や経済にもたらすシナジーが、環境白書の中でも「地域活性化」「国土保全」「観光や農林水産業の振興」といった効果として謳われています。
出典:環境省「環境白書第3節 自然再興(ネイチャーポジティブ)」
ネイチャーポジティブの方向性
環境省が所管する「2030生物多様性枠組実現日本会議(J-GBF)」も、2023年2月28日の第一回J-GBF総会にて「J-GBFネイチャーポジティブ宣言」を発表しています。宣言の中には2030年までに生物多様性の損失を反転させ、回復軌道に載せることが掲げられています。
COP15で設定された国際目標では、2050年には自然と共生する世界を実現することとされています。これからの社会では、人類が存続する基盤としての生態系を維持・回復させ、真の循環型社会を目指すことが求められていると言えるでしょう。
まとめ:環境白書の内容について理解し、ネイチャーポジティブな未来を目指そう
令和5年版の環境白書の内容について、気候変動対策・地域循環共生圏などのポイントと、新たな概念であるネイチャーポジティブについてわかりやすくご紹介しました。
これからは単に自然を保護するということではなく、各地域の自然環境に立脚した循環型社会への変容が、事業活動にも求められます。環境白書の内容を理解して、ネイチャーポジティブな未来を目指しましょう!