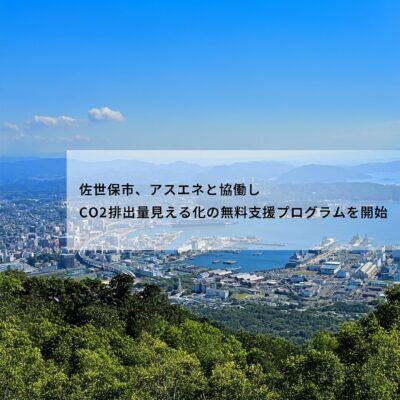本記事では、生物多様性クレジット制度について詳しく解説します。最初に、生物多様性クレジット制度とは何か、その定義や目的について説明します。次に、生物多様性クレジット制度のトレンドについて、世界各国での導入状況や取り組みの最新情報をご紹介します。
INDEX
生物多様性クレジット制度とは
生物多様性クレジット制度の意味や意義を解説します。
(1)生物多様性とは?
生物多様性(Biodiversity)とは、地球上の生物がバラエティに富んでいることを指し、複雑で多様な生態系そのものを表しています。私達人類は生物多様性の上に成り立っており、例えば食料や薬品、繊維など、私たちが生活する上で必要な資源の多くは、生物多様性があることによって成り立っています。
また、生物多様性は自然環境や気候変動の安定にも関与している一方で、昨今は生物多様性が人間活動によって脅かされている状況が続いています。生物多様性を脅かす要因は、大きく次の3つになります。
1. 人間活動による生態系の破壊
2. 外来種の侵入
3. 地球温暖化等の気候変動による危機
生物多様性を保全するためには、私たち人類が自然環境を守ること、外来種の侵入を防ぐこと、気候変動に対処することなどを行う必要があり、生物多様性の保全は私たちの生活や地球環境にとって非常に重要なことです。
出典:環境省「生物多様性」
(2)生物多様性クレジット制度以前にクレジット制度とは?
クレジット制度とは、環境保護や温室効果ガス削減などの取り組みの成果を評価・認証する制度であり、認証された成果は「クレジット」と呼ばれ取引されることがあります。クレジット制度は国内や国際的な範囲で存在し、企業や自治体などが環境保護や温室効果ガス削減などの取り組みを行ったことを証明することができます。
国内の例としては、J-クレジット制度があります。この制度は、省エネルギー機器の導入や森林経営などによるCO2の排出削減や吸収量を「クレジット」として国が認証します。クレジット制度によって認証されたクレジットは、環境保護や温室効果ガス削減などの取り組みを行った証明となります。
出典:J-クレジット制度「J-クレジット制度パンフレット」
出典:J-クレジット制度「カーボン・オフセットスキーム(How-to)」
(3)生物多様性クレジットとは?
生物多様性クレジットとは、個人や企業が豊かな生物多様性に貢献する環境プロジェクトに投資できる仕組みをいい、生物多様性クレジットには、以下のような種類があります。
- 生態系クレジット(ecosystem credit)とは
生態系の保護や復元に貢献した活動やプロジェクトに対して与えられる金銭的価値を持つ単位をいいます。生物多様性の保全や環境の改善に取り組む企業や個人によって取得され、販売や取引が行われることで、生態系サービスの価値を評価し、経済的なインセンティブを提供することができます。
- 種クレジット(species credits)とは
種クレジット(Species Credit)は、生物多様性の保全や絶滅の危機に直面する種の保護に貢献した活動やプロジェクトに対して与えられる金銭的価値を持つ単位です。種クレジットは、生態系の健全性と種の生息地の保全に焦点を当てています。
出典:NSW Department of Planning and Environment「What are biodiversity credits?」
(4)生物多様性クレジットの目的、重要性、利点と課題
生物多様性クレジットは、以下のような目的、重要性、利点、課題が存在します。
- 目的
生物多様性クレジットの目的は、生物多様性の保全や持続可能な経済システムの促進です。これにより、企業や公共部門が自然環境への負荷を減らし、生態系の回復や保護に貢献する点にあります。
- 重要性
生物多様性クレジットは、企業や組織が生物多様性に貢献することを奨励し、生態系や絶滅の危機に瀕している生物の生息地を保護することができるため、生物多様性の保全という点で重要です。
また、企業は自社の生産活動や供給チェーンにおいて生物多様性への悪影響を軽減し、生物多様性の保全に取り組むことが求められているため、企業の社会的責任を果たすことができます。
- 利点と課題
企業、公共機関が自ら率先して導入する生物多様性クレジットは、民間・公共機関が自然に配慮した経済システムを確立する役割を担うことができます。しかし、これには透明性を有した管理体制が必要であり、二重計上の防止、厳格な計測・報告・検証体制の構築が課題となります。
以上のように、生物多様性クレジットには、生物多様性保全や持続可能な経済システムの促進に貢献することが期待される重要な役割を担っており、生物多様性保全に取り組む上で、有用な手段となっています。
出典:NSW Department of Planning and Environment「What are biodiversity credits?」
出典:BiodiversityCreditAlliance「BCA’s Mission」
出典:BIODIVERSITYCREDITS HP
生物多様性クレジットのトレンドについて
生物多様性クレジットの普及と現在の状況について解説します。
(1)生物多様性クレジットの普及時期
生物多様性クレジットの制度は、異なる国や地域で異なる時期に導入されており、具体的な最初の導入時期や場所を特定するのは難しいのですが、「生物多様性クレジット」というフレーズは、少なくとも20年以上前から科学的な文献や保全政策の文献に登場しています。
一方で、2022年8月から、オーストラリアのニューサウスウェールズ州では新規申請に関する生物多様性クレジット供給基金が設立され、オーストラリア連邦政府は2023年4月に新たな生物多様性クレジット市場の立法を導入するなど、生物多様性クレジットの制度がまだまだ進化・改善されています。
出典:NSW Department of Planning and Environment「About the Biodiversity Credits Supply Fund and Taskforce」
(2)生物多様性クレジットの現状
- 普及面
普及の現状について、生物多様性クレジットを扱う企業は、国際的に増えてきています。その理由として、単にマイナスの影響を埋め合わせるカーボンオフセット等の仕組み・効果との違いにあります。つまり、生物多様性クレジットにより企業は、自然の回復に資金を提供することが可能となるため、企業が生物多様性に直接プラスの影響をもたらすことができる点が高く評価されています。
- 開発面
開発面の現状については、カーボン・クレジット会社、植林会社、大学、研究所、自然保護団体、コンサルタント会社といった多くの企業や団体が生物多様性クレジットの開発に取り組んでいます。
- 課題
問題点の現状として次のものが挙げられます。まず、自然保護の進捗を測定する単一の基準が存在しません。そのため、生物多様性クレジットの効果を客観的に評価することが困難となっています。また生物多様性クレジットについて専門家の間では、クレジットがどのように使用されるべきか、そもそもクレジットという名称は正しいのか一致した見解がなく、用語法、使用面についてもさらなる検証が求められています。
出典:The Yale School of the Environment「Pricing Nature: Can ‘Biodiversity Credits’ Propel Global Conservation?」(2023/4/6)
出典:REUTERS「Analysis: COP15 debates whether biodiversity credits can put a value on nature」(2022/12/13)
生物多様性クレジット制度の将来展望に関して
生物多様性クレジット制度の市場は、天然資源の保護、環境リスクの軽減、気候変動の影響へ向けた重要な機会をもたらしています。
例えば、一部の海外企業は、1ヘクタールの生息地とその野生動物を少なくとも10年間保護または回復することを目的とした生物多様性クレジットを開発しています。このような取り組みは、国連環境計画、国連開発計画、スウェーデン開発庁からの資金援助を受けており、また生物多様性クレジットの開発を目指す炭素クレジット会社、植林会社、大学、研究所、自然保護団体、コンサルタント会社など、多くの企業や団体が参加しています。
さらに、生物多様性分野に関わる関係者やプロジェクト推進者の数は急速に増加しており、今後も増え続けると予想されています。
なお、市場は急速に発展していますが、プロジェクトの明確性、厳格な測定・報告・検証、二重カウントの防止といった問題も存在することに留意する必要があります。
まとめ:生物多様性クレジットのような新しい環境保護を知り、今後求められるであろう企業の社会的責任を果たせる準備をしておこう!
生物多様性は私たちの生活に重要な役割を果たしており、クレジット制度はその保護と支援を促進するため、世界的な関心が高まっており各国や地域で導入が進んでいます。そして、生物多様性クレジット制度は生物多様性の単位で取引可能であるだけでなく、カーボンニュートラルの達成にも貢献できる大きな手段であると位置づけられています。
今後はさらなるクレジット制度の発展が予想されており、それによって各国のカーボンニュートラルに対する取組が加速していくことが予想され、ひいては会社の社会的責任としての側面が大きくなっていきます。そのため、今からカーボンニュートラルに関連する知識を増やして、準備をしておきましょう。